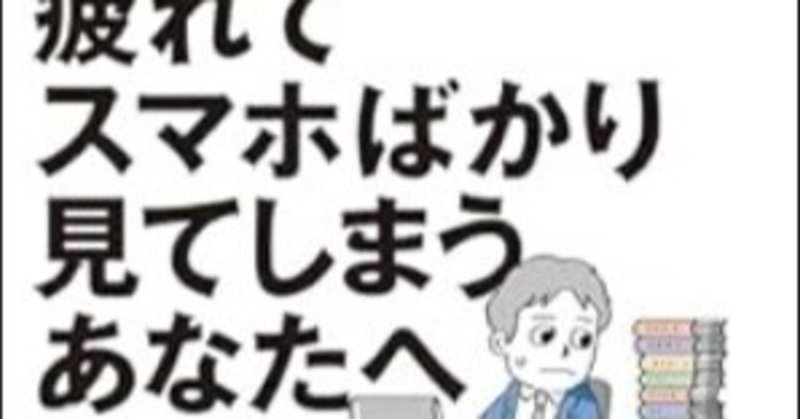
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んで
おはようございます。
2児の子育て中の日本史教員、たこぽんです。
三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読みました。

この帯のフレーズ「疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ」瞬間、「これ、私のことだ」と思って、衝動買い的にKindle版を購入。
すごく良かったので読書感想文を書いていきます。
まず読んでみて思ったのが、「思っていたのと違う」
この表紙とタイトル見て、皆さんどんな本だと思います?
私は「バリバリ自己啓発系のビジネス書」だと思いました。
割とビジネス書はよく読む方なので、そういうものを想像して読み進めていったのですが・・・。
いい意味で「思ってたのと違う」。
話は著者自身が、本を大好きだった読者が社会人1年目で全く本を読んでいなかったことに気づき「なぜこんな社会なの?」と感じるところからはじります。
で、それを理解するために、読書の歴史を紐解いていきます。それも明治時代から。
一瞬「そんな昔から振り返るんかい!」と思いつつ、この視点いいなと。
だいたい普通のビジネス書って「本が読めない!」となると
やれ「スキマ時間を作りましょう」とか「本を読みたいというマインドを大切にしましょう」とか、なんか小手先のスキルの話になっていくんですよね。
本書はもっと歴史的なところから「読書」という行為を見ていきます。
それが日本史教員としてはものすごくツボでして・・・。
・「西国立志編」は自己啓発本のはしり
・「円本」は初の「積読」本
・司馬遼太郎は「ノスタルジー感覚」で読まれた
教科書の歴史用語と現代社会がつながっていく感覚がものすごくいいですね。
なのでこの本、少しでも歴史に興味がある方は読んでみて損はないです。
「ノイズ」を避ける社会だから「本が読めない」
著者の三宅さんはそもそも「読書」は「ノイズ」を取り込む行為だと言っています。
自分の中にない考え方を取り込もうとするとき、人はその情報を「ノイズ」と感じる。
でも、そのノイズを取り込むからこそ、その知識が「教養」となるわけです。
現代社会は働くことに対して「全身全霊」で取り組むことが求められている。
「自己実現の手段」と考えられるようになってきて、仕事を「全身全霊」でやり切ることが大事であると。
しかし、そうなると心も身体も疲れてしまって、読書の「ノイズ」に耐えられない。
そして、「ノイズ」情報ではない単純なスマホゲームとか、SNSのフォローしている情報を
見ているのが心地よくなってしまうわけです。
ものすごくこの考え方、共感ですね。
私も仕事帰りの電車内、「読書したい!」と思うのにスマホを見てしまう・・・。
仕事のあと疲れた状態だと読書したとしても、本の内容が頭に入ってこない「上すべり感」
があって、結局読書をやめてしまう・・・。
疲れすぎていて読書という「ノイズ」に耐えられないわけですね。
育児に対しても「全身全霊」しすぎだったかも
本書では「半身」の姿勢が大事だと言っています。
なんでもかんでも「全身全霊」でとらえて疲れ切ってしまうのではなく「半身」で働く。
これは仕事だけでなく、趣味や家庭、育児もそうだと。
とそこで自分、育児についても「全身全霊」でとらえていたのかも、と気づきました。
自分には6歳の娘と2歳の息子がいるのですが、ここのところ、よく土日に一人で子ども2人をみることがあります。
・休みの日は子ども達を公園に連れて行かなければいけない。
・外出先で子ども達を静かにさせていなければいけない。
・〇〇時〜〇〇時まで、お昼寝をさせなければいけない。
・〇〇時までにお風呂に入れて、夕ご飯を食べさせなきゃいけない。
はじめの頃はなんとなくでやっていたことですが、これがルーティン化してしまい、
自分の首をしめていたのかもしれないなぁと。
多少夕ご飯の時間がずれたとしても、たまには一日家の中にいたとしても、いいじゃない。
こういう「半身」の姿勢がなかったから最近、子育てが楽しめてなかったし、
読書もゆっくり楽しめていなかったのかも、と。
「全身全霊で一生懸命がんばること」がいいことと凝り固まってしまっている時、
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んでみるのがオススメです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
