
❖ルーティンにしやすいものとそうでないもの❖ まいに知・あらび基・おもいつ記(2021年12月17日)
(長さも中身もバラバラ、日々スマホメモに綴る単なる素材、支離滅裂もご容赦を)
◆ルーティンにしやすいものとそうでないもの◆
持論だが、なかなか上手く取り組めないものは、ルーティンとして、日常の当たり前の動きの中に組み込んでしまえば、できるようになると思っている。そう考えるようになったきっかけは、高校時代の学習習慣である。私の高校は当時、3分の2の生徒が寮生活をしていた。寮では高校1年生のとき「義務自習」と呼ばれる学習時間があり、夜の8時から11時まで1日3時間、自習室に「軟禁」され、私語禁止・ジェスチャー禁止で黙々と勉強していた(自習だが義務というよく考えると不思議な名称だった)。この義務自習の使い方の中で、自分が苦手で敬遠しがちだった科目については、短い時間だがいつも決まったやり方で、ルーティンとして組み込むと、取り組めることに気づき、その経験がその後の生活でも活かされてきた。そしてこの経験を活かし、ルーティンとして上手く継続できていることがある。それが毎日1つ記事を投稿することである。これまでも様々なSNSで毎日投稿にチャレンジしてきたが、本当に毎日継続できたものはなかった。去年、自分の担任クラスに配信していた朝コラムはかなり毎日投稿に近かったが、日曜は配信していなかったので連続ではなかった。しかし9月終わりからスタートした「まいに知・あらび基・おもいつ記」は本当に1日も途絶えることなく、現在80日以上の投稿ができている。これについて私が決めたルーティンは、3つのステップに分かれている。①素材となるアイデアを投稿しようと思った時点で出そうとすると、途中で止まったり、捻り出そうとか絞り出そうという無理が生じてしまったりするので、日中の隙間時間で自由に緩くスマホにメモしておく、②夜、寝る頃になってそのスマホメモを見て、明日投稿したいと思ったものをSNSの下書きに移し替え、一読して、論理破綻や飛躍が酷い場合は多少体裁を整えるようにする、③翌日、もう一度読んでみて、夜中のポエム的な盛り上がりになっていないか最終チェックをしてから投稿ボタンを押す。このようなステップに分けることで、①アイデア出し、②清書、③見直しという行動の棲み分けがきれいに成立するので、このルーティンが連続投稿を可能にしていると思う。特にアイデア出しは、決められた時間内での無理矢理なものでは、ストレスやプレッシャーのせいで上手くいかない。隙間時間でのんびり行うから上手くいっているのだと思う。そして清書は、既にある素材を整えることに専念できるので、これもストレスやプレッシャーが軽減される。最後に見直しは、一応、投稿が表現物である以上、最低限のマナーを守らねばならないリスクヘッジでもあるし、単なる勢いやノリに頼らないからこそ、その浮き沈みで投稿の成否が決まらないシステムになっているので、継続できているのだと思う。このように毎日投稿のようなアウトプットルーティンは上手くいっているのだが、なかなかルーティンにならないものがある。それはインプットルーティンである。私は大学院を修了した後も、研究者になりたいという思いを引きずっていて、大学院時代にかなりお世話になった雑誌の定期購読を続けている。その雑誌は「国際法外交雑誌」である。これを読むことで、最新の研究成果をインプットしながら、論文を書けたらなどと淡い思いを抱いているが、このインプットが上手く続けられない。雑誌を読む時間を決めてみたりするが、なかなか定着しないのである。毎日投稿や高校時代の勉強との違いは何なのか考えたとき、雑誌読みにはなくて、毎日投稿や高校時代の勉強にはあった要素に気づいた。それは「行動の可視化と積み重ねの実感」である。毎日投稿は自分が取り組んだ行動がウェブ上に成果として可視化され、その履歴は自分がどれだけ続けられているか認識でき、その履歴に手ごたえを感じているように思える。そして高校時代の勉強でも、私は三時間の勉強時間を10分刻みで18個の枠と捉え、勉強時間の内訳をノートに記録していた。取り組んだ教科ごとで色を替え、実行したらその枠を色で塗り潰し、枠内にどんな勉強をしたか簡単に内容を書き込んでいた。そうして学習成果が形になって積み重なっていくことにやり甲斐みたいなものを感じていたのだと思う。このように自分の行動が成果としてどんどん集積されていく事実は、見た目にも分かりやすく、直接的なモチベーションになっているのだろう。これらと比べ、雑誌読みは行動を可視化していなかった。そして、単に「やらねばならない」というようなノルマになってしまっていた。そのためモチベーションを生み出す仕掛けが不足していたのだと思う。今回の気づきを材料にして、雑誌読みのルーティンを、どのような形式で「行動の可視化や積み重ねの実感」に結びつけられるか考えてみたい。それによってモチベーションが生まれれば、雑誌読みも継続できるだろう(ちなみに、最近の国際法外交雑誌は「COVID19特集」であった。感染症がこの雑誌に特集テーマになっていることからも、国際社会で協力しなければならない分野は多岐にわたり、ますます増えていることが分かる。SDGsのゴールならば3や17が特に関係していると思われる)。
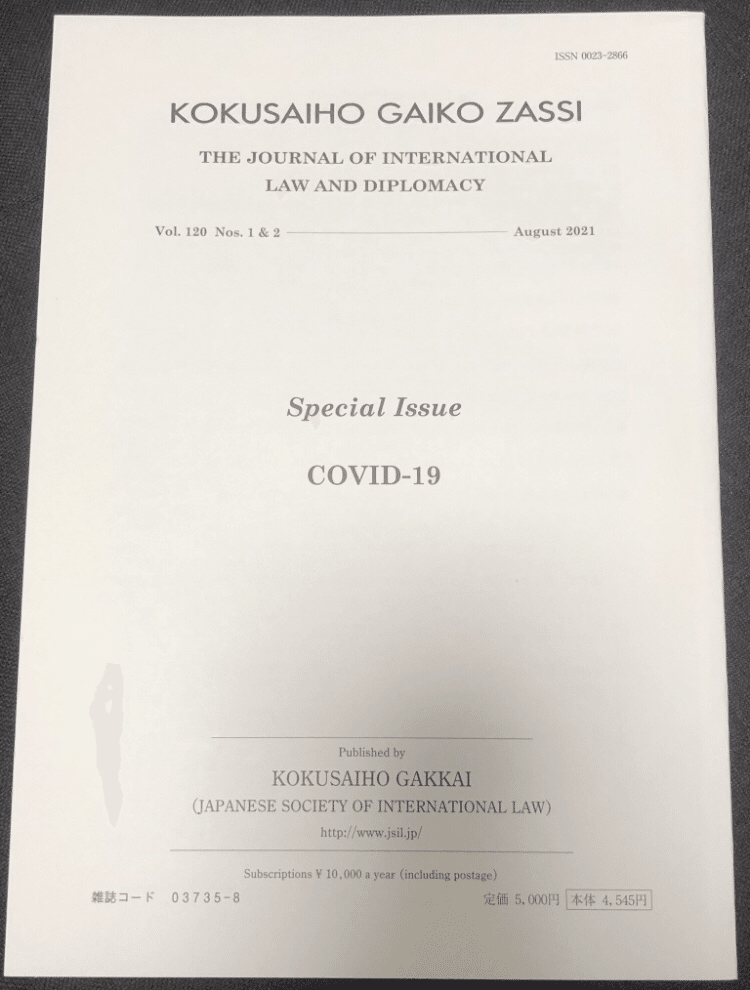



この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
