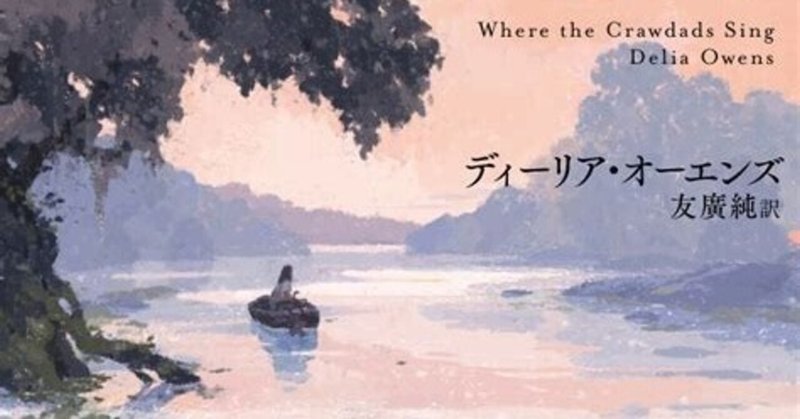
書評:ザリガニの鳴くところ
物語の舞台は、アメリカはノースカロライナ州の小さな村からさらに森の奥に入っていたところにある湿地だ。時代は1950年代から1970年。主人公のカイアは、湿地の森の中で両親と兄姉たちと暮らし、学校にも通うことなく育った。湿地には、借金から逃れたもの、奴隷から逃れたものなど、訳ありの人たちが住み着いていた。戦争で傷ついたカイアの父親とその家族も似たような存在だった。湿地に住む白人たちは「ホワイトトラッシュ(白い屑野郎)」と蔑まされていた。
酒を飲み、家庭で暴力をふるう父親に耐えきれず、まずは母親、そして3人の兄弟たちが次々と湿地を後にする。幼いながら孤独になっていく哀しみに耐えようとするカイアの姿は痛々しいほどだ。そして、ついに父親もどこかに行ってしまう。若干6歳。母が教えてくれたわずかな生活の知恵をたよりに生きていく。生きていくしかないのだ。
わずかながら頼れる人たちもいた。湿地で採った貝を買い取ってくれたり、境遇を知り気にかけてくれる黒人の雑貨店主ジャンピンとその奥さんのメイベル、そして兄の友人だったテイトだ。少し年上のテイトは、文字の読み方を教えてくれた。
文字は、カイアの世界を広げてくれた。自然に関する本を多く読んだ。湿地に棲むさまざまな動植物や日々変化する湖沼の環境と一体となって生きている彼女の中に、自然科学の知識が真綿に水が染み込むように入っていく。
厳しい幼少期を過ごし孤独になって生きることの辛さ。
自然に囲まれ、文字を知り学ぶことで、自然の神秘にのめり込んでいく素晴らしさ。
独りで生きていくんだと決意しながらも、人を恋しく思う気持ち。
読み進めるうちに、カイアの引き裂かれる感情が何度も胸に迫ってくる。また同時に、全く境遇の違う自分は、果たしてどこまでカイアに「共感」できているのだろうか?という思いにもかられる。今、自分が感じているこの痛みは、カイアのそれには到底及ばないのだと。
それでも、読者として彼女の心象風景を想像するために、助けになってくれるのが、美しい自然の描写だ。
自分を捨て出て行ってしまった母のことを、極度のストレス下では、子どもを置き去りにすることもあるキツネの話になぞらえて考えること。カイアの激しい感情の揺れ動きに同調するように描かれる海の潮流や潮衝ののダイナミックな描写。そして、喜ばしい回想場面で描かれる、大きな鳥の群れが飛来する、息をのむような光景。
カイアの心象風景の描写と素晴らしい自然の描写が重なる名シーンが、物語全編にわたっていくつも織り込まれている。何も知らずに読み始めた読者は、この小説の著者は、どうしてこんなにも美しく、繊細に、自然界で起こる神秘的な光景を、読み手がまるで目の前で見ているような気持ちにさせるような描写ができるのだろうか、と不思議に思うに違いない。それもそのはず、著者は一流の動物学者なのだ(その事実を知り、再度驚かされることになる)。
物語を読むことことの喜びは、自分ではない誰かの物語を追体験できるところだ。そして、この小説「ザリガニの鳴くところ」の大きな魅力のひとつが、厳しくも優しい「自然」とカイアの間に交わされる交流と交感を追体験させてくれる。
彼女の辛い境遇に共感を寄せるのが難しいのと同じように、その境遇がもたらした彼女と自然の分かちがたい関係も、簡単に想像できるものではない。それでも、彼女だからこそ築くことができた自然との関係から、気づきを得ることも多かった。
それは例えば、孤独とは何かを考えることだ。
カイア自身、長い孤独のせいで自分が人とは違う振る舞いをするようになったことに気づいていた。しかし、好んで孤独になったわけではない。カイアは大半のことは自然から学んだ。誰もそばにいない時、自然がカイアを育て、鍛え、守ってくれたのだ。たとえ自分の異質な振る舞いのせいで孤独になっている今があるのだとしても、それは、生き物としての本能に従った結果でもあった。
孤独がカイアの独自の知性と生きる哲学を培った。物語の中で、カイアはいくつかの恋や別れ、裁判といった人や社会との関わりを持つ。そこで生まれる喜びや苦しみは、一見、読み手である私たちにも理解できるように感じられるし、だからこそ小説を楽しむことができる。しかし、紙一重のところでやはり、カイアにしかわかりえない境地があるのだということに気づかされる。それはまさに、メタファーとしての「ザリガニの鳴くところ」なのだと思う。深い深い森の奥のことだ。
カイアにとって、ザリガニの鳴くところとは、どういうところだったのか?この問いは、小説を読み終えたら分かるという類の問いではない。それでも、いやそれだからこそ、ぜひこの小説を読んで、深い森の奥、ザリガニの鳴くところに思いをはせてみてほしいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
