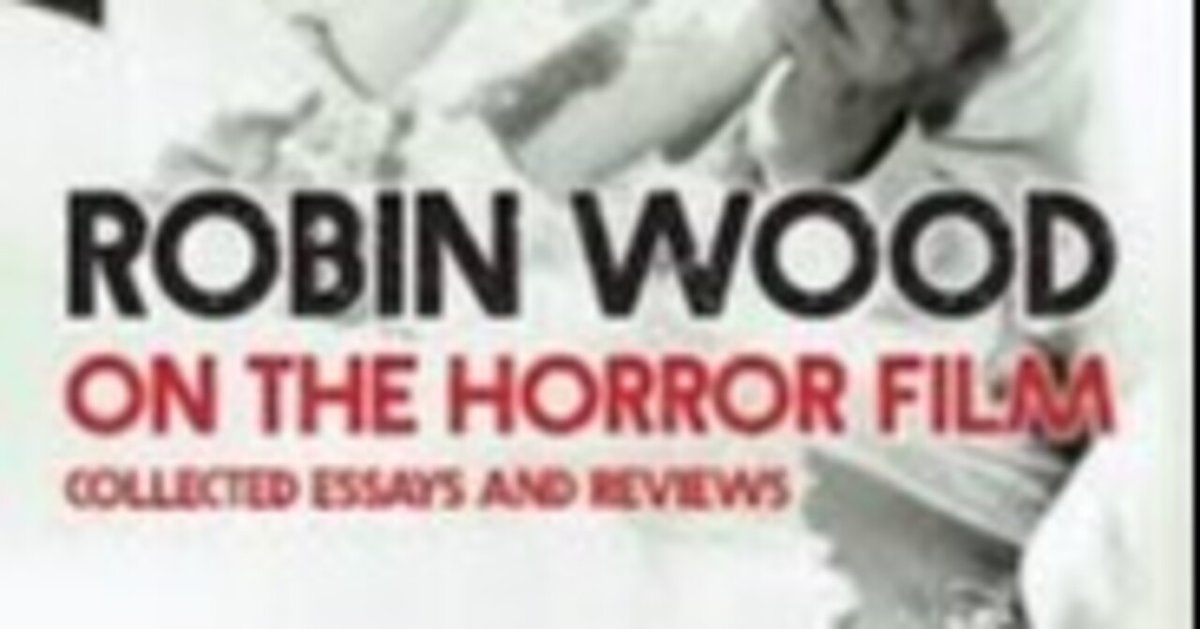
ソーシャルスリラーとホラー映画から見る現代社会 ②ロビン・ウッドの論から見たソーシャルスリラー
今回は、ホラー映画に関する優れた論評を残したロビン・ウッドの論を紹介し、彼の論を援用しつつ、ソーシャルスリラーの三大要素について考察してみる。内容は、ウッドの著書『Robin Wood on the horror file : collected essays and reviews』を元にする。
映画批評家、ロビン・ウッド
ロビン・ウッドは、1931年にイギリスで生まれ、後にカナダで活躍した映画批評家である。同性愛者であることを公表していたウッドは、フェミニズムとフロイト心理分析の観点からホラー映画を考察した。ちなみにウッドはジョージ・ロメロ監督の『ゾンビ』三部作を非常に高く評価し、同著「THE WOMAN'S NIGHTMARE Masculinity in Day of the Dead」で同シリーズを「現代アメリカ映画の特筆すべき、大胆な業績の一つ」と述べている。同著の中でウッドは「三作は併せて、アメリカ文明の主流についての暗示的でラジカルな社会政治的な批評を構成している」(431ページ)と述べており、それぞれの作品は、核家族の破壊(『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』(1968年))、消費主義の批判(『ゾンビ』(1978年))、男性性への批判(『死霊のえじき』(1985年))だと指摘している。ウッドが現在の映画のトレンド、すなわち男性性への批判が高まっている状況を見たらどう考えるだろうか。
少々憶測の域に入ってしまうが、ウッドのアメリカ映画に対する目線は、概ね八十年代に特有のアクション映画(アーノルド・シュワルツェネッガーやシルベスター・スタローンが主演するような作品)には批判的で、社会そのものの破壊を含んでいるような『ゾンビ』三部作を讃えているという辺りに、どことなく自分に似たものを感じている。彼は心底アメリカの映画が好きなのだと思うが、マルクス主義やフロイト心理学の視点から、アメリカ映画に対して批判的な立場を取っている。私はこの5年程アメリカ映画に対して、熱烈に愛しながら、同時に貶すような態度をとって来たような気がする。そして今、自分の位置がよく分からなくなった。ウッドは、どんなにアメリカ映画を批判しても、英語のネイティブとしてアメリカ映画を「我々の文化」と言える、同じ文化圏の人間として生きた。私はどんなにアメリカ映画を愛しても、未だに字幕無しでは完全に理解できないし、字幕と原語で理解したつもりでも、あくまで外から憧れ、惹かれつつもそこに入ることはできない…歪みを生じ、心にモンスターを育ててしまうのはいつも私の方である。次に紹介するウッドのモンスターの概念はそういう意味で気になっているのだろう。
モンスターが「正常」を脅かす
さて、ウッドは、同著の「RETURNING THE LOOK: Eyes of a Stranger」で八十年代のホラー映画の特徴を論じるため、それ以前の伝統的ホラー映画の構図に言及している。曰く、かつてのホラー映画はモンスターが「正常」を脅かす形式だったと。また「正常」を象徴するのは妻タイプの女性で、未来のモノガミーの核家族を構成することが期待されるタイプの女性であり、それをモンスターが脅かし、奪いに来る、と見做していた。1931年のジェームズ・ホエール監督『フランケンシュタイン』に関しては「What the monster really threatened was the repressive, ideologically constructed bourgeois "normality." (モンスターが真に脅かしていたものは、抑圧的でイデオロギー的に構築されたブルジョワの「正常」であった)(265ページ)」と書いている。それ故に、その種の映画では「正常」を象徴しないタイプの(つまり娼婦タイプ)女は殺されることになっていると指摘している。
ここで、「正常」を脅かす古典的ホラーに出ていたモンスターの役割について考えたい。ウッド自身は、「the monster was in general a "creature from the id," not merely a product of repression but a protest against it(そのモンスターは一般に「イド(著者補足 衝動と本能をつかさどる)からの生物」であり、単なる抑圧の産物ではなく、それ(抑圧)に対し抵抗であった)(263ページ)」と指摘している。
ウッドは、モンスターが女性への攻撃を行う点については一定の批判をしているものの、「正常」を脅かすモンスターに対して「ブルジョワ的な体制に対する抵抗」という、マルクス主義的な観点から積極的な意義を見出している。
しかしながら「正常」の世界に住む登場人物の日常にとって、モンスターとはただ単に危険な存在である。そもそもホラー映画を今娯楽として観る我々は、半ばブルジョワ的で、半ば労働者として生きているため、モンスターは怖い。また、ホラー映画おけるもう一つの女性類型である娼婦タイプとされる、男性の意のままにならない女性はいつもモンスターの犠牲になっていた。
一方、超自然的な力や異様な容姿を持つが故に社会から排除されて来たモンスター(抑圧された存在)は、どこか肩身の狭い思いをして育ってきたタイプのホラーファンやホラー作家にとって同一化しやすい存在でもあろうし、そのモンスターが暴れ、そして主にヒーロー役の男性に退治される物語は視点を変えれば悲劇的である。それを転換して見せた『シェイプオブウォーター』の監督ギジェルモデルトロは、モンスターや怪獣への愛を語っている。実は私は彼の作品を今ひとつ愛せていない。同作も見終わることができなかった。モンスターをどう捉えているかの違いではないかと思うが、私にとってのモンスターとは、自分がそれではありたくない、自分の中に存在を認めたくない、故に真に恐るべき存在なのだと思う。本論ではその意味でモンスターを捉える。
ところで、モンスターの暗示するもの(抑圧され出てこられないようにされているもの)も、「正常」に包摂されるものも常に変化し続ける。ホラー映画が大きく発展を遂げた70年代から現在に至るまで、両者は大きく変動してきた。例えば、『エルム街の悪夢2 フレディの復讐』(1985年)では、シリーズを通じて夢の中で人々を殺害する殺人鬼フレディ=モンスターは抑圧されたホモセクシュアルな欲望の具現化として明確に描写されている(故にラストシーンの不気味な笑い声はその欲望はクローゼットの中には押しとどめられることはないことを暗示する。まさに「正常」に対する抵抗ではないか!)。しかし今はホモセクシュアルの欲望をモンスターとしては描くことは無いだろう。それぞれ時代の許容範囲や流行を参照しながら、個々人は自分の「正常」を書き換え続ける。それぞれ流動的であるモンスターと「正常」は時には入れ替わり、互いを意識し合って来たと思う。
私はその当時の映画作品に詳しくないものの、敵の浸透を恐れた冷戦初期には宇宙からの侵略ものの映画が流行したという。また『エクソシスト』(1973年)、ハリウッドリメイク版の『呪怨』(2004年~)シリーズ、昨年Netflixドラマの『真夜中のミサ』まで、一部のアメリカのホラー作品は、悪魔や怨霊は外国から入り込んでくると描く。また『ゾンビ伝説』(1988年)、『ホステル』(2005年)、『ミッドサマー』(2019年)に至るまで、アメリカ人は、海外でモンスター的な人物や超自然的存在と遭遇する。モンスターとは他者であり、異常な存在である。ホラーではそれらのモンスターを追い払うか殺害する。或いは異常を目にしてパニックに陥っても、無事にアメリカに逃げ帰ることができれば、再び自分たちの「正常」が回復されるということを非ホラーの『セックス・アンド・ザ・シティ2』のラストシーンが物語っている。
一方、ソーシャルスリラー作品は、モンスターはアメリカの文化の中に存在し、内部の「正常」を脅かしていると指摘している。
ソーシャルスリラーの三大要素
実際のところ、マルクス主義とフロイトから強い影響を受けているウッドの言う「正常」や「殺害=処罰」の意味と重みはもう少し検討した方がいいようにも思うが、「異常」つまりウッド言うところのモンスターが「正常」を脅かすという伝統的な構図は様々なアメリカのホラー作品の特徴をうまく切り出してくれるように思う。一旦ホラーの一つのトレンドであるソーシャルスリラーに適用すると、同作品群の中でモンスターが脅かす「正常」とは何か、また「正常」の側が何をモンスターとして見做しているかがはっきり分かるのではと考え、以下のようにまとめてみた。
①強者の属性がモンスター性を含んでいる
②弱者が「正常」を代表する
③「正常」が復讐の形で「異常なモンスター」を打倒する
①強者の属性がモンスター性を含んでいる
人種や民族、性別等の理由に基づく差別を描く映画であれば、非ホラー作品でも①を含んでいる。ここでの「モンスター性」とは何なのか。異常性の暴走という点では負けず劣らずの80年代のスラッシャーホラー(殺人鬼が連続殺人を行い、血しぶきが飛ぶ場面の連続を含む映画)の殺人鬼たちには、強者の属性への紐づきが確認できない。確かに男性がモンスターとなるケースがほとんどで、彼らを強者属性のモンスター達だと見なすこともできるが、彼らはそもそも社会から逸脱した「被抑圧者」の要素を持っている。そして、別の男性(ヒーロー役)や、女性によって退治される運命にある上、製作会社が続編製作を決定し、蘇る度に怖さが減退していった。それと比較すると、ソーシャルスリラー作品に描かれる「異常」な言動や欲望は、現実に存在する強者の属性(男性や白人)に紐づくように表現されている。この点が、社会的な規範、「正常」から「抑圧」されていた、故に抑圧に対抗する道も開かれているとウッドが考えた過去のモンスターたちとは一線を画している。むしろ、かつてモンスターからヒロインを救出したようなタイプの強い男性たちこそが新しい「異常」の源泉である。
②弱者が「正常」を代表する
②は、正義や「正常」を体現している人物が、強者に対置される弱者属性を帯びているということを意味している。もちろん、80年代ホラー『ポルターガイスト』シリーズに顕著な異性愛の核家族像(同作ではその像が失墜していく)も依然として「正常」枠に入っているが、女性、有色人種、性的マイノリティなどの弱者属性が「正常」と正義を体現することにより、ソーシャルスリラー的な世界がより確固たるものになっている。
ところで、弱者が「正常」を代表しているということは、その弱者に内在する「異常」は作中で極力触れられないことになる。弱者である女性や有色人種や性的少数者(時にはそのすべてを兼ねる)の主人公が好ましくない行動をとる場合は、その理由が作中で説明されなければならない。例えば、『ハッピーデスデイ』の主人公が最初少し好ましくない言動をとるのは、彼女が過去と向き合えないからである。超自然的な体験を通じて過去と向き合い、好ましい人物に変化していく主人公に観客が同一化する仕掛けである。
③「正常」が復讐の形で「異常なモンスター」を打倒する
③は、②で弱者に同一化した観客が、弱者が正義を取り戻す様を体感するために必要である。そもそも、『親切なクムジャさん』(2005年)のような弱者から強者への復讐は映画として観ると痛快である(同作は復讐を遂げた後のクムジャの痛快とは程遠い心境をも描き出しているが)。一方、もし弱者が強者に敗北(殺害)されて終わる場合、その映画が批判せんとする「現実」と同じ結末になり、却って差別や抑圧、強者の暴力を告発する映画として力強いメッセージを放つ。それを敢えてホラーとして描いたのが、Amazon Primeのドラマ『ゼム』(2021年)シーズン1である。悲惨な人種的迫害を受けた後、ある街に引っ越してきた中流の黒人一家が、超自然的存在と近所の人々の両方から同時に人種差別の攻撃を受け、精神的に追い詰められていく物語である。また、白人の登場人物たちの言動は観る側にとって不快なまでに歪である。そのような露悪的な描写の連続によって、恐怖と不快感が主観的に混同されてしまうことも、ソーシャルスリラーの特徴の一つかと思う。
もし、あと一つ付け加えるとすれば、アメリカのホラーの系譜の中で、悪いものが自らの文化の中に根ざしていることを指摘している点がソーシャルスリラーの特徴である。故に、文化圏内の人にとって、本来直視することが難しいのではないだろうか。ソーシャルスリラー的な価値観を学び、自己と向き合い、自らを悔い改めるに至るのだろうか。そう考えると鑑賞体験自体がホラーである。
ソーシャルスリラーにおけるゲイ男性の立ち位置は。
ところで、同性婚して子育てをし、世間から認められているゲイカップルというのは、弱者なのだろうか、強者なのだろうか。核家族というレベルで捉えると旧来の「正常」であり、性的マイノリティというレベルでは、弱者であるが、同時に男性は強者に属する。まして白人であれば最強である。今後、同性愛者男性がアメリカの映画の中でどう描かれるか、非常に興味深い。非ホラー作品にも関わらず、ラスト10分のホラー性が七十年代オカルトホラー作品『オーメン』(1976年)に肉薄する『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021年)では、同性愛者男性が、攻撃的な男性性の装いをまとったまま処罰(=殺害)されている。日本よりも過酷な暴力に晒されるリスクがある社会において、弱者と強者の両方の属性を持つゲイ男性が、ソーシャルスリラー的な作品の中でどのような役回りを演じるか、興味深い。女性的なゲイは生き残り、男性的なゲイは処罰されやすくなるだろうか。『ブローク・バック・マウンテン』(2004年)のような物語も、今後は男性であるが故のモンスター性が妻や子供(弱者)にどう作用したかを問われるのかもしれない。『パワー・オブ・ザ・ドッグ』とはそういう映画だったのではないだろうか。
社会の問題を様々な形で描くアメリカ映画界と、その背景にある政治力と経済力に恐れ入る。アメリカとは、作中で観ているのが辛くなるほどに強い怨念が渦巻く場所であると同時に、それらのテーマを持つコンテンツがかなりの予算を得て製作され、多くの人々に消費されている。ソーシャルスリラー作品の存在は、種々の社会問題がホラー作品という娯楽的な形式で消費されていることを示す。そのこと自体が驚きでもあるが、ソーシャルスリラー作品は、現在しばしば話題に上るような話題をどのように描いているだろうか。考えてみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
