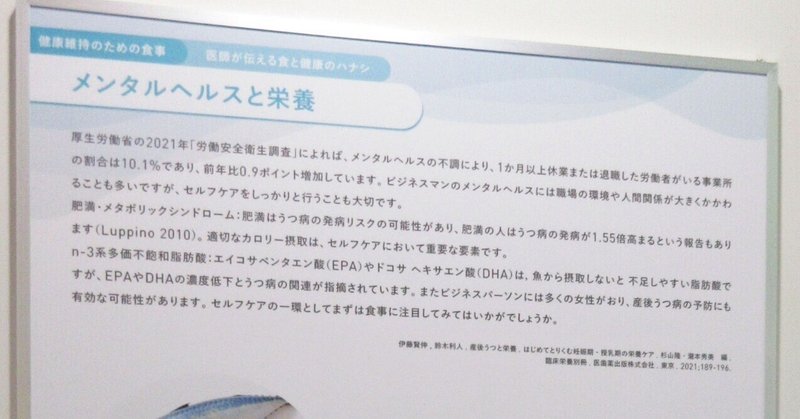
医師が伝える食と健康のハナシ:日本医学会総会2023東京 博覧会 セルフ ケア スタジオ 03
2023年04月22日、私は東京国際フォーラムを訪れ、一般客として、日本医学会総会 2023 東京 博覧会に参加した([1])。
その中の「セルフ ケア スタジオ」内の「医師が伝える食と健康のハナシ」で、順天堂大学医学部の医師らは以下の研究を紹介した。
01.やせていることは健康的ではないの?“やせ“に潜む健康リスクに要注意。(図03.01,[2],[3])。
2021年02月16日、順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学・スポートロジー センターの田村好史 先任准教授、河盛隆造 特任教授、綿田裕孝 教授らの研究グループは、日本人の痩せた若年女性 (BMI <18.5kg/m2) に食後高血糖となる耐糖能異常が多く、その原因として、主に肥満者に生じるインスリン抵抗性や脂肪組織の異常が関連することを世界で初めて明らかにしたことを発表した。
本研究成果のポイントは以下の通りである。
l 日本人の痩せた若年女性は標準体重者に比べて耐糖能異常の割合が顕著に高かった(13.3%)。
l 痩せた若年女性の多くは食事量が少なく、運動量も少ないという「エネルギー低回転タイプ」となっており、骨格筋量も減少していた。
l 痩せた若年女性の耐糖能異常の原因として、主に肥満者に生じると考えられてきたインスリン抵抗性や脂肪組織の異常となる「代謝的肥満」が関与する可能性を世界で初めて明らかにした。
本研究結果から、痩せた若年女性に対する取り組みとしては、十分な栄養と運動により筋肉量を増やすような生活習慣の改善が重要と考えられる。また、耐糖能異常の病態に、インスリン抵抗性も関与する可能性が明らかになったが、昨今の研究でインスリン抵抗性は運動をしたり、食事の脂質摂取割合を減らしたりすることにより改善する可能性が示唆されており、糖尿病の予防のためにそのような生活習慣の見直しが必要かもしれない。しかしながら、本研究で見つかった痩せた若年女性のインスリン抵抗性や脂肪組織異常が生じるメカニズムについてはまだ明らかになっていないため、更なる研究が必要である。
「エネルギー低回転タイプ」の女性が、筋肉の「量」と「質」を改善し、糖尿病になるリスクを下げるためには、まずはしっかり動いてお腹を空かせて、しっかり食べるという生活習慣に変えていくことが重要と考えられる。
食事では、バランス良く食べて十分な栄養を摂ることを心掛けることが大切である。やせた女性に多いのが、空腹のときにお菓子やパンだけを少し食べる、というパターンであるが、これはで摂取する栄養が炭水化物に偏ってしまう。筋肉の量を増やすために、肉、魚、豆類などでしっかりタンパク質を摂ることが勧められる。肉の脂には飽和脂肪酸が多く含まれるので、避けることを意識することが大切である。体に良い不飽和脂肪酸が多く含まれる魚や、脂質が少ない鶏肉がお勧めである。
さらに大事なことが、動くことである。目標にしてほしいのは、厚生労働省のガイドラインに示された「1日8,000歩」である。8,000歩は、距離にすると5~6 km、時間にすると80分程度になる。
この1日8,000歩という目標は、健康を維持するためのベース ラインである。これにプラスして、週に2回程度、軽いジョギングや筋力トレーニングをしたり、フィットネスクラブで体を動かしたりするなど、いわゆる「スポーツ」をすると、さらにいろいろな健康効果が得られる可能性がある。
以前は、「運動は30分以上続けないと効果がない」といったことも言われていたが、現在は、むしろ細切れに運動をした方が、食後の血糖値が上がりにくくなるなど、細切れでも様々な健康効果が得られることが研究で確認されている。
“ちょこちょこ運動”の目安は「30分に1回、3分間」である。なお、家の中でもできるおすすめの運動の1つが、その場で足踏みをすることである。
運動を続けるポイントは、日常生活の中で習慣化することである。
健康のための運動で大事なことは、一歩目を踏み出すこと、かつ、毎日少しずつ活動量を積み重ねていくことである。
日本では、痩せた女性(BMI 18.5 kg/m2未満)の比率が先進諸国の中で最も高く、特に若年女性では、痩せ願望を反映してその比率が約20%と極めて高い。
最近の研究により、中年以降と同様、痩せた若年女性でも糖尿病のリスクが高いことが分かったこと自体が、私にとっては意外である。
痩せた若年女性に対する取り組みとしては、十分な栄養と運動による筋肉量を増やすような生活習慣の改善が重要と考えられる。
やはり、「筋肉は全てを解決する」ということで(笑)。余談だが、大きなお世話とはいえ、筋肉が少ない痩せた若年女性を見ていると、「おいおい、このままだと糖尿病だけでなく、骨粗しょう症にも罹らないか」と思ってしまう([4])。

02.メタボリック シンドロームを知っていますか?メタボは食事で改善しましょう!(図03.02)。
順天堂大学 医学部附属 順天堂医院 糖尿病・内分泌内科の佐藤淳子 医師・准教授([5])は、メタボリック シンドローム(通称メタボ)を解説した。
その予防には、適正なエネルギー量のバランスのよい食事と運動が重要である。男女ともに更年期の変化が内臓脂肪を蓄積させてしまうことが知られており、中高年は注意が必要である。特定健診は、メタボリック シンドロームに着目した健康診断で、生活習慣病の予防のために行うものである(図02.02)。

なお、2017年10月20日、順天堂大学大学院医学研究科・代謝内分泌内科学の金澤昭雄 准教授、佐藤淳子 准教授、綿田裕孝 教授、プロバイオティクス研究講座の山城雄一郎 特任教授らの研究グループは、株式会社ヤクルト本社との共同研究の成果として、プロバイオティクス飲料の継続摂取が日本人2型糖尿病患者の腸内フローラを変化させ、慢性炎症の原因となる腸内細菌の血液中への移行を抑制することを明らかにしたことを発表した。これらの結果は、糖尿病の発症メカニズムや病態の理解、新薬の開発に道を開く可能性を示した。
本研究成果のポイントは以下の通りである([6])。
日本人2型糖尿病患者におけるプロバイオティクス飲料の継続摂取により、
l 摂取群では便中の総ラクトバチルス属菌が増加し、腸内の善玉菌も増加した。
l 摂取群では血中の細菌数が減り、血中への腸内細菌の移行を抑制することができた。
l 腸管バリア機能を強化することで慢性炎症を抑制する可能性を提示した。
バランスのよい食事と運動こそが重要ということで。
また、過信は禁物とはいえ、プロバイオティクスは、便秘・下痢症の改善、乳糖不耐症の改善、免疫機能改善による感染防御・アレルギー抑制、動脈硬化の予防、ならびに、抗腫瘍に有益であることは収穫である([7],[8])。
03.メンタル ヘルスと栄養(図03.03)。
順天堂大学 医学部附属 順天堂医院 メンタル クリニックの伊藤賢伸 医局長と小畑洋平医師は、以下を紹介した。
l 厚生労働省の2021年「労働安全衛生調査」によれば、メンタル ヘルスの不調により、1カ月以上休業または退職した労働者がいる事業所の割合は10.1%であり、前年比0.9ポイント増加している。ビジネス パーソンのメンタル ヘルスには職場の環境や人間関係が大きく関わることも多いが、セルフ ケアをしっかりと行うことも大切である。
l 肥満・メタボリック シンドローム:肥満はうつ病の発病リスクの可能性があり、肥満の人はうつ病の発病が1.55倍高まるという報告もある(Luppino 2010)。適切なカロリー摂取は、セルフ ケアにおいて重要な要素である。
l n-3系多価不飽和脂肪酸:エイコサペンタエン酸(eicosapentaenoic acid:EPA)やドコサヘキサエン酸(docosahexaenoic acid:DHA)は、魚から摂取しないと不足しやすい脂肪酸であるが、EPAやDHAの濃度低下とうつ病の関連が指摘されている。またビジネス パーソンには多くの女性がおり、産後うつ病の予防にも有効な可能性がある。

様々な人達が言及しているが、心身の健康を保つためには、ビタミン、鉄や亜鉛などのミネラル、必須アミノ酸、EPA、および、DHAを含む食品をバランスよく食べつつ、エネルギーばかり摂り過ぎてしまいがちな加工食品をできるだけ避けるようにすることが大事ということで。ちなみに、伝統的な和食は、魚や大豆製品が多く、メンタル ヘルスの観点でも好ましいと言える。主食は量を控えめにし、精製度の低い穀物(白米よりも玄米など)を選ぶことが勧められる。ただし、和食は塩分が多いことと、乳製品が摂れないことに注意が必要である。減塩を心がけるとともに、ヨーグルトや牛乳などを補う方がよい。
また、食事の際には、最低一品、スープなど温かいものを取り入れる方がよい。温かいものが並ぶ食卓は、体だけでなく、心も温めてくれるからね。
それに、今のご時世、インスタグラムやツイッター、家族、友人へのSNSなどに食事内容を掲載することも一興である。こうすることで、食事選びに張り合いがでたり、共感してもらったりなど、孤食のマイナスを補うことができるわけだし。実際、私もそうしている([9],[10],[11])。
上記の件から、バランスのとれた食事や適度な運動が心身の健康を保つことを改めて痛感した。こうしたことは、「言うは易く行うは難し」とはいえ、やるしかない!
参考文献
[1] 第31回日本医学会総会2023東京 展示事務局.“第31回日本医学会総会 博覧会 ホームページ”.https://tsunagu-iryo.jp/minna-expo/,(参照2024年05月08日).
[2] 学校法人 順天堂 順天堂大学.“食後高血糖となる耐糖能異常が痩せた若年女性に多いことが明らかに~ 痩せていても肥満者と同様の体質 ~”.順天堂大学 トップページ.ニュース&イベント.2021年02月16日.https://www.juntendo.ac.jp/news/00217.html,(参照2024年05月11日).
[3] 学校法人 順天堂 順天堂大学.“やせていても「少食で運動不足」はハイリスク。若い女性も気をつけたい糖尿病”.順天堂 GOOD HEALTH JOURNAL トップページ.MEDICAL.2021年11月30日.https://goodhealth.juntendo.ac.jp/medical/000233.html,(参照2024年05月11日).
[4] とも内科クリニック.“骨粗しょう症”.とも内科クリニック ホームページ.https://tomo.clinic/osteoporosis.html,(参照2024年05月11日).
[5] 学校法人 順天堂 順天堂大学 医学部附属 順天堂医院.“スタッフ紹介”.順天堂医院 トップページ.診療科・部門.診療科・外来部門.糖尿病・内分泌内科.https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/tonyo_naibunpitsu/staff.html,(参照2024年05月11日).
[6] 学校法人 順天堂 順天堂大学.“プロバイオティクス飲料の継続摂取が日本人2型糖尿病患者にもたらす効果 ~腸管バリア機能強化による慢性炎症の抑制の可能性~”.順天堂大学 トップページ.ニュース&イベント.2017年10月20日.https://www.juntendo.ac.jp/news/02885.html,(参照2024年05月12日).
[7] 厚生労働省.“プロバイオティクスについて知っておくべき5つのこと”.厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』 ホームページ.医療関係者の方へ.コミュニケーション.《知っておきたい成分の知識》.https://www.ejim.ncgg.go.jp/pro/communication/c03/07.html,(参照2024年05月15日).
[8] 公益財団法人 腸内細菌学会.“プロバイオティクス(probiotics)”.腸内細菌学会 ホームページ.用語集.https://bifidus-fund.jp/keyword/kw030.shtml,(参照2024年05月15日).
[9] 沢井製薬株式会社.“心の健康にも食事は大切! メンタルヘルスと栄養の関係”.サワイ健康推進課 ホームページ.季節のテーマ.2023年07月.https://kenko.sawai.co.jp/theme/202307.html,(参照2024年05月18日).
[10] 株式会社 社会保険出版社.“第1回 食生活とメンタル ヘルス”.心と体のバランス 心も体も健康に トップページ.https://www.shaho-net.co.jp/kokoromokaradamo/01/index.html,(参照2024年05月18日).
[11] 株式会社 大賀薬局.“管理栄養士から見たメンタル ヘルス(心の健康)と食事の重要性”.大賀薬局 トップページ.コラム.2020年04月30日.https://www.ohga-ph.com/column/detail/?cms_id=98,(参照2024年05月18日).
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
