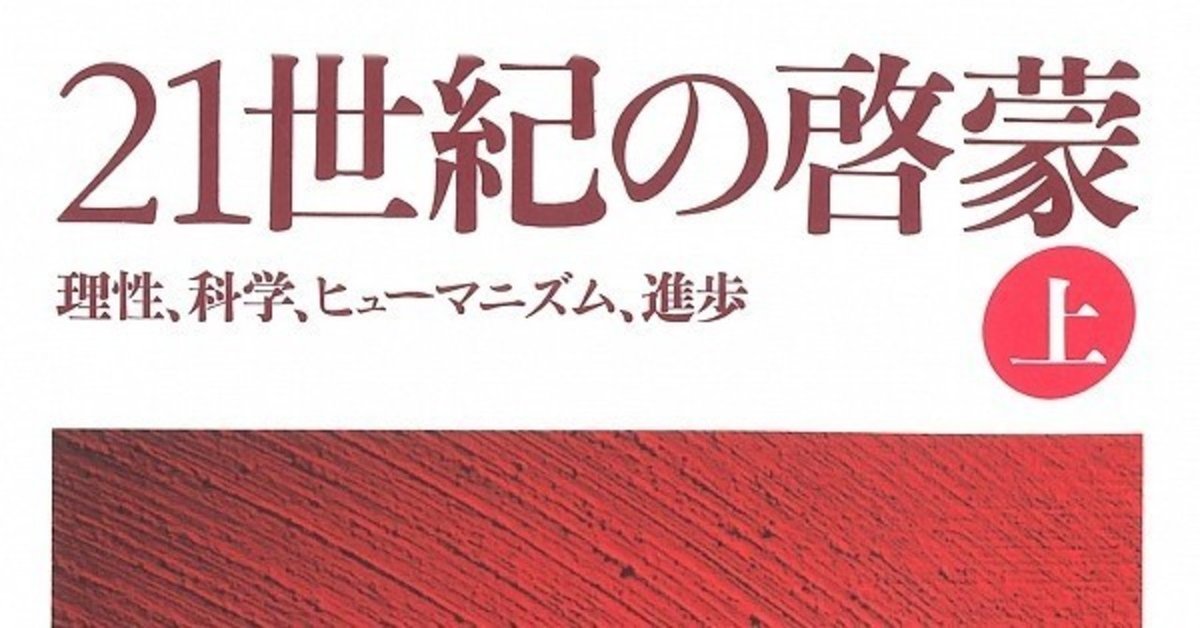
「21世紀の啓蒙」(スティーブン・ピンカー)未来に希望が持てて社会進化の過程がわかりつつ、薄っぺらな意識の高さ,ヒロイズムに鉄槌。ドヤ感にも満ちた、これぞ自己啓発本。
僕は心理学がどこからどこまでを範囲にしているのかよくわかっていない。通っていた大学でいくつか心理学の講義をとったけど、それはアンケートのとり方や、反抗期やホルモン、精神の恒常性(ホメオスタシス)といった、医学と哲学と社会学の間の常識を一度さらい直すようなものだった。
最近心理学と経済学を組み合わせた行動経済学が大ヒットを飛ばしている。ダニエル・カーネマンのファスト&スローが極めて面白かったので、そういう内容なのかと思って本書「21世紀の啓蒙」を読んでみたが、ファスト&スローとはまったくちがう。
ファスト&スローは、全編「人間はこういう勘違いをしやすい」という内容だ。人間にはパッと見で瞬間的に判断できるファストなシステムと、熟考して決断を出すスローなシステムがあり、どちらのシステムも鍛えることが可能で、強み弱みがあることについて、様々な研究成果、エピソードを積み重ねていく。
この「21世紀の啓蒙」には、そういう人間の仕組について書いた本ではない。社会全体、そして社会を前進させてきた啓蒙について、上下巻あわせて1000ページが費やされている。
人類の進歩について。でもそれだけではない
山形浩生さんもこの書評で触れているが、内容的にはファクトフルネスや進歩 人類の未来が明るい10の理由、繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史などに近く、これまでの各学会の研究データをまとめて、人類の平均寿命が伸び続け、貧困や飢えが解消され、教育や衛生が行き渡って世界が良くなっていることを豊富なエビデンスを出しつつ語っている。良くなっている事実だけでなく、成果を支えた技術や機序についても説明してるのは進歩 人類の未来が明るい10の理由と同様、読んでいてありがたい。
さらに「21世紀の啓蒙」では、技術だけでなくそれをもたらした啓蒙思想について解く。科学的思考がなぜ大事か、科学的思考は人間本来のものでなく努力して身に付けないとならないものだが、それでもなるべく多くの人が取り組むことがなぜ大事なのか。そして、人はみな平等ではないのだけど、平等目指して社会を作っていくことがなぜ人類全体の幸福につながるのか。
多様性を称賛し、努力することを解きながら、同時に社会全体で平等性を担保していくことを説く。そうきくと聖人や中国の君子を目指すような本に聞こえるが、本書で見られるピンカーの筆致はかなりアグレッシブなものだ。
ドグマ、思い込みに対するアグレッシブな筆致
べつの書でピンカーは「人間には遺伝的な差がある」ことを証明する本を書いてもいる。ポリコレ的には危険な内容だ。
アメリカ言語学会ではピンカーに対する除名運動が起きたが、それも警官の銃撃に対して、「人種差別云々でなくて警官の銃撃が多いことが問題」と説明したことがきっかけになっているようだ。
「21世紀の啓蒙」は社会の平等を強く訴える本でもあるが、平等はあくまで論理的な帰結にすぎない。本書の最大のメッセージは思い込みや偏見に頼らず、科学的思考を行おうというものだ。それが良いことでも非科学的な思い込みに頼るのは啓蒙にそぐわない。
そうしたドグマに対するピンカーの筆致は極めて攻撃的なものだ。
最高すぎるw
— TAKASU@Nico-Tech Shenzhen ニコ技深センコミュニティ (@tks) August 30, 2020
21世紀の啓蒙 239ページより pic.twitter.com/b5TyXF76xH
たとえばSDGsのブームについてはこの図を引用して過熱ぶりを戒める。
科学的思考については、「人文社会でなく科学を」と、人文社会を科学に含めないような言葉が見られる。
原子力発電は積極的に推進している(CO2を減らすほうが大事だし、エビデンスベースだと火力や水力に比べて発電量あたりの事故死者は少ない)
などなど、「これは思い込みだ、エビデンスベースでは違う」という筆致が多くを占める。
薄っぺらな意識の高さに鉄槌
そうしたドヤ感に満ちた攻撃的な筆致でありながら、本書が凡百の自己啓発本に堕していないのは、最終章「ヒューマニズムを改めて養護する」を中心に全編に渡って展開されるポピュリズムやエリート主義、「優れたものは劣ったものをリードすべきだ」というドグマに対する攻撃だ。
ニーチェを題材に厨ニ的なイキリっぷりを、トランプ現象を例にポピュリズムを、「この集団はまとめて劣っている」という決めつけに頼った判断を、ピンカーは攻撃する。
そうしたキャッチコピー手法や安易なオンラインサロンのような雰囲気で理解すること、群れることで理解したつもりになることに対する攻撃は、本書のもう一つの魅力だ。
全編アグレッシブな本書が、それでもアオリに終止しているように読めないのは終章がそうしたヒロイズム、意識の高さに対してさえも啓蒙をして終わる構成が、読後感を爽やかにしている。ピンカー教、ピンカーかぶれを招くような本ではない。
ページ数の割にストレスなく読めてわかりやすい本
章ごとにテーマがはっきりしているし、シンプルなメッセージに沿ってエビデンスを並べているので、ピンカーの意図にはそぐわないだろうけどナナメ読みもできてしまう。最初に関心あるところだけを読みはじめることもできる。分厚いにもかかわらずベストセラーになるのは、本自体のクオリティの高さもありそうだ。
この記事が参加している募集
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 深圳ほかアジアで見たものをシェアするマガジンをやっています。
