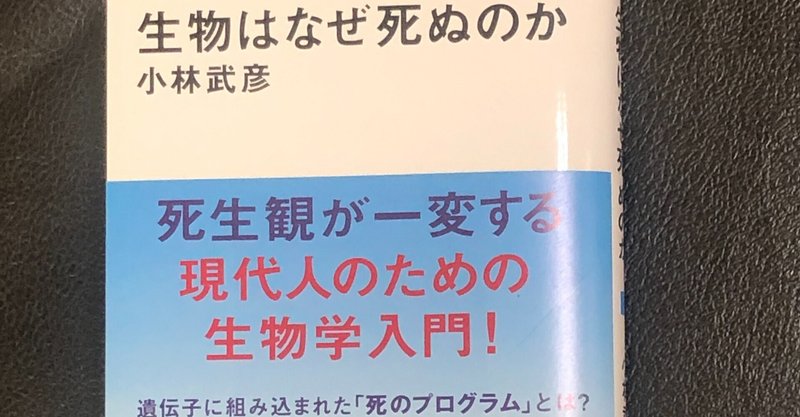
「生まれてきた以上、私たちは次の世代のために死ななければならない」に、死の恐怖を克服するヒントが隠されています。『生物はなぜ死ぬのか』
『生物はなぜ死ぬのか』は、生物に組み込まれた「死」の仕組みを解き明かすビジネス書です。
「死:作っては分解して作り変えるリサイクル」「コロナウイルス:風邪の原因」「生物の最大の法則:進化=変化×選択」など、死を通して進化の仕組みを学ぶことができます。
特に「進化の想定年齢:55歳/ヒトの最大寿命:115歳」は、がん化を防ぐ細胞の仕組みは55歳が限界で、ヒトは細胞の想定年齢の2倍以上長生きすることを明らかにしています。
細胞限界の55歳からは病気との闘いで、異常な細胞が急増していきます。
死が怖い方は、「老化抑制薬:メトホルミン/ラパマイシン/SIR2遺伝子などで無理やり延ばす」か、「進化の過程とあきらめる」か、の選択を受け入れる必要があるでしょう。
「身体の変化は、まずDNAに起こる」「栄養の摂取量が少し減ると寿命が延びる」「死は生命の連続性を維持する原動力」などを通して、死を感情論で拒否するよりも、論理的に死を肯定することの有用性を示しています。
特に「先進国の人口減少が引き金となり、人類は今から100年ももたない」は、人類滅亡を予言する一言です。
「生き物が死ななければいけない理由①食料や生活空間などの不足②多様性のため」とあるように、少子化圧力が高まり、人口減少が加速していくからです。
「死に絶える」というよりは、「子どもが生まれなくなる」のが正解かもしれません。
人類滅亡を回避するためにも、「死」の概念を再度問い直してみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
