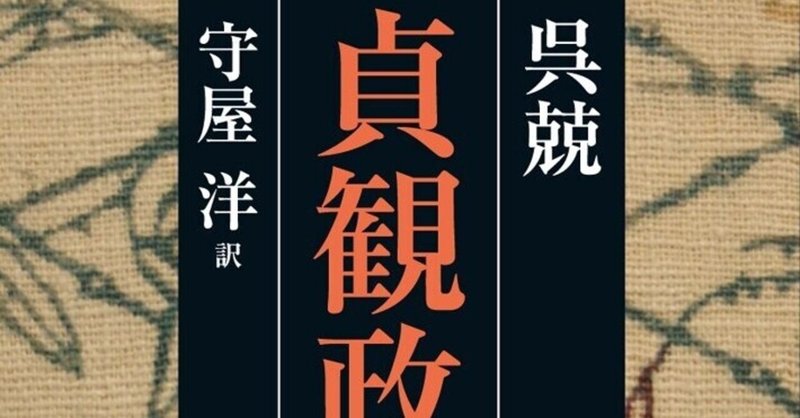
Etude (14)「人間はまだまだ科学では解き明かされない未知なる存在」
[執筆日 : 令和3年3月22日]
昨日から今日にかけて、沢山の方からメールを頂戴しまして(多くは海外からのもので、英国在住の同僚のコロナ・ワクチンを打った話なども)、その返信と追加の発信で嬉しい悲鳴を挙げておりましたが、御紹介した内容は沢山あるのですが、今日は、その中で、絵画・音楽に関してのお話と、人間の行動に関しての興味深いお話を御紹介しながら、人間を考えたいと思います。
あ、その前に、若干言い訳めいた事を。今回、敢えて、七面倒な仕分け(徒然の送り先の配送先のトリアージュ)をしたかと申しますと、私は誤解を招く事を話すし、書く人間であるということがよく分かったということです。コロナ禍でもありますし、なかなか思い通りにはならない訳ですが、私のように、能天気に好きなこと、本を読んで、 読書感想文を書いて、またはゴルフの話を付け加えて、時には高尚に哲学はこうだ、絵画はこうだ、人生はこうだと書いたものを送ると、人によっては、いい気なもんだなとか、或いは、こっちはそんな暇はないよ、読みたくても読めない、書きたくても書けない人の身にもなってくれと思う人もいたであろうと想像した訳です。気の毒なことを「平気」でしたということなんでしょう。「残酷」なことをする人だと思った人もいたであろうと、そういう自己反省に立ってのことだとご理解くださいませ。
なお、私がこの人はいい人だなあ、この人好きだなあと思う人は、男女ともにですが、ある特徴があります。それは、いえ、眉が立派ということではありません。それは、その人から流れ出る香りが、香水の匂いや加齢臭ではありません、色がついていたり、ついていなかったりする香りを感じるのです。その香りが「微風」になって、身体の周りを漂うというか、吹いている、そんな印象を与えてくれる人が好きなんですねえ。大体そういう人は、経験的にですが、私にとっては善人のようです。お役人? 淀んでいますよね、多くの方は(笑い)。
で、先ずは、芸術に関してのお話を最初に。以下は、若干私が脚色した、海外から届いたメールです、念のため。
「私の主人は芸術家の父親を持つパリ生まれのフランス人で、彼の父親は、このところ書かれていらっしゃる芸術の世界をまさに地で生きたような人だったと思います。主人から聞いた話では、彼は、朝は生涯チャイコフスキーのバイオリン第一協奏曲を弾き、午後は絵筆を握る人でした。芸術家であった彼の人間性について語ることは、難しいと思います。と申しますのは、芸術家ですから、極普通の人にとっては当たり前の家族との楽しく、笑いに溢れるような会話のある暮らしや、子育てといった日常生活からは程遠い生活だったからです。ただ、世の中の動きについてのオピニオンは持っていた人だったと思います。画家でもありましたから、夜になると、ピカソやダリもよく家に遊びに来ていたようですし、藤田嗣治も何度か見かけたようです。もっとも、彼等はもう随分齢はとっていたようですが。ピカソにしてもダリにしてもその画筆の基本の能力は比類なく、それ故、ピカソは絵を切って動かすキュビスムができたのだとも言っておりました。
芸術家の息子である主人は、さほど楽器を弾く能力はなかったようですが、週一度の音楽鑑賞講座(子供向け、一般向けのオーケストラが弾く)に通わされ、クラッシク音楽をたたき込まれ、中学生になると夏は、まだ敵として認識されてはいなかった、偉大な 文化大国ドイツに音楽修行のために行かされたこともあったと聞きます。
日本人とフランス人とは宗教も違いますし、日仏の色々な違いの中で培われたものが芸術でもありますから、そうした違いは知識ではなく、一種の血のようなものです。神の脅威のようなものもあります。ですから、日本の芸術家がフランスに長く住んで、仮にフランス人になったとしても、芸術をフランス人のように理解すること、そして語ることは難しいのではないかと思います。」
どうでしょう、上手く着色できたかなと思いますが、画家というのは、私の岳父がそうでしたから、多少は行動様式は分かるのですが、基本的に孤独ですよね。孤独を楽しむくらいでないと、画家は続けられないでしょう。西洋画と日本画の違いはありますが 、画家は文字表現者である作家に比較して、長生きの傾向があり、特に日本画の画家( 女性は特別に)が長生きであることに、案外日本画の特異性のようなものがあるかもしれません(日本画といえば、オタワに叙勲もされた菊池大先生がおりましたが、お元気かどうか)。しかしながら、私にはその辺はわかりません。ただ、絵には、音楽性(時間の移り変わりですね)を感じられるという面はあると思います。
さて、もう一つは、ゴルフに嵌っている友人が書いてきた、行動経済学で謂われるプロスペクト理論についてです。「人は利益の増加より、(同じ量なら)損失を帳消しにすることの方により大きな価値を見出す性質を持っている」ということですが、この理論(理論と言えるがわかりませんが)を考える前に、昨日読み終えた「貞観政要」の話を。訳者の守屋洋さんが要約として、
◎安きに居りて危うきを思うこと、
◎率先垂範、わが身を正すこと、
◎部下の諫言に耳を傾けること、
◎自己コントロールに徹すること、
◎態度は謙虚に、発言は慎重にすること、
を呉兢は説いていると説明しております。
「貞観政要」は、起業家精神にも関連する、創業とそれを維持するための守成の行動の質の違いを説明しながら、明君と暗君の違い、諫言を如何に聞き、それをどう実行するか、人材の登用のあり方、良臣と忠臣の違い、等を為政者であった李世民と彼に対するご意見番的な補佐達とのやり取りを挙げて、如何にして、国を治めるかということを説く本であります。帝王学の走りの本ではありますが、マクロ的には国のトップのあり方、あるいは会社の社長さんの、そして、ミクロ的には、一個人としての社会生活のノウハ ウ的なものとして、或いは、趣味の世界、私的にはゴルフの遊び方にも運用のできる知恵の宝庫のような本であります。
人間は、エコノミック・アニマルでもあると言われますが、経済学の基本は、人は「 合理的」に行動する生き物であることが前提になっております。経済学が人間学であるとも言われ、人間の本性と人間が有するとされる合理性が経済活動でどう反映されているかを知るのが私が理解する行動経済学であります。需要と供給の価格決定メカニズムは、その人間の仮定的な合理的行動から導き出される理論で、一方で、限界効用逓減の法則は、人間の快楽は同じ快楽を受けていたら、快感度が下がることから導き出されている訳です。
問題は、この合理性というものです。合理化を辞書で見ると、「能率を上げるために無駄を省くこと」。或いは、「もっともらしく理由づけをすること」や「言い訳をして、行為を正当化すること」という意味があります。フランス語では合理化はrationalite、合理化するは rationaliserです。これは理性raisonによってなされることとの説明があり、では理性とはなにかというと、人の考える能力であり、人がそれによって、正しく判断し、行動に適用することを可能にするものと説明があります。論理的という言葉の類語でもありますが、目的から正しく判断することが合理的なことなのか(帰納的に)、それとも、そうではなくて、一歩一歩の正しい判断の積み重ねの結果を合理的なものとするのか、悩ましいところがありますが、経済的には、利益を最大化することが究極の目的ですから、得られるものと損失するものとの比較で、行動は決まります。
シャネルのバックを買う場合、満足度を求める訳ですが、その満足度に見合った支出であるかどうかは、持っているお金次第でもありますが、今持っているバックでは得られない満足度(見栄も含めて)が、それに支出して家計が苦しくなる度合い(損失度)よりも大きければ買うのでしょう。つまり、買うという行為(支出行為)は、結果として得られるものへの期待値が高くないと成り立たない行為ということですが、日常的に経験するのは、そんなことは実はそんなに多くはないということです。大体、失望し、損したなあと思うことが多い訳です、それに、幾ら良いものでも、限界効用逓減の法則で、飽きます。そして、そうした損失を取り返そうとして、今度はエルメスのバックを買うということです。ですから、人間の合理性というものには、長期的なことにはあまり加味されないということが分かります。そして、多くの人の行動は合理性に基づいているとは必ずしも言えないということです。
で、ゴルフですが、前のホールでダボを叩いた人(経済学的に赤字状態)は、次のホ ールには挽回しようとする訳です、本当に上手な人は、無理に総てを取り戻そうとはしないようですが、これがヘボは、一挙に返そうとします。(パー4のミドルホールで)一打目でミスし、二打目もミスし、三打目でグリーンに乗せることの成功の確率が低い場合、上手な人は、無理してグリーンに乗せるのではなくて、4打目が打ちやすい、寄せやすい場所にレイアウトしますが、ヘボなゴルファーは、3打目の成功の確率よりも 3打目でオンした方が、結果としてパー乃至は、ボギーを取れると期待し、果敢に攻め るゴルフをして、結果的には、パーもボギーも、そしてダボすら得られなくなるのです 。でも、ヘボは3打目の結果だけを期待し、攻めのゴルフをしている、そんな気がします。博打的なゴルフとも言えますが。
合理的というのは、損失を計算した上での守りのゴルフということなんだと私は思います。得られることへの期待値が高いのは良しとしても、合理的というのは、こうした損失をきちんと行動の前に計算できる能力であると思いますが、ヘボゴルファーは、ある意味で、経済学でいう合理性からもっとも程遠い存在ということです。なぜ、そうしたことが出来るかといえば、失敗しても恥はかいても、死ぬことはないから。そこが人生とは違います。
結論として何が言えるかと言いますと、理論というのは総ての人に当てはまるものではないということです。経済学は純粋な科学ではないのです、人間は科学的には解明尽くされてはいないのです。況んやゴルフをやです。それであるからこそ、私たちは、こうした「貞観政要」を読んで、人間の深さ、知恵の深さを知る必要性がある、と私は思っております。その詳細はまた後日ということで。(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
