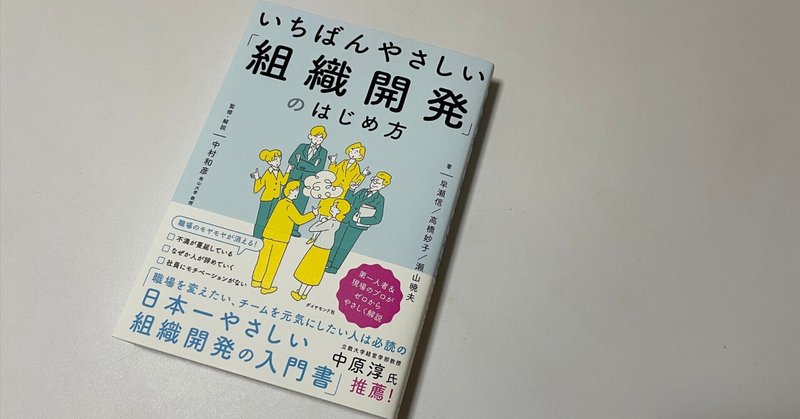
【読書メモ】『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(早瀬信・高橋妙子・瀬山暁夫著、中村和彦監修・解説)
石山ゼミ関連でご一緒する早瀬信さんからご恵投いただき、さっそく読ませていただきました。早瀬さん、ありがとうございました!本書は、そのタイトルにたがうことなく、組織開発の入門書として読みやすく、また味わい深い書籍でした。
二つの組織開発
組織開発に詳しい方ですと、二つの組織開発と聞くと「対話型と診断型の違いでしょ」となるかもしれませんが、本書では違う観点から類別をしています。具体的には、構造化された組織開発と構造化されていない組織開発、というように構造化をキーワードにして以下のように分けています。
(1)構造化された組織開発
日常業務とは異なる特別に設けられた場で対話や研修を行う取り組み
(2)構造化されていない組織開発
組織における日常業務を通じてチームや組織のメンバーが現状に気づいてよりよくするために行う自発的な取り組み
7-8頁の監修者の解説を基にまとめてみましたのですが、これは、さらっと読み飛ばせない痛い問いを実践者である私たちに投げかけています。つまり、「組織開発の施策を実行します!」と経営や人事部門が言うとき、たとえばエンゲージメント・サーベイを基に対話するという場を設えることは想定されると思いますが、その後の日常の行動までをスコープに入れられているか、と問われているわけです。
現場でありがちなケースは、ワークショップでは対話が盛り上がってアクションプランまで「なんとなく」できあがったのに、その後の現場での実行にまでは落ちないという場面です。これは(1)はできているのだけれども、(2)に落ちていないという典型例と言えます。
組織はワンアクション(1回の対話の場やワークショップ)で変わるわけではありません。関わりを通しての相互理解やつながり、関係形成の蓄積によって漸進的に変化していき、人々の意識や行動が変わっていく。
この部分はよくよく味わいたい箇所ですね。
二つのプロセス
本書では、組織開発の七つのケースが紹介されています。小規模な企業から大企業、町や大学でのゼミといったようにバリエーションが多いので参考になる部分が見つかるのではないでしょうか。
ケースを読む際にぜひ意識されると良いのが、二つのプロセスです。よく組織開発においては、起きている問題事象の対象範囲について、目に見える問題事象であるコンテントと、目に見えない問題事象であるプロセスという二つがあるという解説がされます。このプロセスには二つの種類がある、と著者たちはさらに分けていて、これがわかりやすいと感じました。氷山モデルを用いて、55頁で以下のように整理されています。
(1)タスク・プロセス:目に見えにくい問題事象
・意思決定のされ方
・目標の共有
・役割分担
・手順や仕事の段取り
(2)メンテナンス・プロセス:見えない問題事象
・職場の雰囲気や組織風土
・メンバーのモチベーション
・メンバー同士の関係性
肌感になりますが、組織における問題を見ようとする場合、対話の話題になりやすいのは、
コンテント >>> タスク・プロセス >>>>>>>>>>> メンテナンス・プロセス
という順番ではないでしょうか。目に見えるコンテントにどうしても意識は向いてしまいますし、プロセスの中でもタスク・プロセスに注意が向きがちです。組織開発においては、タスク・プロセスとメンテナンス・プロセスの両方を意識すべし、という著者たちの主張はぜひぜひ意識したいものです。
組織開発を難しく考えすぎない
ここまで読んで興味を持たれた方は、ぜひ本書の七つのケースを読んでみてください!ケースを基に自分自身の組織に置き換えていろいろと考えを深められると思います。
読んでみると、取り組みの最初から「組織開発の施策を今から始めます!」というように、組織開発のプロセスを意識して着手したケースは決して多くない、というかマイノリティであるということに気づくと思います。組織開発に興味関心がある方は、本書を読んでみて、その概要とポイントを理解してみると良いかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
