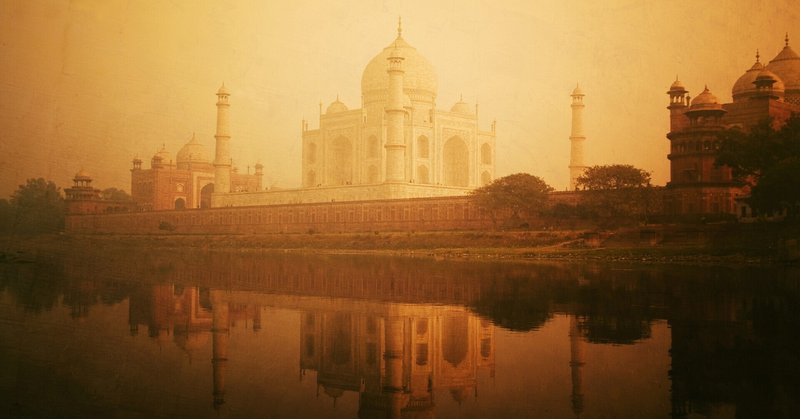
【読書メモ】『彼岸過迄』試論:『夏目漱石の時間の創出』(野網摩利子著)第7-8章
『門』を執筆後、修善寺の大患と呼ばれる危篤状態から復帰して、漱石は後期三部作への執筆へと進みます。その第一作が『彼岸過迄』です。個人的に、後期三部作で最もピンと来ないのは本作品なのですが、著者の解説を読んでいて感心することが多くありました。
まず本書の主題は死です。特に「死んでほしくなかった者について、人はどのようにして語りはじめることができるのかを問うている」(208頁)と著者は述べています。
では、この「死んでほしくなかった者」とは誰なのか。漱石が『彼岸過迄』執筆前年に急死した五女・ひな子であろうと述べられています。生まれて一年で急死してしまった娘に対する想いをきっかけに本作品は書かれました。それは、現在では季節を表す言葉とも読み取れる「彼岸」という仏教用語にも現れています。
『彼岸過迄』は五つの篇から成っていて、主な語り手も異なるという異色の小説です。なんだかとっつきにくいと感じるのは語り手が複数いることによる微細なズレがあるからなのでしょう。
複数の語り手がいるということは複数の人物の内面が語られるということを意味します。これは「ジェームズの多元宇宙観の小説的実現」(231頁)と形容されていて、本作品においてもジェイムズのプラグマティズムからの影響が見て取れるようです。
複数の語り手の記憶が紡ぎ合うことで一つの物語を形成するというプロットは、漱石による新しい手法であると著者はしています。
この小説の形状は、人間の頭のなかで持続する内容を挑発する。一度記された言葉が登場人物や読者の頭のなかでさらなる成長を遂げる。これは生成しつづける小説という漱石の挑戦に他ならない。人間の思考が言葉を受けとったのち、さらなる屈折を重ね、発展してゆくその自然なありようが、小説によってけしかけられている。(248頁)
これまで読んだ時にはとっ散らかった印象があったのですが、複数の語りとは奥行きであり、読者側でそれを拡げていくことができると捉え直すと、違った読み方ができるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
