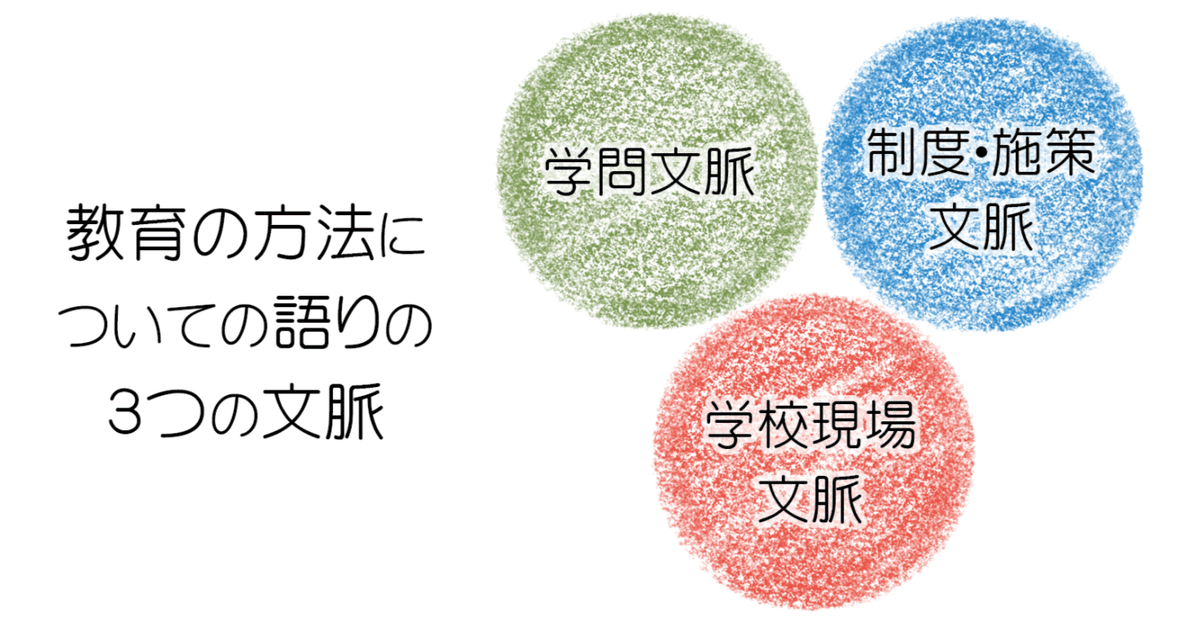
教育の方法についての語りの3つの文脈
教育の方法について語ろうとするとき、3つの文脈ないし世界があるように思う。学問文脈、制度・施策文脈、学校現場文脈だ。
それぞれの文脈での典型的なコミュニケーションを挙げると、
学問文脈:学術論文や専門書
制度・施策文脈:学習指導要領の解説本や教育政策(国内外問わず)の紹介
学校現場文脈:授業の進め方や教材を示すノウハウ本や実践の記録
といったところになる。
それぞれの文脈での語りの論理や重点価値は違う。
ざっと以下のように示せるだろう。
学問文脈:学問的手続きにのっとりつつ、いかに新たな知見を(大胆ないし堅実に)提起できているか
制度・施策文脈:制度や施策の方向性に沿い、制度や施策全体との整合性を保ちながら、いかに正確に、誤解のないよう伝えられているか
学校現場文脈:実際に教育活動を行ううえでどれだけ役立つか、現場のリアリティや教師の実感に迫れているか
これらの文脈の間に優劣はない。学問文脈のものだから「上」だとか「下」だとかがあるわけではない。
ただし、それぞれの文脈のなかで、質がよいものとそうでないものとはある。学問文脈において、明晰で問題提起性にも富んだ論文がある一方、論理が粗雑だったり新規性が不明だったりする論文があるといったようにだ。
(なお、制度・施策文脈に関しては、日本の場合、判で押したようなものはたくさんあるものの、良質のものは不足しているように思う。)
それぞれの文脈の主たる語り手としては、学問文脈は大学の研究者、制度・施策文脈は指導主事や行政方面の人、学校現場文脈は学校の教師が考えられる。
けれども、これは固定的なものではない。
大学の研究者が授業づくりへの役立ちを最優先にして学校現場文脈で語ることもあるし、学校の教師がそうした役立ちから距離を置いて研究を行いその成果を学問文脈で語ることもある。
また、一対一対応の関係ではなく、複数の文脈をにらんだ語りもあり得る。
新しい施策の方向に沿ってそれを分かりやすく伝えながら、教師にとって「授業をするのに役立つなあ」と思える解説や具体例の紹介をする(制度・施策文脈+学校現場文脈)といったものだ。
さて、ここまでが前置き。
ここから先考えたこと、2つ。
1つは、教育の方法について語るときに、こうした文脈の種類を意識することの大切さ。
例えば、大学の研究者が校内研修などに呼ばれて授業やカリキュラムのことについて話す際、学校側からは学校現場文脈が期待されているにもかかわらず、無自覚にもっぱら学問文脈でしゃべる(若い研究者にありがち)と、きっと「また大学の先生が空理空論を言って…」みたいに受け止められてしまう。もちろん、これは、単純に「学校現場文脈に合わせるべし」という話ではなく(それだと、学問文脈で鍛えられてきた大学の研究者をわざわざ呼ぶ意味って?となりかねない)、何が期待されているかを意識しながら、そこであえて学問文脈を入れ込んだりとか、戦略的になる必要があるということ。
あるいは、教職大学院にやってきた現職院生が課題研究でぶち当たる困難も、これに関係する。授業実践について、学校現場文脈や制度・施策文脈で語ることに慣れすぎてしまっていて、学問文脈での語りの意義やそもそもそうした異なる文脈での語りがありうるということ自体がつかめず、「自分はいったいここに何をしにきたのだろう」と路頭に迷ってしまうといった事態だ。これもまた、別に、従来行われてきたような学問文脈での語りを絶対視する必要はなく、新たな研究像を(院生と大学教員とが協力して)つくっていけばよいのだが、少なくとも、こうした文脈の違いについては、意識しておくほうが研究を進めていくうえでスムーズだろうし精神衛生上もよい。
もう1つは、教育方法分野でのいわゆる教職課程テキストの問題。
教育職員免許法施行規則上の「教育の方法及び技術」や「教育課程の意義及び編成の方法」に対応して作成されるテキストは、種類の点でも発行部数の点でも膨大なのだが、似かよった章構成や内容のものが多いし、率直に言ってそのうちのかなりのもの(すべてとは言わない)は、つまらない。もちろん私見だし、反論も歓迎なのだが、こうしたテキスト類が教職課程の教科書という用途を超えて読まれている(例えば、現場の教師や他分野の研究者などによって)様子があまり見受けられないところからすると、この捉え方はそう的外れでもないだろうと思う。
なぜそうなってしまうのか。
まず考えられるのは、作り方の安易さだ。大勢の執筆者でつくれば作成期間を短縮できるし、それぞれが担当する授業で教科書指定すれば一定の販路も見込めるしということで、残念ながら、安易な作られ方をしてしまっているものが少なくないように思う。厳しい言い方をすれば、出版社・大学教員の共犯関係だ(「被害者」は、テキストを買わされる学生ということになる)。
そして次に考えられるのが、ここでようやく前置きの話に戻るのだが、文脈の問題だ。免許法施行規則に対応して作られているという出自からもうかがえるように、制度・施策文脈は必然的に強くなる。けれども同時に、大学で用いる以上、学問っぽさも出さないととなるし、教育の方法という実践的なものを扱う以上、役立ちも意識せざるを得ない。その結果、学問文脈、制度・施策文脈、学校現場文脈のどこからみても中途半端なものができてしまっているのではないか、と思う。
もちろん、例外はあって、私世代の教育方法学者ならば必ずくぐったであろう岩波テキストブックスの佐藤学『教育方法学』は、ほぼ学問文脈に振り切っており(免許法施行規則の枠組み自体特に意識していなかったのかも…)、それがかえって強みとなったのか、1996年の刊行にもかかわらず、いまだに生き長らえている。また、最近だと、稲垣忠らの『教育の方法と技術 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン』(北大路書房、2019年)のように、3つの文脈すべてに目を配りつつ、より広い層の読者への訴求力がありそうなものも出てくるようになっている。
おそらくこの問題は、テキストづくりというところに象徴的に現れてはいるが、根本的には、教育方法学者や教育工学者が、自身が仕事をするうえで欠かせないこの3つの文脈をどのように統合できるのかという問題でもあるのだろう。
さて、私のほうはというと。
私は、ある時期から、こうした教職課程テキストのあり方に関して上に述べたように疑問をもつようになって、この種のテキストの執筆に声をかけていただいても、ほぼすべて辞退させていただいてきた。別にこれは大御所気取りとかなのではなく、単純に、自分自身のスタンスが定まらないままこの風習の再生産の一端を担うのが、嫌だったからだ。
とはいえ、いつまでもそんなことは言っていられないだろうし、実際、「どういうものであれば教育の方法に関するテキストとして成立しうるか」の意識的な問い直しを経たうえで出されるテキストが必要にもなってきていると思う。
つい先日も、「先生の話をうかがって教育方法学に興味をもったのですが、何から読めばよいですか?」と相談に来た教職大学院の新入生がいて、それ自体は有難いしうれしいことなのだが、答えに悩んだ。個別のテーマなら本を紹介しやすいが、「教育方法」とか「教育方法学」とか言われると、かえって難しい。
まあ、「教育方法学者」を名乗る以上、自らの責任を果たすべく、少しずつ進んでいこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
