
「答えのあるお勉強」と「答えのない問い」という二分法がもつ危うさ
「未来の教室」事業を推進してきた経産省・浅野大介氏の著書を読んでみた。
浅野大介『教育DXで「未来の教室」をつくろう』学陽書房、2021年。
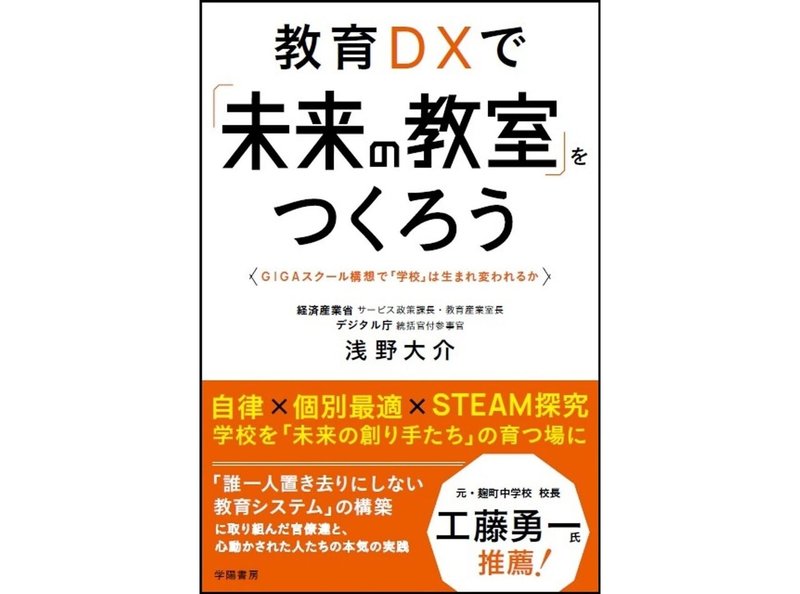
これまでの学校教育で弱かった部分・改めるべき部分への批判および対案として、教育関係者がきちんと受け止めるべき内容は含まれていると思う。
従来の学校における主体的に判断して行動する訓練の不足の話(第1章)や高校の専門学科の見直しと再評価(第4章対談)、不登校の子どもたちを今の学校の学習環境への違和感を表明している存在と捉え、さまざまな学び方に応じられるような仕組みをつくる話(第5章)、授業時数による学習管理の限界の指摘(第5章)などだ。
以前石川晋さんもブログに書いておられたが、浅野氏はこの数年間、たしかに精力的に動き回って、勉強もされてきたのだろう。
けれども、だからこそよけいに思うのは、浅野氏が、なぜこれほど(あえてはっきりと書くが)貧困な学習観しか持ち合わせていないのか、なぜそれを土台として「教育改革」を構想できてしまうのか、ということだ。
それは例えば、序章における次の文章にも示されている。
「答えのあるお勉強の指導」では、学校はサービス業としてAI型教材などを生み出す教育産業の進化に勝てません。この「お勉強ドメイン(領域)」では学校は教育産業と張り合わず、 教育産業が生み出すEdTechを使いこなす側に立つ(つまり「他人の褌で堂々と相撲をとる」)べきです。そして「面倒臭くて、手間のかかる、答えのない問い」に集中すべきです。
ここにあるのは、「答えのあるお勉強」と「答えのない問い」という二分法である。
そして浅野氏の主張は、前者(主に従来の教科教育が想定されている)を、ICTを活用したEdTechの教材に委ね、学際的な探究活動などを行う後者に教師は注力すべき、というものである。
はたして、学習というのは、「答えのあるお勉強」と「答えのない問い」にそうスッパリと分けられるものなのか。
むしろ、大人にとっては「答えのあるお勉強」に見えるものが、今まさにそれを学びつつある子どもにとっては、答えが分からない、ワクワクする探究になりうる。
また、実は大人にとっても、「答え」というのはそれほど自明ではなく、一つ分かればまた一つ分からなくなるものであり、そうやって絶えず探究心に駆られるところにこそ、学びの本質がある。
そのことを認識してきたからこそ、教師たちは、「すでに答えが出た、分かりきったもの」として知識を与えるのではない教え方に腐心してきたわけだし、また、表面的な理解に「ゆさぶり」をかけるような授業展開や教材を大事にしてきたのではないか。
ちょうどたまたま、前後して出たこちらの新書を、併せて読んでいた。
西林克彦『知ってるつもり ~「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方~』光文社、2021年

知識が少なく孤立していると「知ってるつもり」になりやすく、知識が孤立しないで豊富にあるようだと「知ってるつもり」になりにくい(第1章)
孤立した知識がわからない状態になりにくいということは、その知識を所持している人間がその知識に関わる問題を考えなくて済む確率が高いということです。それは他者から見れば、知識の状態は必ずしも満足できるものではないにもかかわらず、本人としては知っているという感覚を持っている可能性も高くなります(第3章)
西林氏は、知識が孤立した状態、「知ってるつもり」の状態を、「マズイ知識」と呼んでおり、そうした理解のあり方、また、それをもたらすような教科書やら教え方やらを、厳しく批判している。そして、理科の磁石から社会科の日本各地の気候までさまざまな例を挙げながら、表層的な理解の仕方の奥に、どのような深い理解の仕方がありうるかというのを、具体的に示している。
これに照らし合わせるならば、教科学習を安易に「答えのあるお勉強」と捉えて学習アプリで事足れりとする浅野氏の発想は、「マズイ知識」をもった「知ってるつもり」の人々をただ量産していくだけのものになりかねない。
西林氏が示す知見は、学習論として特に新奇なものではないし(例の出し方や説明の仕方は西林氏の面目躍如だが)、もう20〜30年も前から繰り返し述べられてきている。実際、基本的には同系統の主張をしている西林氏の『間違いだらけの学習論 ~なぜ勉強が身につかないか~』は1994年の刊行だ。浅野氏の学習観・知識観は、それ以前のもののままストップしているようだ。
一応述べておくと、私は、教育現場でのICT機器の活用に全面的に反対する立場ではない。学級での連絡事・情報の共有などこれを使って効率化できる部分はあるだろうし、また、何度でも(再生速度の調整や一時停止も交えながら)視聴したり試行したりできるというデジタル教材の特性を知識や技能の習得に活かすこともできるだろう。
けれども、根本的なところで、教科学習を「答えのあるお勉強」として矮小化し、教師らの(子どもたちを「知ってるつもり」に終わらせないようにするための)専門性や努力をないがしろにするような浅野氏の発想には、危機感を覚える。
「未来の教室」実証事業として学校現場で取り組まれてきたもののなかには、興味深い出来事が生じているものがたしかにあるだろう。それを否定するつもりはない(むしろ私自身、良質の事例から学びたいし、見に行きたい)。けれども、そこには教師たちの上に述べたような専門性によってカバーされている部分が相当あるはずである。浅野氏は、そこには目が向かず、もっぱらそれを「答えのあるお勉強」領域でのEdTechの功績として捉えているようだ。そして、自身のプロジェクトの推進にとって都合が良い部分しか目に入っていないように思える。(本書の第3章には、小学校でのEdTech活用への「紙と鉛筆を使わないと字が書けなくなるのではないか」という懸念に関して、浅野氏が、「タッチペンを使ってタブレット上に文字を正しく書かないとQubenaが文字を読み取らず、不正解と判定されます。『だから、 子どもたちは読み取ってもらえるように文字をちゃんと書こうとします』とは先生のコメントです」と述べるくだりが登場する。この「先生」がどのような意図で述べたのかは分からないが、これをタブレット&タッチペンの有効性の証左として受け止めているらしい浅野氏に、私はゾッとする。自分が意図するようにタッチペンの軌跡が認識されず、タブレットを相手にイライラと無力感を募らせる子どもたちもまた存在することを、浅野氏は想像できないのだろうか。多少改善されてきたし、今後解消されていく可能性もあるとはいえ、現状では、手書きで文字を書く際の操作性に関しては、紙と鉛筆のほうがまだ圧倒的に上である)。
もう一点、「いや、通常の教科学習の内容も深いものになりうるというのは分かるけれど、それはまず基礎的な知識を身につけてから行えばいいんじゃないの?」といった疑問にも答えておこう。
こうした段階説が妥当ではないというのも、近年の研究で示されてきている。
「創造性」という、むしろ浅野氏らが注目しそうなトピックを中心に学習科学の研究を進めてきたキース・ソーヤーもまた、『クリエイティブ・クラスルーム』において、「最初に浅い知識を教えてから創造的な思考習慣を教えたのでは遅い」と述べ、「学習基準で求められている教科内容の知識を浅い知識としてではなく、創造的な知識として学」んでいく(p.65)ための方策を、同書で具体的に示している(なお、それは、即興を含む教師の専門性を重んじるものだ)。
なぜこんな自らの素朴な学習観を見直すことがないまま「教育DX」やら「未来の教室」やらを進められてしまうのだろう。
そこが最大の疑問だし、教育学者としての自らの責任を痛感する部分でもある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
