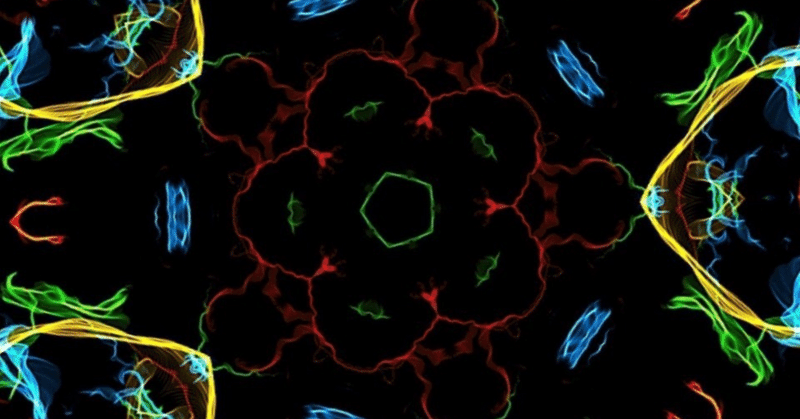
「アクティブリスニング」をかみしめる
赤羽雄二さん『自己満足でない徹底的に聞く技術』で書かれている
アクティブリスニングを実践中の畑中です。
日曜日の朝、目を覚ましたら、雨音が聞こえました。
その雨音を聞いて、前日の夜、子どもたちから「朝6時に起こしてね。朝一で、公園にエビ取りにいくから」と頼まれていたことを思い出し、「雨じゃ行けないから、がっかりするだろうなー」と想像しました。
こうやって、自然と耳に入ってくる音からも、色々な情報を得て、思考し、状況判断をしていますよね。
こんな風に、「聞こえる」ことに、アンテナが立っている今日このごろ。
というのも、今月、仕事で「耳の聞こえにくい方」6名を対象に、対面参加web参加のハイブリット型でzoom研修を行ったからです。
研修参加者は、まったく音が聞こえない方、難聴で聞こえにくいけど聞こえはする方、手話で会話する方、言葉を発することができる方、チャットを使った方が良い方、UDトーク(発話内容を文字化できるアプリ)で連携した字幕を読む方など、「耳の聞こえにくい方」と一口にいっても、コミュニケーションの取り方は、さまざま。その方たちを対象の研修を実施するために、研修コンテンツや実施方法を検討し、聴覚障がい者のことを学び、研修でファシリテーションをする中で「聞こえない」世界で過ごす方たちの経験シェアやディスカッションからたくさんの気づきがありました。
耳から入る情報に意識を向けると、想像以上にいろいろな音や声を聞いていることに気づきます。「聞こえるのに、聞いてない」「聞こえるのに、聞けない」。そんなもったいないことをしないようにと、気持ちを新たにしています。
さて今回は、カレイドソリューション株式会社の「アクティリスニングをかみしめる」というセミナーを受講しての学びを書き留めておきます。
傾聴とアクティブリスニングの始まり
国立国会図書館サーチで「傾聴」で検索すると、
1905年(明治38年)『催眠術活法:実験立案』(鈴木丈次郎 著)
1906年(明治39年)『応対談話法』(蘆川忠雄 著)
がヒットして、すでに明治時代に「傾聴本」が存在しています。
アクティブリスニングは、
1957年(昭和32年)アメリカの臨床心理士カール・ロジャースが提唱したのが始まりと言われていて、1960年になると、傾聴とアクティブリスニングが、混同されるようになってきました。
アクティブリスニングをどう訳すか?
「積極的傾聴」と訳されることが多いが、それは正しいのか?
例えば、
・アクティブラーニング って、積極的ラーニング?
・アクティブシニア って、積極的シニア?
・アクティビティ って、積極?
・ボタンがアクティブ ってボタンが積極的?
アクティブの本来の意味である「活動を伴う」が転じて、「積極的」と訳されることが多いです。
英語圏では、
・目的的に(listening on purpose)
・全力で(fully engaged)
・反射的に(reflective)
と説明されて、「積極的」という表現とはズレがあります。
カレイドソリューション株式会社では、アクティブリスニング≠積極的傾聴と考えているそうです。
「聞く」と「聞こえる」の違い
・聞く(他動詞・動作動詞)
→「~を聞く」という、「hear」と意味が一致しない
・聞こえる(自動詞・状態動詞)
→「~を聞こえる」とはいわない、「hear」と意味が一致
たとえば、聴力検査では、「聞こえますか」といわれるが、「聞きますか」とは言われません。つまり、耳の受信の機能は「聞こえる」という表現に含まれます。
耳は、受信器で、受け取る機能しかありません。
厳密には、耳は動作しませんが、動作動詞の「働く」つまり能動的動詞という意味が含まれます。「聞く/聴く」は耳が「働く」状態であると表現した言葉です。
二音節動詞の二文字目が「く」の場合、「働く」の意味を持つという説がある。
これを踏まえると、「聴く」は能動、「聞く」は受動と言われますが、「聞く」も能動的な行動と言えます。
能動と受動
能動と呼べない状態のことを受動と呼ぶ
「~する」「~される」だけが、対立概念ではなく、「~する」「~しない」という関係もあります。
たとえば、「聞こえる?」「聞いている?」という表現の違いがあるように、「聞く」には、耳が受信器として機能している「聞こえる」だけではなく、「わかっている?」「理解している?」といったニュアンスが含まれます。
「聴く」は「聞く」に加え、相手の言いたいことを意図をもって汲み取る行為で、「相手の真意・本音はこうではないか」という洞察が含まれるため、こころの姿勢と言われたりします。
まとめると、
・「聞こえる」→耳に音が入っていること(感覚器の受信)
・「聞く」→聞こえたままに理解する意図を持った行為
・「聴く」→相手の言いたいことを意図を持って汲み取る行為
リスニングとは
リッスンの和訳は、「きく」ですが、「聞く」「聴く」「訊く」どの表現が適切なのか。
・「聞く」 ”耳”が含まれる→耳の機能
・「聴く」 ”耳”が含まれる→耳の機能
・「訊く」 ”言”が含まれる→口の機能
リッスンは、「聞く+聴く」の意味があると考えるとよさそうです。
アクティブリスニングとは
アクティブは、活動を伴うこと
リスニングは、聞く+聴く
正しく聞く力があることを前提に、
意図的に聞き・聴くことをあいづち・反応・質問などの「活動/行為」と用いて、実現するものをアクティブリスニングと呼び、傾聴(聞く+聴くで質問は含まない)とは、範囲が異なります。
今回はセミナーで、このようにアクティブリスニングについて、結論付けがされていました。セミナーを受講して、「傾聴」・「アクティブリスニング」のはじまりについて学べ、「聞く・聴く・訊く」について、整理することができました。
ただ、赤羽雄二さんの『自己満足でない徹底的に聞く技術』では、「聞く」技術に加え、的確な質問や問題の深堀りをして、問題把握・解決までできるのが「アクティブリスニング」と書かれています。「アクティブリスニング」を広げるために、このブログを書いていますので、そもそも「アクティブリスニングとは?」ということを考える、良い機会になりました。
苦しくつらい子育てから抜け出し、家庭を安全基地にしたい方へ、情報を更新しています。
よろしければ、フォローしていただけると嬉しいです。他の投稿も参考にしてみてください。
■赤羽雄二さんのアクティブリスニング関連情報はこちら。
■アクティブリスニングの仲間とつながれるLINEオープンチャットはこちら。
■↓↓↓Twitterのフォローもよろしくお願いします↓↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
