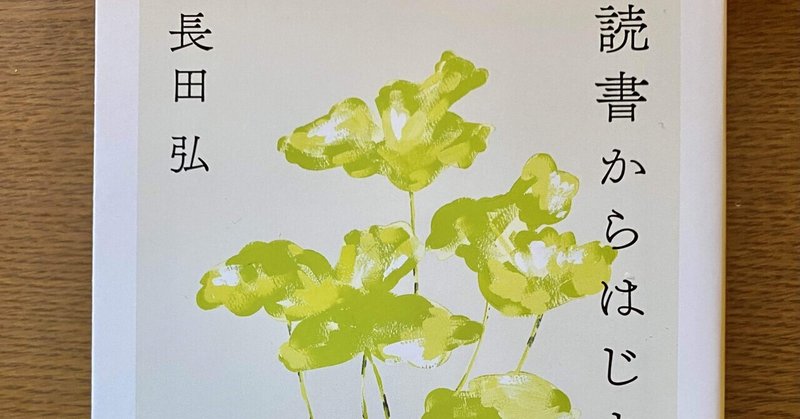
通学路が、憶えている
元旦。2024年。実感もなきままに、新しい年が始まった。
例年、年末年始は変なスイッチが入ってしまって予定を詰め込みすぎているので、今年は腰を据えてゆっくりしようということで、「予定なし」という一番難しい予定を入れることに成功した。
そしていざ、1月1日に待ちに待った「予定なし」の実行が始まるのだが、1月1日なりに結果を出さねばという(本当によく分からない)小さなプレッシャーもあり、なんかしよう、ということになり、とりあえず年末に買い込んだ本を何冊か、手に取った。(本を読んでおけば、とりあえずいい時間になる、という安易な発想と本への過信たるや。)
長田弘さんの「読書からはじまる」だ。
代表作の詩集である「世界はうつくしいと」、で言葉の持つ繊細さ、力強さに心打たれ、長田さんの考える読書、本を読むということへの想いを聴きたくなったのだ。
そこで、読書のための椅子、という章で、こんな記述があった。
世の中を変えてきたのは、日々の時間や空間を自由にするための、さまざまなハードウェアの充実でした。そう考えれば、今、読書の魅力そのものをも削いでしまっているのは、読書をめぐるハードウェアをもっと魅力的にしようとする気もちのなさだと、そう思うのです。
だからこそ大事なのは、その本をどんな椅子で読むか、ということです。
本はソフトウェアである。そして、いつもソフトばっかりで、ハードのことは全然考えてなかったな。。と思ってふと自分の座っている椅子に意識を向けると、それは中高の受験勉強を支えに支え、肘掛けが片方取れてクッションもボロボロの、見るに堪えない椅子だった。
おれは何年前のハードウェアを使っているんだ、、と悲しくなって、本を閉じ、であるならば通学路を歩いて小学校まで行こう、それから本の続きを家でこたつか風呂で読もう、と謎の帰結を迎えた。
とまあ、前置きがずいぶん長くなったが、とにもかくにも荷物も少なく、家を出て、通学路を忠実に歩いた。途中で通学班の集まる小さな公園があり、そこのベンチで物思いにふけりたかったが、新年を親子でキャッチボールして過ごす素敵なファミリーズ(複数いた)の眩しさに目を開けられず下を向いてそそくさと通り過ぎた。
十数年ぶりの通学路。気づきはたくさんあった。
・とにかく新しい見知らぬ家がたくさん増えたこと
・壁が低すぎること
・家から学校が思ってたより近いこと(13:42に家を出て13:56には着いた)
・畑や山や林など自然が豊かなこと
・学校は遊具などマイナーチェンジはあれど大きく変わっていないこと
・貯水池でT君がいじめられていたのを思い出したこと
・グラウンドは相変わらず木でできた不安定なベンチが健在だったこと
etc
通学路は、表情こそ変われど、しっかり記憶が刻まれていた。そして、今もなお生き続けていた。
自分が忘れていたとしても、通学路はずっと、憶えていてくれていて、自分さえその気になって足を運べば、すぐに当時が蘇る。
別に小学生に戻りたいとは露も思わないけれど、そんな小さな頃を思い出すという行為は、一方向に強制的に流れていきそうな時間に対する、ささやかで健気な抵抗であるようにも感じる。
過去に向かって一度ベクトルを向けることで、その分強く今に矢印が向いていくような感覚。実際に通学路をたどって帰るとき、「いや、自分でかくなったな」と今の自分を少しばかり肯定できるような気がした。
実家に戻って、家族からどこへ行ってきたのと聞かれる。
恥ずかしくて、ちょっとそこのコンビニ。とだけ言って自分の部屋に戻る。
そこにあるのは、読書には向かないであろうハードウェアとしての椅子と机。
でも、少しばかり小学生のぼく、を取り戻した僕は、参考書を開くようにしてパソコンを開き、noteに文字を打ち込み始めた。
この机と椅子は、打ち込むためには、最高のハードウェアだ。
そして東京にもどったら、自分の読書をめぐるハードウェアを整えることを始めようと誓った、元旦の昼下がり。
*
1.「読書からはじまる」長田弘
本とその周辺の捉え方を再認識できる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
