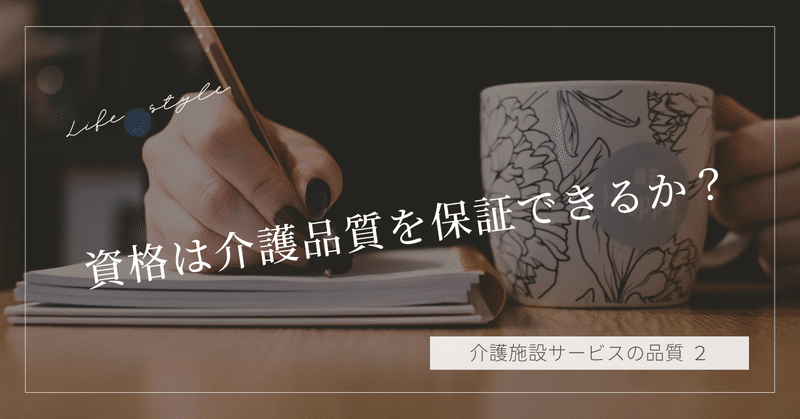
介護の資格は介護品質を保証できるか?-介護施設サービスの品質 2
念のため、最初に言っておきますが、私は資格は無駄だとか、不要だとか言っているのではありません。
1.資格よりも相互関係が大切
介護職員が自信をもつため、また社会的に認められるためには介護に係る有資格者となることが一つの条件かも知れません。たぶん、資格なしにはなかなか自信を持てないし、社会的評価も得られないかもしれません。
介護に係る基礎的な資格には介護職員初任者研修修了、介護福祉士実務者研修修了、そして介護福祉士がありますが、なんといっても国家資格である介護福祉士が最も社会的評価が高いと言えるでしょう。
しかし、入居者やその家族はこれらの資格についてどう思っているのでしょうか。また、介護職員に何を期待しているのでしょうか。
(1)介護職員に必要とされるのは人柄や態度
上野千鶴子(社会学者)さんは、「高齢社会をよくする女性の会」が2006年に要介護認定を受けている高齢者を対象に実施したアンケート調査報告書『高齢者と家族が介護職員に期待するもの』を紹介しております。
その質問項目の「介護職員に必要とされる人柄や態度」への回答では、要介護者の家族のベスト・スリーは「責任感がある」「対応がやさしい」「仕事に喜びを持っている」ですが、要介護高齢者、ご本人は「対応がやさしい」「話を聞いてくれる」「責任感がある」だといいます。
上野千鶴子(社会学者)さんの解説によると、要介護者ご本人は相互関係に関わる要因を重視し、家族はよりプロとしての側面を期待しているとのことです。
さらに、要介護者の年齢が上がるほど、また、在宅より施設の入居者の方が「対応がやさしい」「話を聞いてくれる」という相互関係を重視する傾向があるといいます。
(2)資格への思い―要介護者と家族の違い
また、上野千鶴子さんは、介護職員の資格について次のように指摘しています。
『資格要件については要介護者は「人柄がよければ資格は不要」と考え、家族は「実務経験のある中高年有資格者」を求めている。』
『要介護高齢者本人は学歴も国家資格も期待していないが、それを要求しているのは家族の方である。』
家族は資格を求める傾向があるけれど、高齢者ご本人はそうではないらしいのです。
私もまったく同感です。私が要介護状態になり介護施設に入居したとしても、介護職員の資格は気にしません。
優しくしてくれるかどうか、訴えを聞いてくれるかどうか、話を聞いてくれるかどうか、人間として接してくれるかどうかに尽きるのではないでしょうか。
(3)資格と能力
さらに、資格と能力との関係についても上野千鶴子さんは次のように指摘しています。
「資格と能力とのあいだに何の相関関係もないことは、サービス利用の当事者が日々経験していることである。」
これも、まったく同感です。
本来、資格とは最低限の品質を保証しようとするものですが、介護が介護される者と介護する者との相互行為である限り「人柄・態度」は非常に重要なものになります。
しかし、この「人柄・態度」と、資格が保証しようとしている「技術・専門性」とでは全く異なるものです。資格では人柄や態度を測ることがでませんし、それを保証することも、できないのではないでしょうか。
(参照:上野千鶴子(2011)『ケアの社会学』太田出版P175)
2.資格ヒエラルキー
介護現場で実際に働いている方々も、資格と能力は何の関係もないということを薄々は感じているのではないでしょうか。
しかし、資格が職場内の立場を決定してしまうのが医療・介護の世界です。
国の公式見解はもちろん資格者優位です。
例えば、サービス提供体制強化加算などは、介護福祉士資格保有者の割合がポイントとなっています。ようするに介護福祉士が多ければサービスの品質が高いと認定されるのです。
また、給与規程上の資格手当も介護福祉士の方が実務者研修修了者よりも高く設定されている事業者がほとんどでしょう。
介護業界には国家資格である介護福祉士、社会福祉士を頂点とする資格ヒエラルキー(hierarchy:階級構造)が歴然とあるのです。この介護資格ヒエラルキーのさらに上に、医師を頂点とする医療資格ヒエラルキーが被さってきているのです。
医療と介護の連携が叫ばれていますが、医師を頂点とし、初任者研修修了者や無資格者を底辺とする医療・介護資格ヒエラルキーが歴然とあるのです。
3.介護の資格・教育ビジネス
とにかく、介護業界は資格好きです。介護業界では実に多くの資格、そして、教育研修が用意されています。
思いつくまま挙げてみますが・・・
介護職員初任者研修、介護福祉実務者研修、喀痰吸引等研修、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修、認知症チームケア推進研修、ユニットリーダー研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当研修、認定介護福祉士養成研修、重度訪問介護従事者研修、等々
まさしく、資格(研修修了を含む)のオンパレード(on parade:勢ぞろい)です。
屋上屋を重ねる[1]とはまさしくこのことではないでしょうか。
資格・研修の屋上屋を重ねながら介護教育ビジネスは拡大・成長してきています。介護の現場、介護労働者は介護教育産業の餌にされているのかもしれません。
また、介護業界では多くの資格を持っていることがその能力の証となると信じている人も多いようです。
実際、資格収集マニア(maniac:熱狂家)がいるくらいですから。もちろん、必要に迫られて資格を取得する人も、勉強したいと思って資格を取る人も多いとは思いますが。
資格と能力とのあいだに、あまり相関関係がみられないのが現実なのですが、実際の個々の職員の介護能力についての評価が適切にできない、評価するのが面倒なので、資格を手掛かりにしか能力を評価するしかないのが実情なのだと思います。
4.介護サービス品質等の評価をする権利は誰にある?
介護については、その介護職員の能力や介護サービスの品質を評価する権利を有しているのは当事者(お年寄り)ですが、当事者(入居者・利用者)の評価は無視され続けており、政府の定めた資格が、相互関係である介護の品質を保証するかのような幻想が広がっているのです。
「資格を否定しろ!」「資格は無駄だ!」と主張しているのではありません。
資格があるからといって介護能力を保証はしないし、介護の品質も保証したりはできないという当たり前のことを言っているのです。
そして、繰返しになりますが、個々の職員の介護能力、介護サービスの品質を評価する権利があるのは当事者(入居者・利用者)です。
よって、介護能力は当事者目線で評価するのがベストでが、上手く話せない、判断できない当事者や、介護関係の非対称性という関係要因から正直に話せない当事者も多いのが実情です。
ですから、利用者満足度調査も正確に当事者の判断を代表しているとは言えない事情があるのです。
それでもやはり、当事者が介護サービスの品質評価する権利があるということを決して忘れてはならないと思います。
[1] 屋上屋を重ねるとは、屋根の上に、もう一つ屋根を設けるように、無駄なものをこしらえること。「屋上屋を架す」とも言う。
以下のnoteも併せてご笑覧願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
