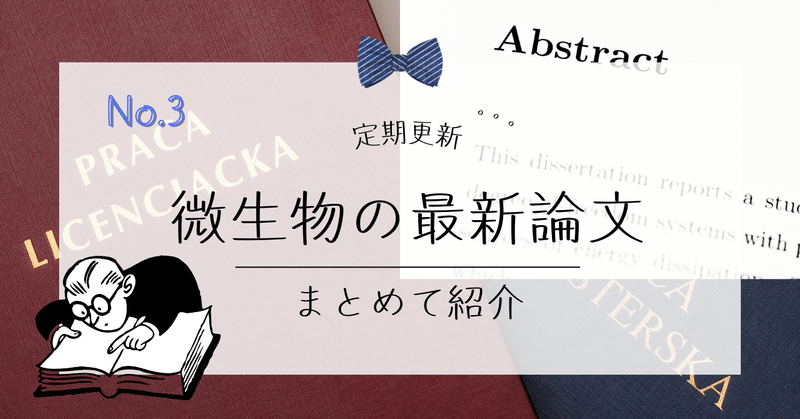
No.3 マイクロバイオーム研究の最新論文紹介(微生物、腸内細菌の最前線)
生物学に機械学習の手法ががしがし入ってきています。アナログ人間にはつらいところです。
ゲノム解析技術が手軽に使えるようになり、目に見えないマイクロバイオーム、腸内細菌に関する論文は、この10年あまりで指数関数的に増えています。
ここでは、PubMedで'gut microbiome' 'FMT'などのキーワードで集めた論文を定期的に紹介します。
新しい論文はまだ評価が定まっていないこともあり、鵜呑みにするのは危険な一面、研究の最前線に触れることができます。
要点だけでも、興味のある内容をぜひ読んでみてください!
ニューラル常微分方程式を通して、微生物組成から代謝プロファイルを予測する
[Regular Article]
(タイトル)Predicting metabolomic profiles from microbial composition through neural ordinary differential equations
(タイトル訳)ニューラル常微分方程式を通して、微生物組成から代謝プロファイルを予測する
(概要)代謝プロファイルを直接測定するのに比べ、微生物叢の組成から代謝を予測することは比較的安価に行える。筆者らは機械学習の技術であるニューラル常微分方程式(neural ODE)を利用し、微生物叢と代謝を予測するmNODEを開発した。腸微生物叢の場合は食事内容を予測に含めることができる。ただ、肺や土壌の微生物叢のほうが代謝プロファイルが正確であり、腸微生物叢の複雑さを物語っていると言える。
(著者)Tong Wangら
Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA
(雑誌名)Nature Machine Intelligence
(出版日時)2023 Mar 13
(コメント)ニューラル常微分方程式(neural ODE)は、2018年に発表された機械学習分野の技術で、今非常に注目を集めているそうです。
詳しく知りたい方はこちら。
https://neuralnet.hatenablog.jp/entry/2019/01/26/112337
青年期における腸内細菌と、乳児期からの習慣的かつ長期的な食物繊維摂取の関係
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316624000270?via%3Dihub
[Regular Article]
(タイトル)Association of long-term habitual dietary fiber intake since infancy with gut microbiota composition in young adulthood
(タイトル訳)青年期における腸内細菌と、乳児期からの習慣的かつ長期的な食物繊維摂取の関係
(概要)長期にわたる食物繊維摂取は、多様性指数の減少に関連があった。食物繊維摂取は、酪酸を生成するButyrivibrioと正の相関があったが、その他の酪酸菌であるFaecalibacteriumやSubdoligranulumなどとは負の相関だった。
(著者)Marja A. Heiskanenら
Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, University of Turku, Turku, Finland
(雑誌名)ELSEVIER
(出版日時)12 January 2024
(コメント)食物繊維摂取が必ずしも多様性向上に寄与しないこと、酪酸産生菌を一律に増加させないことなどの知見は、これまでの知見とは一見して矛盾するように思える。
思春期における加速度センサーを用いた睡眠の質と腸内細菌の関係:ブラジルコホート研究から
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945723016015?via%3Dihub
[Regular Article]
(タイトル)Accelerometer-based sleep metrics and gut microbiota during adolescence: Association findings from a Brazilian population-based Birth cohort
(タイトル訳)思春期における加速度センサーを用いた睡眠の質と腸内細菌の関係:ブラジルコホート研究から
(概要)ブラジルの子どもたち352名において、11歳時点での睡眠時間と睡眠効率と、12歳時点での便サンプルの解析を実施した。睡眠時間はα多様性と関連があり、睡眠時間や効率が上がるとBacteroidetesが減っていた。睡眠と便サンプル解析は1〜2年のブランクがあったが、その期間経過後も関連があった。睡眠が脳腸相関のサポートをしているといえる。
(著者)Marina Xavier Carpenaら
Postgraduate Program in Epidemiology, Federal University of Pelotas, RS, Brazil
(雑誌名)ELSEVIER
(出版日時)February 2024
(コメント)睡眠による多様性向上は、すでにいくつかの研究でも確認されている。
ヒト腸マイクロバイオームのゲノム工学
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1673852724000031?via%3Dihub
[Review Article]
(タイトル)Genome engineering of the human gut microbiome
(タイトル訳)ヒト腸マイクロバイオームのゲノム工学
(概要)ヒトの腸内共生細菌のゲノム工学の現在の進展と課題について、in vitroまたはin situで実施されるものを含めて概説している。特に、DNAの輸送や高スループット技術の進展と展望に焦点を当て、さらに、ゲノム工学手法がヒトの腸内微生物叢の理解を深め、微生物を改良して人間の健康を向上させる可能性についても検討している。
(著者)Linggang Zhengら
Dr Neher's Biophysics Laboratory for Innovative Drug Discovery/State Key laboratory of Quality Research in Chinese Medicine, Macau University of Science and Technology, Taipa, Macau 999078, China
(雑誌名)ELSEVIER
(出版日時)12 January 2024
植物由来の食事と腸内細菌:ボルティモア(アメリカ)の長期的な長寿研究での発見
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002916524000078?via%3Dihub
[Regular Article]
(タイトル)Plant-Based Diets and the Gut Microbiome: Findings from the Baltimore Longitudinal Study of Aging
(タイトル訳)植物由来の食事と腸内細菌:ボルティモア(アメリカ)の長期的な長寿研究での発見
(概要)植物由来の食事には、健康的なものとそうでないものがある。さまざまな植物由来の指標と成人の腸内微生物叢の多様性、構成、および微生物代謝物TMAOとの横断的な関連性を調査することがこの研究の目的。食物頻度調査票のデータを使用して健康的な植物由来の食事指数(hPDI)および健康でない植物由来の食事指数(uPDI)を導いた。705名の成人の便サンプルを解析したところ、hPDIはα多様性(特に均一性)と相関があった。
(著者)Xinyi Shen MHS
Department of Epidemiology, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, U.S.A.
(雑誌名)ELSEVIER
(出版日時)12 January 2024
(コメント)健康的な植物由来の食事指数(hPDI)および健康でない植物由来の食事指数(uPDI)について。
健康的な植物性食品とは、全粒穀物や野菜、果物、ナッツ、コーヒー/紅茶、植物油、豆類など。対して不健康とされる植物性食品には、精製穀物、フルーツジュース、ジャガイモ、加糖飲料、デザートなどが該当する。
↑健康的な植物性食品により糖尿病リスク低下―メタボロミクス解析|医師向け医療ニュースはケアネット https://www.carenet.com/news/general/hdn/54353
マルチオミックス解析により、鶏の脂質合成と筋肉発達を調節することが解明された
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579123009379?via%3Dihub
[Regular Article]
(タイトル)Multiomics analysis reveals that microbiota regulate fat and muscle synthesis in chickens
(タイトル訳)マルチオミックス解析により、鶏の脂質合成と筋肉発達を調節することが解明された
(概要)無菌鶏(GF)と特定病原体フリー鶏(SPF)において、トランスクリプトーム解析とメタボローム解析を実施。トランスクリプトーム解析では、SPFで筋肉形成に関する遺伝子発現が高く、GFでは低かった。逆に、GFでは脂質合成に関する遺伝子発現が高かった。メタボローム解析では、腸内微生物トップ10と脂質代謝・筋肉発達に正の相関があり、脂質合成には負の相関があった。これらから、鶏の腸マイクロバイオームは脂質合成を抑制し、筋肉の発達を促進している可能性がある。
(著者)Hai Chang Yinら
College of Life Science and Agriculture Forestry, Qiqihar University, Qiqihar 161006, China
(雑誌名)ELSEVIER
(出版日時)March 2024,
(コメント)家畜を太らせるために抗生物質が投与されることは近年の規制により減っているが、腸内細菌の調整によってこれの代替になる可能性がある。
アルツハイマー病と微生物:非コーディングRNAを通じて
[ReviewArticle]
(タイトル)Alzheimer’s disease and microorganisms: the non-coding RNAs crosstalk
(タイトル訳)アルツハイマー病と微生物:非コーディングRNAを通じて
(概要)アルツハイマー病は非コーディングRNA(ncRNAs)による調節の影響を受けている可能性が示されている一方、アルツハイマー病と腸内細菌などの微生物との関連も指摘されている。本レビューでは、腸内および鼻の微生物叢が神経変性疾患において果たす役割や、ncRNAsが免疫反応と炎症の調節において果たす役割を踏まえ、微生物叢コミュニティにおけるncRNAsの撹乱などにも触れている。
(著者)Hanieh Mohammadi-Pilehdarboniら
Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
(雑誌名)Frontiers in Cellular Neuroscience
(出版日時)05 January 2024
腸生態系と健康と疾患:マイクロバイオーム、腸粘膜バリア、サイトカイン環境
[Editorial Article]
(タイトル)Editorial: Impact of gut ecosystem in health and diseases: microbiome, mucosal barrier and cytokine milieu
(タイトル訳)腸生態系と健康と疾患:マイクロバイオーム、腸粘膜バリア、サイトカイン環境
(概要)新生児期からの外部環境暴露(エクスポゾーム(exposome))の中には、共生体や病原体としての微生物も含まれている。これらの要因と宿主側の免疫、サイトカインへの影響を理解するための短い総説。
(著者)Akihito Harusatoら
京都府立医科大学
(雑誌名)Frontiers in Microbiology
(出版日時)05 January 2024
マイクロバイオームの手綱を引く:進化する膠原病治療に関する包括的なレビュー
[Review Article]
(タイトル)Harnessing the Microbiome: A Comprehensive Review on Advancing Therapeutic Strategies for Rheumatic Diseases
(タイトル訳)マイクロバイオームの手綱を引く:進化する膠原病治療に関する包括的なレビュー
(概要)このレビュー記事は、口腔および腸のマイクロバイオームに関する現在の知識の包括的な概要と、これらが将来的に膠原病の管理に果たすかもしれない役割に焦点を当てている。また、バイオインフォマティックス解析やFMTなどの新しい治療戦略についても、検討している。
(著者)Priyadarshini Bhattacharjeeら
Acute Medicine, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust, Cambridge, GBR
2 School of Clinical Medicine, University of Cambridge, Cambridge, GBR
(雑誌名)Cureus
(出版日時)2023 Dec 22
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
