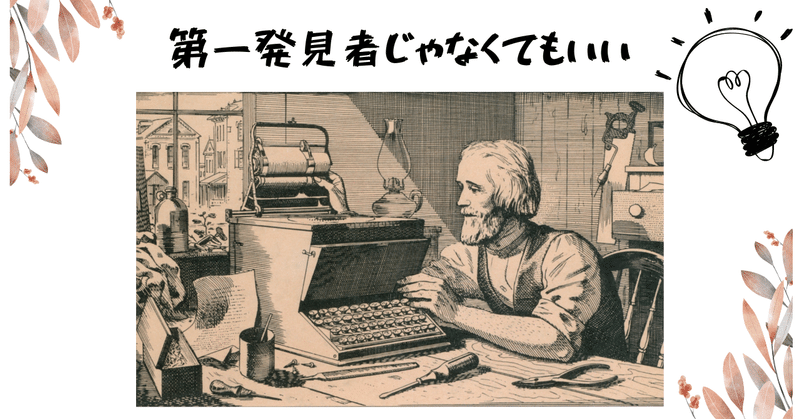
車輪を再発明しながら生きていきたい 〜研究の新規性について思うこと〜
あなたが三国志時代の武将だとして、3日で矢を10万本作らないといけないとする。できなければ斬首。
さて、どうしますか?
A:木を切り倒し、石を削って矢じりをつくり、一本ずつ紐でくくって気合いで頑張る。
B:市販の「矢キット」を使って、時短をはかる。
詳しくは私の大好きな映画『新解釈 三国志』を見ていただくとして、Aを選ぶ人は少ないんじゃないだろうか。
実際、Bの選択肢のほうが圧倒的に賢いですよね。
でも、Amazonで検索しなければ、矢キットの存在もわからずAしか選択肢がなくなってしまうでしょう。
車輪の再発明とは
"reinventing the wheel"(車輪の再発明)という英語のことわざがある。日本ではITエンジニアがよく使う用語らしいのだが、どういう意味なのだろう。
プログラミング業界は、オープンな世界だ。すでに膨大なコードが誰もがアクセスできる環境に存在し、優れた設計手法や、逆に失敗につながりそうな情報も整理されている。
こういった情報をしっかりリサーチせずにコードを書き始めてしまうと、車輪を再発明することになりかねないのだそうだ。
つまり無駄な時間や労力をかけて、既存のものと同じものを作るということだ。
IT業界以外でも、既存の使えるものがあるかリサーチすることはとても有意義だ。時間の節約にもなるし、自分で作るより質のいい方法に出会えたりする。
冒頭の「矢キット」はまさしくその例で、世の中にはお菓子づくり、工作、編み物、家庭菜園などありとあらゆるキットがあふれている。小屋キットなるものまである。
キット化されていなくとも、丁寧なインストラクションがYouTubeで公開されているなど、何かをイチから作る必要性は少なくなっている。
研究は新規性がないとダメ?
研究論文は、新規性がないと出版することができない。
つまり、発見したことが何かしらの形で第一発見者でないといけないのだ。(まあ、対象や母数をちょっと変えればアクセプトされるらしいけれども)
科学研究においても、車輪の再発明は避けるべき悪なのだろうか?
なにかの研究を行うとき、まずは先行文献のリサーチが欠かせない。
そこには偉大な先人たちの試行錯誤が詰まっている。彼らの興奮に満ちた発見の軌跡を論文で読むのは楽しい。
研究を行う際の手法として、標準化されたキットのようなものもたくさんある。ゲノム解析手法などはその好例だ。
もし私が奇跡的に今使われているのと同じゲノム解析手法を自分で思いついたとしても、誰も褒めてくれない。
それどころか、論文のアクセプトさえされない。
だってそれはすでにある技術で、私がそれを知らなかったのは単に私のリサーチ不足であり、リサーチさえしていれば労力は無駄に費やされなかったかもしれないからだ。
わくわくしなければ研究じゃない
研究は多くの場合、お金がかかる。
少なくとも仕事で研究をすれば、人件費がかかる。
そして人類は、ほかの動物とちがって知識を積み上げられる動物だ。自分の人生以上の経験値を、歴史という形で貯められる。
だから、研究は過去の業績に上積みされていかなくてはならない。
そうでないと前に進まないものごとはたくさんあるし、コストも無駄にかかるし、新しいことを発見するのが科学だからだ。たぶん。
でも、すでに誰かが発見しているからという理由で自分の発見を無価値化してしまうと、研究のワクワク感は消える。
私たち一般人が体感できることのかなりの部分が科学的に解明されている今、研究の新規性は極度の専門化の先にしかない。
それでわくわくできる人はいいだろう。
でも私は、少なくとも今の段階ではできない。
先行文献のリサーチも楽しいけれど、たとえすでに発見されていることであっても、自分の足でそこまでたどり着く経験もほしい。
人は、自分で経験するために生まれてくるのかもしれない
実を言うと、私のもともとの性質は超リサーチ型だ。
とりあえず何でもググって、最短で解決策にたどり着こうとする。
受験生のときも、とりあえず公式をたくさん覚えて、数学でさえほとんど暗記で乗り切った。
反対にうちの夫は、何でも自分で考えてやってみる。
どんなに遠回りでも、失敗しても、まずは自分の考えたやり方でやってみて、自分で考察する。
そばで見ていて、ときどきイライラする。
彼は大学受験でも、学校の授業をよく聞いて、過去問を何年分か解いただけで合格した。
解説をじっくり読んで、問題を因数分解して、根本から理解したのだ。
そんな夫は、3年前にITエンジニアになって、私と結婚して、近道することも覚えた。
もしかしたら、私は彼の大事な何かを奪ってしまったのではないだろうか。
「たとえ車輪の再発明であっても、今ここにいる自分が経験するということが大事なんじゃないか」
先日、夫とそんな話をした。
その考え方は、今の私にとてもしっくりきた。
車輪の再発明という言葉はあまりいい文脈では使われないけれど、車輪を再発明することで別の道が見えてくることもある。
冒頭のAとBの選択肢には、実はCがある。
C:夜に対岸の敵へむけて藁を積んだ船を出し、そこに火をつけて敵を慌てさせ、矢を自分の藁船に放ちまくらせて、瞬時に大量の矢をゲットする。
これは、Aの選択肢を試みたものの、無理だと悟って一生懸命考えたことで見えた選択肢だ。他にも、石よりももっと鋭利な金属製の矢じりを思いついたかもしれない。
もしBの矢キットの存在を知っていれば、こんなアイディアは浮かばなかっただろう。
車輪を再発明すると、既存の車輪を使うよりも効率は落ちるかもしれないけれど、経験の深みが増す。
新しいアイディアが生まれることもある。
ひょっとしたら、長期的に見れば効率が上がるかもしれない。
論文にはならなくても、リサーチばかりではなく自分の頭で発見することを楽しみながら、研究をしていきたい。
もう第一発見者にはなれなくても、何度でも何度でも、再発見したり再発明していいのだ。
ちなみに弊社の理念は「偉大な発明はリサーチの先にはない。発想の先にこそある」です。
うーん、深い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
