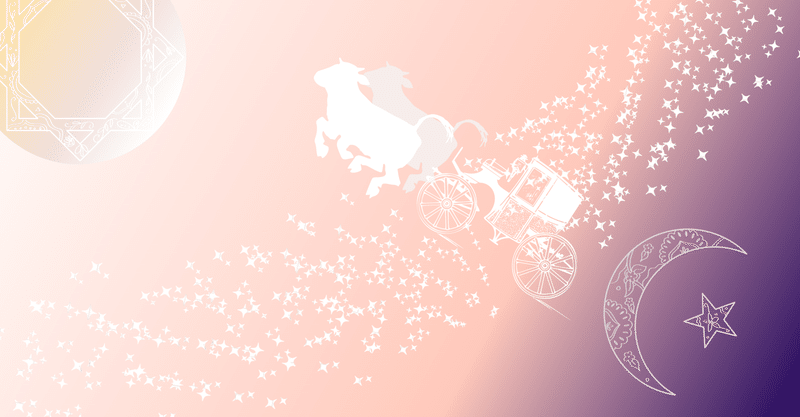
スウェーデン語・ドイツ語の Gift の続きで、バルト語の「結婚」にまつわる小咄を。
こんにちは。スイスラボの言語学者 Yamayoyam です。
前回の言語学小咄は、「結婚」に縁のある言葉についてでした。お楽しみいただけたでしょうか?今回はそのつながりで、バルト語を題材にした小咄をついに披露したいと思います。
バルト語には gift 関連の、クスリと笑えそうな単語が残念ながらみあたりません。なのでシンプルに「結婚する」の表現について書くことにします。バルト語では、男性と女性で「結婚する」に違う単語を使います。今でこそニュートラルに「結婚する」をよく使いますが、日本語でも一昔前までは違う単語を使っていましたっけ。「嫁入り」に「娶(めと)り」とかありました。今も頻度は下がったかもしれないけど、使います。ただ、「娶り」に至っては、聖書の訳文に使われているのを見るくらいかなぁ。
でも、バルト語では今も違う単語を使っています。リトアニア語から例を引きますが、男性だと vesti, 女性だと ištekėti です。Vesti は本来「導く、リードする」といった意味、ištekėti は「流れ出ている」という意味を持つ動詞です。ところで英語の wedding は、リトアニア語 vesti と同じ語根「*wedʰ-(導く)」(※1)から作られた単語なんですよ。印欧系諸部族が家父長的な社会を維持していたと聞けば、男性が結婚によって家を引き継いでいき、女性は嫁として他家へと「嫁いで出て行く」イメージがなんとな~くつながるかもしれません。
そんななんとな~くなイメージをもっと具体的に伝える、伝統的な結婚の習俗にまつわるフォークソングが、バルト語圏にあります。ラトビア語に伝わる次のフォークソングは、花嫁と太陽の神話的なメタファーを明示的に用いて、古い習俗を今に伝えます。
Gērbies, Saule, sudrabā / Nu nāk tavi vedējiņi
Udens zirgi, akmens vāģi, / Sidabriņa kamaniņas (LD 33784 ※2)
「銀の衣を着たサウレよ、今あなたの迎えが到着しました
水の馬と、石の馬車、銀のそりを携えて」※3
「サウレ」とは太陽の神で、同じ詩の別の連の描写によれば、朝は銀の衣を着て馬車に乗って森を駆け抜け、夕方になると赤い衣に着替えて舟に乗って海(あるいは Daugava 河)を渡るとされています。この短い引用では、婚礼の花嫁が太陽の神に喩えられています。つまり、花嫁は婿の遣いを待ち、婿の遣いが花嫁を(石の)馬車や(銀の)そりに載せて花婿のもとへ連れていく、という習慣があったことが伺えます。このような習わしのもとでは、女性は実家から出て行き(ištekėti)、婿側は花嫁を連れていく(vesti)、という言い回しがしっくりくるわけです。時は流れて今はもうそんなことはしていないでしょうけれど、このような古い習俗に根ざした言い回しが今も使われているのは興味深いものです。
バルト語では、「結婚している」と言うのにこれらの動詞から作った分詞を使います。みなさん、昔々英語の授業で分詞(=動詞から作られた形容詞)を習ったの、覚えてますか~?英語には現在分詞と過去分詞の2種類しかありませんが、バルト語には4種類あるんです。現在能動分詞、現在受動分詞、過去能動分詞、過去受動分詞。※4「結婚してます」のときは、「以前~したことのある…」という意味の過去能動分詞を使って、ちょうど英語の I am married、ドイツ語の ich bin verheiratet のような構文をとります。しかし!英語やドイツ語と違って、リトアニア語などのバルト語では、このような「述語」に使われる分詞も主語に性・数・格を一致させるんです。なので再びリトアニア語の例ですけれど、Aš esu vedęs (男性) / ištekėjusi (女性) のように、動詞語根だけでなく分詞の語尾まで男性と女性で違います。バルト語ではすべての分詞がこういうふうに性・数・格に合わせていつも格変化しています。
だから、例えば Migros でジビエ料理のパックを見つけて「鹿肉って食べたことありますか?」と誰かに(誰に!?)敢えてリトアニア語で聞くときも、どの相手に尋ねているのかちゃんと意識しないといけません。
男性単数 Ar tu esi valgęs elnio mėsą?
女性単数 Ar tu esi valgiusi elnio mėsą?
男性複数 or 男性+女性 Ar jūs esate valgę elnio mėsą?
女性のみの複数 Ar jūs esate valgiusios elnio mėsą?
場合によっては、「アタシ女なんだけど、今アナタ男性形で言ってなかった!?」なんて事故も起きかねません。
こんなふうに文法的な役割や機能を表すのにいちいち語形を変化させる言語を、言語学の用語で「屈折言語」と言います。※5 屈折というのは、こうやっていちいちいちいち語形が変化することを言います(決してメンドクサイと思っているのではナイ)。
リトアニア語含むバルト語の、この見事なまでの屈折っぷりは、屈折言語の中の屈折言語!といった風格を感じさせますが、学習者泣かせであります。
リトアニア語の語形変化についてもっと聞きたいっていうかた、いるのだろうか?みなさまのお声はよく分からないんですけど、リトアニア語の語形変化の悲喜コモゴモについてもっと書いていきたいと思います。
それではみなさん、お楽しみに!
Yamayoyam
※1 「語根」というのは、単語の基本的な意味を担っている部分のことを言います。例えばリトアニア語 vesti では、ves- が語根で「導く・結婚する」、-ti が vesti が不定詞であることを示す接辞だと分析されます。
※2 Barons, Krišjānis(編)Latvju dainas. (Riga: Latvijas Universitates Literaturas, folkloras un makslas instituts, reprinted in 2012)
※3 Jonval, Michel(著)Les chansons mythologiques lettones (Paris: Librairie. Picart, 1929) を参考に、筆者が日本語訳に挑みました。
※4 あれ?他にももっとなかったっけ?という方に。はい、その通り!必要分詞、副分詞、半分詞もあります!ここではもっとも典型的で基本的な4兄弟についてだけ挙げました。
※5 これは言語をその構造や性質によって分類したり、最適に分類する方法を考える「言語類型論」という分野での用語で、他にもいくつか「言語のタイプ」があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
