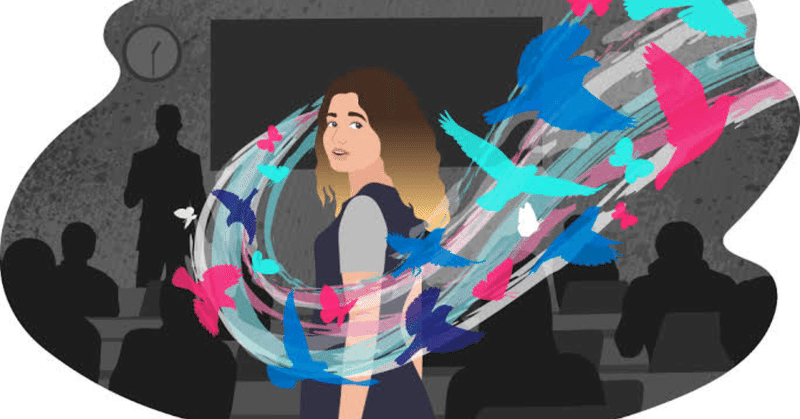
ADHDの診断を受けて良かったこと
私は2年前の3月にADHDの診断を受けました。
学生時代からその自覚は多少はありましたが、自己診断で済ませて、問題を先送りにしていました。
しかし、社会人になって「生きづらさ」が顕在化したため、自ら精神科に予約をとり、「ADHDなのかどうか」を確認しにいきました。
診断はもちろんADHDという結果でしたが、私の場合は、特に「脳の多動による不注意」があるため、周囲の理解やサポートが必要なレベルとのこと。
それから約2年が経とうとしていますが、今回のnoteでは、『ADHDという診断をもらって良かったこと』について振り返りたいと思います。
あくまでも私自身の経験によるものなので、必ずしも全員に当てはまるわけではないので、ご了承ください。
ADHDの診断を受けて良かったこと
①自分と向き合うきっかけになる

「ADHDかもしれない」と自覚する時点で、少なからず「生きづらさ」を感じ、悩みがある状態かと思います。
「診断を受けにいく」という行為は、目の前の「生きづらさ」とまっすぐ向き合うきっかけになります。
診断の材料として、幼少期から現在の自分の話を、お医者さんに伝える過程で、改めて、自己分析をすることができ、「ありのままの自分」を見つけていくことができます。
②むやみに自分を責めることが減った

「自分は意志が弱い」「なんでこんなミスが多いんだ」「どうやっても時間が守れない」
診断を受けるまでは、自分に対してこんな言葉をかけていて、知らぬ間に自分を責め続けていました。
診断を受けた後は、『脳の特性が関係しているんだ』と受け止めることができるようになり、責める癖が取れてきました。
③「人が完全でないこと」を受け入れられる

そもそも完全な人なんていないのですが、
そのことを身をもって学ぶことができます。
自分の中に「できないこと、苦手なこと」を認めているからこそ、「他人が不完全であること」にも寛容になれます。結果、人としての器が少し大きくなります。
ADHDの診断を受けて戸惑ったこと

良かったことと合わせて、診断をもらってから、少し戸惑ったことがあるのも事実。
社会の理解が進んでいないため、ADHDについて周囲への伝え方にはどうしても慎重になってしまいます。
私の場合、診断結果をもらった当日はショックが大きく、結果を受け止められずに、誰にも伝えられませんでした。
ただ、幸いだったことに、私は家族や職場の理解があったため、自らも、この診断結果を受け止めることがスムーズにいきました。
理解がある人が近くにいれば良いですが、いないと、この診断結果を1人で抱えてしまうケースもあります。
もし近くに理解者がいない場合は、他のADHD当事者とつながる等、誰かと「共有」することをお勧めします。
まとめ
最後に情報をまとめます。
●ADHDの診断を受けて良かったこと
①自分と向き合うきっかけになる
②むやみに自分を責めることが減った
③「人が完全でないこと」を受け入れられる
診断直後は戸惑いがありましたが、
2年経った今振り返ると、ネガティブなことは何もありませんでした。
これは私のケースなので、一概には言えませんが、「ADHDかもしれない」と悩まれる方がいらっしゃいましたら、その気持ちを蔑ろにせず、とことん自分自身と向き合うチャンスとして前向きに捉えて欲しいなと思います🌼
では!
より多くの方に読んでもらうため、 投稿はすべて無料記事にする予定です💌 お気持ちだけでもサポートしてくださると とっても嬉しいです☺️
