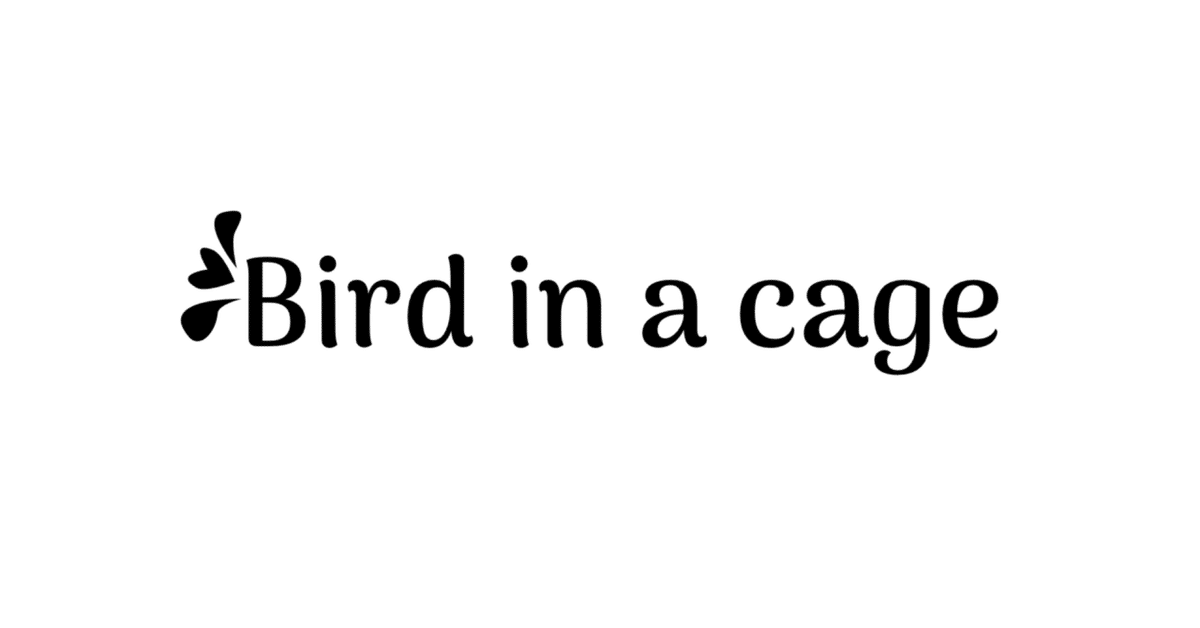
[短編小説]カゴの小鳥
「あなたは今、気鬱の病に罹っているから、しばらくは気楽に過ごしてください」
そう言った、短髪の胡麻塩頭の医者の表情をみると、からかっているわけではないらしかった。ただ事務的に、機械的に告げる男。会ったばかりのこの男の出す薬を、無警戒に体内に取り入れる患者の自分。これは、信頼ではなく怠惰だ。
病院と薬局と、数時間の拘束に疲れた僕は重い玄関扉を開ける。すると間髪入れずに、小さな高い鳴き声で、来い来いと鳴く小鳥。僕は、ベッドを横目に嫌々と小鳥の元へ行く。
「帰ったよ。さあ静かにしておくれ。まだ遊ぶ時間でもないだろう?」
覚めるような青。小さなくちばし。つぶらな瞳。俊敏に動く熱の塊。
カゴの中を跳ねまわり、カシャンカシャンと金属の音を鳴らす。
もともと、僕の鳥ではない。数年前、女が僕の部屋に転がり込んだ時に、一緒にねじ込まれた鳥だ。数か月前、女が出て行くときに、置いて行かれた哀れな鳥。
そうだ、愛情なんて元からなかったのだ。少しの同情と多大な惰性で、カゴの位置が変わらないだけだ。
しかし今、僕はとても疲れている。
「寝かせてくれよ」
そう言って、籠にタオルをかけた。これで静かになる。
僕は、のそのそと着替えを済ませてからベッドに横になった。
上司と話し合った結果、とりあえず一週間ほどの休みをとることになった。僕は若いから、すぐに復帰できるさと、エールをもらった。
泥のように眠ろう。そうすれば、起きた時に少しはすっきりしているだろう。
寝つきは悪く、ぼうっと良くないことを考えているうち、いつの間にかまどろむ。そして、悪い夢を見て、朝を迎えた。
「ピチュ、チチチ、ピチ、チチチ」
いつもの時間に小鳥が小さな声で鳴く。
まだ、寝足りないように思う。泥のように、溶けるように、どうしたら眠れるだろう。
ベッドから這い出して、狭いリビングに向かう。カゴの中の水と餌を新しくしてやる。
カゴの中では、小鳥が小さな鈴を咥えて振り、シャラシャラと鳴らす。
「わかった。わかったよ」
力いっぱい鈴を振る姿に負けて、小鳥をカゴから出してやる。時刻は六時過ぎ。
「正確に時を刻むんだな」
手に飛び乗った小鳥は、僕の指先に嘴を寄せる。
「チチチチ、ピチチチチ」
執拗にこすりつけられる嘴。
「さあ、そろそろ降りてくれ」
そう言って、小鳥をテーブルのに置かれたスタンドミラーの前に降ろす。小鳥は、いそいそと鏡に向き直って、鏡に映った自分に何事か話しかける。
これで、しばらく僕はほっておかれる。
安堵して、グラスに水を注いでテーブルに着く。
「明日も、明後日も、こうやって起こされるんだな」
独り言のようにみせて、小鳥に嫌味を吐く。小鳥は、鏡に映った自分に熱心に愛をささやき続けていた。
翌日、また小鳥に起こされて、同じように世話をする。餌をやって、カゴをきれいにしてやって、知能の高い鳥の心のケアに頭を使う。
でも、僕の鳥じゃない。愛してもいない。ただ、罪悪感を感じたくないのだ。僕の世話が行き届かなくて、こいつが病気になってみろ、なんて嫌な気持ちがするだろう。
もちろん、保護施設に預けることも考えた。実際、申込書に記入だってした。この鳥について質問通り、毎日何を何グラム食べて、いつもどこで遊んで、どんなオモチャが好きか、事細かに答えた。
まるで、飼い主が飼い鳥のことを、どんなに愛しているか再確認させるかのような項目だと思った。それでも、僕には愛がもともとないので、つらつらと書ききった。
ではなぜ、まだ小鳥がここにいるのか。簡単だ。その施設では、引き取った鳥を譲渡会に出すからだ。もし、審査の目を搔い潜った変質者がこいつを迎えたらどうなる。もし、不勉強な飼い主に当たったらどうする。いい飼い主に出会たとして、環境に馴染めなかったら。なんとも後味が悪いじゃないか。
そういうわけで、リビングには今も小鳥がいる。愛はない。煩わしくさえある。
ポックリ逝け。何の痛みも苦しみも感じず、さっさとポックリと逝け。
そう願って止まない。
昼まで寝ることをあきらめ、昼から寝ることにした。しかし、あれこれと頭に浮かんでしまって寝付くのが難しい。
諦めて本でも読もうかと思うが、心が動かない。動画でも観てみるかと、小さな画面上で指を動かそうとするが、うるさいとすぐにオフにしてしまった。
リビングへの扉の隙間から、細く一筋の光が指している。鳥はときどき、面白いことがあるのだろう、ピチピチと声を出して笑っている。
なんとなく、リビングに行ってカゴの中を覗いた。
僕に気付いた小鳥は、せわしくなくカゴの中で動き回り、鈴を咥えると、いつものようにシャラシャラと振って見せた。いつも通りの動き。そう、いつも通りに元気に見えた。
「お前! どうした?!」
カゴの床を見ると、水分の多い便に、赤い血が滲んでいる。
さあっと血の気がひいた。そしてすぐに頭に血がぐんと上るのを感じた。
バックンバックンと脈打つ心臓の音と全身の体温が下がるのを感じながら、外出用のキャリーケージを出しつつ、病院へ電話する。幸運にも、キャンセルが出た時間に診てもらえることになった。
ジップ付きの透明な袋に便の付いた敷き紙を入れる。真っ赤な色に不安が濃くなる。
「さあ、掴むぞ」
小鳥は大人しく僕の掌に包まれ、キャリーケージに入る。
病院はさほど遠くない。電車でも行けるが、音や振動が負担になるだろう。タクシーを呼ぶことにした。
病院へ着くと、しばらく待った。待ち時間の長く感じること。
やっと呼ばれて診察室に入る。
「血便が出ているとのことですが」
医者がキャリーを覗き込む。しかし、底には小さな固形の便がひとつふたつあるのみ。
「先生、これです」
血便の付いた敷き紙の入った袋を渡す。差し出した手が震えている。
「食欲もありますし、歌ったり踊ったりしてます。羽根もふくらませていませんでした。なんでですか? どうして」
しゃべると、両目から涙が溢れてきた。ぽたりぽたりと、滴が床に落ちた。元気そうに見えて、こいつは、苦しいのだろうか、痛いのだろうか。何をやっているんだ僕は。とんだ自己満足で飼育して、結局こいつを病気にしてしまった。
こんなに無抵抗に、信頼してくれたのに。愛情なんて与えられず、寂しいまま、健康すら守れず。
失格だ。飼い主失格だ。そうだ、どうしたって病や老いからは逃れなれないじゃないか。僕がしたのは、こいつを孤独に閉じ込めただけだ。ごめん。ごめん。
のどが締め付けられて息もできない。救いを求めるように医者の言葉を待った。
「ああ、これ、血じゃないですね」
笑みすら見せて医者が言い放った。
「え?」
医者の表情に理解が追い付かず、頭が真っ白になる。
「新聞紙を敷き紙にしてる方で、たまに勘違いされる方がいましてね。これは、濡れて裏面の赤い印刷が透けて見えてるだけです。心配なら顕微鏡でも観てきますよ」
何の言葉も出ないまま、医者がひっくり返して見せる新聞紙の裏面を凝視する。そこには、無数に咲く赤い花の写真が印刷されている。
呼吸を整えてから、にっこり笑った医者に、
「お騒がせしました」
と頭を下げる。恥ずかしくてそそくさと帰ろうとするが、医者に呼び止められる。
「でも、便の水分が多いですね。要観察です。何かあったらまた来てください」
僕は、また深々と頭を下げた。
帰りは電車を使った。電車の中でピチュピチュと小さく鳴くので、隣に座った幼稚園児だろう子供に注視された。
布をめくって中の小鳥を見せてやると、ぱあっと子供の目が輝いた。
子供の母親が、
「まあ、こんなに喜ぶなんて。今度、鳥さん観に行こうか?」
と声をかけていた。
僕は、よほど力んでいたのだろう、今は何だか力が抜けているのがよくわかる。
久しぶりに空腹を感じていた。料理はしないので、どこかへ飯を食いに行こうと思う。
電車を降りると、人通りの多い商店街を避けて家路につく。
両手にキャリーの入ったバッグを抱えて歩く。
ぶつからないように、揺らさないように、慎重に歩く。
傾いた日が射すリビングで、カゴの中の小鳥を眺める。
「ポックリ逝けよ。痛みも苦しみも感じず、ポックリ逝けよ」
カゴの中の小鳥にはっきりと言ってやった。
「ただ、それまでは、楽しくやろう、ハル」
そう言って、僕は小鳥を指に乗せた。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
