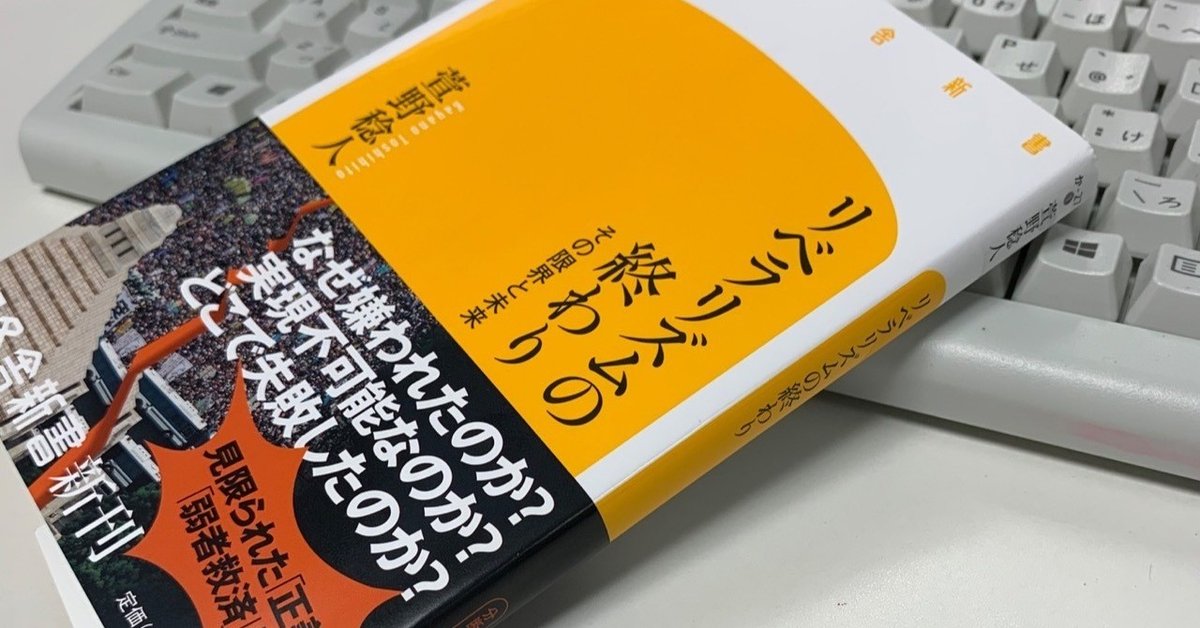
僕には結構納得できる整理でした:読書録「リベラリズムの終わり」
・リベラリズムの終わり その限界と未来
著者:萱野稔人
出版:幻冬社新書

佐々木俊尚さんのFacebookで紹介されて興味を覚えて。
いやぁ、実に興味深く、自分としても「腑に落ちる」内容でした。
<リベラル派への批判が高まっているのも、根本的にはこのフェアネスをリベラル派が徹底できていないことに理由がある。自分たちは権力に対峙しているのだから、多少の強引さや強権さ、ルール違反、不誠実、まやかし、暴論、暴言などは許される、というおごりが(本人たちがそれをどこまで自覚しているかは別にして)彼らからにじみでているのだ。>
いやはや、厳しい指摘ですが、頷けるところも少なくないです。
ただ本書はそういう「リベラルの欺瞞」を掻き立てるような作品ではなく(そういうのは百田さんあたりに任せてw)、「なぜそう言う批判が高まっているのか」その背景を分析しつつ、そもそも「リベラリズム」そのものの「立ち位置」「自己認識」に誤認があるのではないかと言う指摘をする内容となっています。
僕自身は自分のことを「リベラル寄り」と認識しています。(弱者の救済や、公平・公正の実現、人権重視等は重要だと思ってますから)
にもかかわらず、最近のリベラルサイド(意識するのは朝日・毎日や立憲民主党あたり)の主張には違和感と、時には苛立ちを感じることがあります。
「なんでかな〜」と思ってたんですが、本書を読みながら思い当たることがありました。
僕の考えは「功利主義(全体最適)を踏まえたリベラル」に近いんですよね。
すなわち「パイの拡大があってことのパイの配分」というスタンス。
「それが当然」と(無意識に)思ってたんですが、リベラルサイドの言説にはこの点を無視して、「配分」のみを<上から目線で>求める論調が少なくない。
ここが「苛立ち」のベースにあるんです。
「パイが拡大」している局面なら、それもいいけど、パイが停滞・縮小する状況ではそれはただの「ワガママ」と区別がつかなくなる。
リベラルが嘆くように、「世間が右傾化している」のではなく、「世間がパイの縮小を認識し、そこに不安を覚えるようになっている」のであり、そのことに「無自覚」に主張ばかり繰り返すリベラルの「思考停止」こそが問題…というのが本書の認識だと思います。
「功利主義を踏まえたリベラル」ってのは、そもそも近代の「リベラル」のベースとなるロールズの主張に近いスタンスというのも興味深いです。(ロールズ自身が意識的であったかどうかはともかく)
「リベラリズムが終わった」というより、
「ある程度、リベラリズムが成果を挙げた中、その成果を土壌として、<パイが縮小する>現実を踏まえた<次のステップ>に(リベラル勢力は)進まなければならない」
と言うのが僕の認識です。(その<現実>の中で「リベラル」な主張をして行く)
そこら辺の頭の整理に本書は非常に役に立ちました。
一読の価値あり、かと。
PS ちなみに本書が「幻冬社」から出版されてるってのも、ちょっと面白いですw。(懐が深いと言うか、ダボハゼと言うか…)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
