
俺たちは浅倉透と共有する
沼の中にいる。
沼の名をシャニマスという。
0.

『noctchill』というユニットは、ジュブナイルを根幹に据えたユニットである。
この場合のジュブナイルとは今風でいえばエモい、もう少しいえば青年期への懐古。
過去に未練がない人なんていない。それが未熟だった頃であればなおさらだ。
俺たちは『noctchill』が魅せる特有の”青さ”に、懐かしさと、同調と、後悔と、自嘲と、羞恥と、それらがない交ぜになったもので感情を揺さぶられる。
そのメンバーの浅倉透が抱える内面の"青さ"は、透明感が形を持ったかのようなルックスやシンプルで飾らない言動、それら人を惹きつける突出したタレント性によって隠れてしまっている。
言葉少なに出力される特有のフラットな視点は、バイアスまみれの俺たちには少し眩しく映るのだ。
1.

『noctchill』のキーワードを1番分かりやすく体現しているのが浅倉透で、彼女が纏う雰囲気に惹かれた人は多いのではないだろうか。浅倉透を表現する際、皆が皆、示し合わせたかのように同じ言葉を口にする。
透明感。
それくらい、浅倉透の持つそれは圧倒的だ。
けれど、最初に感じる非凡さに反して、実際に綴られる浅倉透の物語は誰もが覚えのある将来への漠然とした不安を描くもので、プロデューサーとすれ違う様子を通してただの口下手な女の子の姿も見えてくる。


表面上の浮世離れした雰囲気とあまりに少ないアウトプットが相まって、その真意を感じ取るのは難しい。
プロデューサーはそんな浅倉透とのコミュニケーションに悩んだ末、日誌を毎日提出させることにする。それでも、その控えめな言葉数は質の変化はあれど、最後まで量は改善しなかった。この一連のコミュは浅倉透が伝えることに前向きな姿勢を見せることで収束するが、ここから読み取れるのは彼女が伝えなくても伝わる幼馴染たちとの狭い世界で生きてきたこと、それから、極端なまでに執着心が薄いことだ。浅倉透の透明感の正体は、この執着心の薄さに起因する。

17歳はこの質問にもっとスラスラ答えられてもいいはずだ。
人間の思考の根源は執着心だ。これは欲望と言い換えてしまってもいい。ああしたい、こうしたいと思うから人の想いは難解になる。そして、人を人たらしめているのも何かをしたいという欲である。浅倉透にはこうした欲が欠けている。浅倉透は受動的に判断が求められれば回答を出すが、能動的に行動を起こすことをほとんどしない。彼女を人間として見ようとすると、そうした部分が空っぽで機械的に見えて、でもその様が彼女の魅力を際立たせていることは間違いなくて、俺たちは複雑な感情で悶々とするのだ。(これも一種の執着心である)

正直、イエーイ好き。
そんな浅倉透が唯一執着を見せるのがプロデューサーであり、WING優勝コミュでは、あのいつもシンプルな言動ばかりだった彼女が、真実を自ら告げるのではなくプロデューサーに思い出して欲しいという、なんともいじらしく複雑で、実に人間らしい欲求を口にする。
このプロデューサーへの感情が何であるかというのは難題だが、回答は彼女自身が出すべきで、曰く時間が掛かるというなら俺たちは待つだけだ。

ほとんど見せない人間らしさを見せるのがここっていうのは、頭ジャングルジムと言われても仕方ない。
伝えなければ伝わらないことを理解した浅倉透は、上手く形にできない内心さえもプロデューサーに伝えるようになる。そこから見える浅倉透の世界は、彼女と同じ透明感の塊だ。まっさらで、純心で、俺たちが普段見ているものと違いすぎて。
浅倉透というフィルタ越しにそれを見せつけられて、俺たちは昔見ていた世界が今より綺麗だったことを思い出す。
いつから、綺麗なものを綺麗だと言えなくなったのか。いつから、すごいものをすごいと言えなくなったのか。素直に表現するのは難しいと今は言えてしまう。だけど、昔の俺たちはそうだっただろうか。
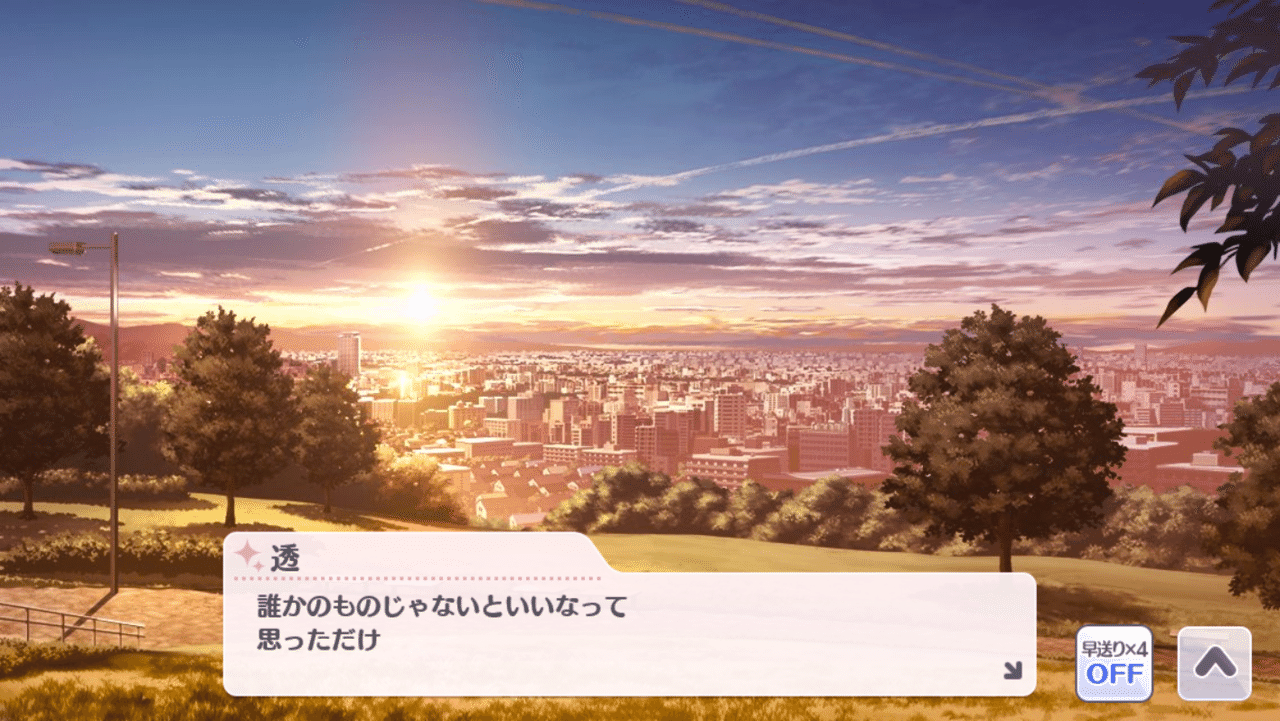

多分、俺たちが見ている世界もまやかしじゃない。けれど、一面でしかないことを俺たちは忘れている。浅倉透はもう一度世界の輝きを教えてくれるのだ。彼女と対等に他愛もない話をして、馬鹿みたいに笑って、仰ぎ見る空は鮮やかに映ることだろう。彼女と土手に寝そべって感じる風は、きっと心地よいことだろう。

浅倉透の"透明"に触れていると、頭をもたげることがある。
俺たちに見えている世界は、いずれ彼女も知ることになるだろう。それは、彼女を濁らせることにならないだろうか。先延ばしになるだけだとわかっていても、彼女をそれから遠ざけるべきなのだろうか、と。
その答えを、浅倉透は『天塵』で示してくれた。誰かの都合と誰かの都合でまみれた、あの番組と『noctchill』の境遇は、俺たちの見慣れた世界だった。打算と慣習と嘘に塗りつぶされた、本当にくだらない、俺たちの世界だった。
その中心にいて、浅倉透の"透明"が失われることはなかった。
善悪でものさしを当てるなら、未熟で愚かだったのかもしれない。それでも確かに浅倉透は浅倉透のままでいて、自分でいることなんてとうに諦めた俺たちは、羨ましくて眩しくて、胸の苦い痛みを自覚しながら目を離せずにいた。
浅倉透は"透明"で、同時に鮮明だったのだ。
透明な輝きは見えづらいかもしれないが、見つけた人はその輝きにきっと魅せられる。透明に染められる。
浅倉透なら、それができるような気がするから。
その日まで、俺たちは中身のない話で笑い合うのだ。

俺たちは浅倉透と共有する。
何色に触れても透明でいられるなら、それはきっと何よりも鮮やかだ。
俺たちは浅倉透と共有する。彼女の世界と、俺たちの世界を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
