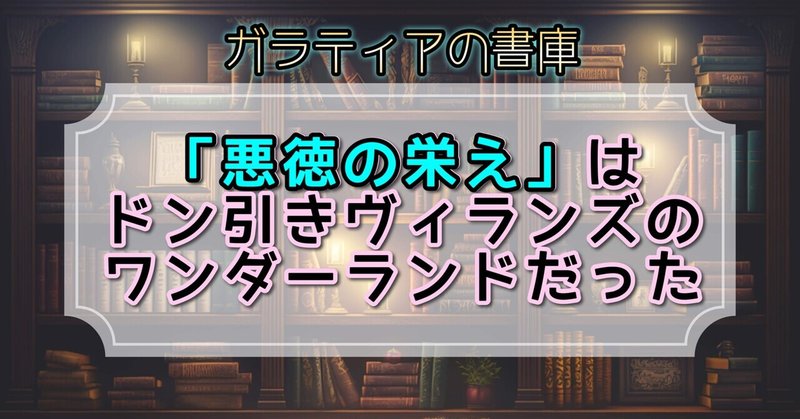
【書評】「悪徳の栄え」はドン引きヴィランズのワンダーランドだった
「悪徳の栄え(上)(下)」(澁澤龍彦訳)は、マルキ・ド・サドによる長編小説だ。
このサド伯爵は、ご存知の通り「サディズム」の語源となった18世紀フランスの人物で、執筆活動の大半を獄中で過ごした。
そんな彼の紡ぎ出す書であるから、当然その内容は残虐に満ちた惨憺たるもので満ちている。
今回紹介するこの作品は、
稀代の悪女ジュリエットを主人公とした回想譚という設定で、清廉な妹であるジュスティーヌが完膚なきまでに打ちのめされる「美徳の不幸」(同著者)の続編という位置付けがなされている。
起伏に富んだストーリーがあるというよりも、
その物語はひたすら拷問と殺戮のオンパレードであり、サドの性癖博覧会とでも言える「カタログ」的なものだ。
ジュリエットに悪事を手ほどきする者、一緒になって悪事を楽しむ者、ジュリエットさえ恐れを覚えるほどの残酷な人物……
数多く出てくる登場人物は、まさに笑えないレベルのヴィランズ揃い。
夢の国ならぬ悪夢のワンダーランドである。
今回は、この小説における特に個性的な何人かのヴィランズに焦点を当てて感想を書いていきたい。
①【淫乱な修道女「デルベーヌ」】
悪人度:★★☆☆☆
上下巻にわたって描かれる主人公ジュリエットの一生は、加虐と変態的快楽に満ちた非道なものである。
しかし、ジュリエットも最初から極悪だったわけではない。
…いや、その素質というか種は彼女の中にあったのかもしれないが、初めから開花していたわけではないのだ。
彼女はその運命と境遇によってさまざまな人物と出会い、悪の愉しみを覚えていく。
その中で、最も重要な人物の1人が最初に出てくるデルベーヌだろう。
デルベーヌは、ジュリエットが幼少期に預けられた修道院の院長である。
彼女はいわば"少女の園"を支配する尼僧であり、
夜な夜な少女たちと淫らな秘め事をするレズビアンのシスターだった!
1章から淫乱シスターとは……サド、初っ端から飛ばしている。
当然、院に入ってすぐにジュリエットも彼女の快楽の餌となってしまうのだが、
デルベーヌはこれでも、作中これから出てくるヴィランズに比べればだいぶ温情が残っていると言えるのだ。
信じられないって?信じられないでしょう!
それほどまでに、他の悪役たちは恐ろしい人間たちなのだ。
覚悟して読み進めてほしい…
事実、デルベーヌは誰にでも手を出しているわけではなく、正式に修道女の誓いを立てた娘に関しては「そうした若い娘さんとも遊びたいのは山々だけれど、何もその娘たちの一生を滅茶苦茶にしたくはないわ。修道院で過ごした一時期を、娑婆へ出て行ってから楽しく思い出させてやりたいわ。」と述べている。
僅かながらもこうした理性を残しているのは作中ではデルベーヌのみである。
本書を読むにつれ、デルベーヌがいかに分別があってまだ生優しいかを実感せずにはいられない。
肝心のジュリエットはというと、最初は驚き、戸惑ったものの、見事に放蕩の楽しさに目覚めてしまった。
ところが、修道院を出ることになったジュリエットが後日、彼女に会いに行くと、
あれだけ貪るように愛撫してくれたデルベーヌの態度は打って変わり、
閉じたままの門の中から「もういっしょに暮らしているわけでもないのに、あんなつまらない昔のことをいつまでも覚えているものじゃないわ」と素っ気なく追い返すのだった。
院内の少女たちを情欲のままに激しく求めるが、一度出た人間には途端に興味を失う。
彼女は特定の誰かを愛し、欲情するわけではなく、「少女の身体」、もしくは「少女という概念」のみに火種を見出しているのだ。
個人への執着がないデルベーヌは、快楽のみに心を向ける、ある意味さっぱりした爽やかな女性だった。
というわけで悪人度☆2。
大悪女として育っていくジュリエットを目覚めさせた張本人という元凶的な意味では、最も罪が大きいかもしれないが。
②【DV男の最終形「ノアルスイユ」】
悪人度:★★★☆☆
次に登場する主要な人物は、ジュリエットが院を出た後に出会う男、ノアルスイユだ。
彼は作中でもキーマンとなる人間で、物語の最後の方まで登場している。
彼は男前の貴族だったが、妻にむごい仕打ちをすることが至上の楽しみという男だった。
ノアルスイユは妻の目の前で他の女と色事を演じ、それを妻自身に手助けさせた末に妻を無理やり犯す趣味を持っていた。
日頃の激しい暴力・折檻は当たり前、ジュリエットとの遊びを楽しんだ夜も、食事会ではノアルスイユの指示によって妻がひとり全裸で彼らに給仕することとなった。
可哀想なことに、妻は至って普通の感覚を持った常識人で、なおかつ気弱な女性だったため、どれだけの無理な要求を突きつけられても泣きながら従う他なかった。
そんな妻を見て、ノアルスイユは逆にいたく満足するのである。
最終的には、ノアルスイユは仲間たちとともに妻をとろ火でじわじわと炙りながら毒殺してしまう。
その場面は、作中でも珍しいほど臨場感に溢れた細かい描写がされており、読者の吐き気を催したシーンではないだろうか。
彼は、ジュリエットの芽吹いてしまった悪徳の心をさらに加速させるガソリン的な役割を担っており、
折々の遊戯を楽しみつつそれをもっともらしく正当化する弁論家だった。
乱暴、盗み、殺しなど何でもござれで残虐性は低くはないのだが、饒舌で小物感が拭えないので悪人度は☆3。
③【変態糞爺「モンドール」】
悪人度:★☆☆☆☆
次に、1章分しか登場せず、物語の根幹にもさほど関わらない人物であるが、モンドール老人は個人的にインパクトが大きいので紹介したい。
この老人は70歳の大富豪で、院を出た後のジュリエットが所属した娼館の常連客だった。
その特異な性癖を満たしてくれるなら何人でも女を呼び、金に糸目はつけないという、なんだか現代にも居そうな人間である。
モンドールの性癖は一言で言えばスカトロ。
仰向けに寝かされた彼を数人の女でビンタしながら顔に唾を吐きかけ、その口に汚物と放屁を浴びせかけてやらないと果てることができないという、
ダイヤモンド富士の撮影並みに達成条件が厳しい攻略難度スーパーハードのジジイだ。
だがさすがはジュリエット、老人の要求に見事に応え、仕事を終えることができたのだった。
モンドールは故意に物理的な危害を加えたりしない分、悪人度は☆1だが、変態度でいえば間違いなく☆5である。
④【悪虐大臣「サン・フォン」】
悪人度:★★★★☆
続いて登場する悪人は、絶大な権力を持ったろくでなしだ。
なにせ大臣である。
ジュリエットとの出会いのきっかけは、悪事を犯した彼女が一度は嫌疑をかけられるもなぜか無罪放免となったことだった。
実はノアルスイユに頼まれ、権力によって彼女のために罪を帳消しにし、事件を隠蔽したのがサン・フォン本人だったのである。
この人物は、あらゆる異常性癖を詰め込んだ性癖キメラみたいな男なのだが、
そんな人間が権力を持つとさあ大変である。
名家に生まれ、「権勢は国王すらも凌ぐ」と豪語する彼は、これまでに2万人以上の無実の人間を自身の気まぐれと享楽のためだけに不当に監獄送りにした桁違いの悪徳人だ。
歪みきった偏執を揺るぎない地位と権力を以て実現するのだから、彼の餌食になった人間はたまったものではない。
しかしさすがは我らがジュリエット、彼に人糞まみれの尻を舐めろと言われても、口の中に放屁させろと言われても、乳房の上に尿をさせろと言われても、ことごとく命令を完遂してのけた。
サン・フォン登場以降は、個人的な快楽主義からシステムを使った大掛かりな加害へと話の体質が変化していく。
それでも、人体をいたぶり、命をことごとく軽視したプレイの数々は健在だ。
ジュリエットのパトロン兼共謀者として、一生豪遊できるだけの金と、邪魔者をすべて投獄できる勅状を与えることを約束した強力な後ろ盾。
しかし、「平民を大量に餓死させるために国中の穀物を買い占めよう」というサン・フォンの突飛な提案にさすがに難色を示したジュリエットは彼の不興を買ってしまい、死の危険から逃亡せざるを得なくなってしまう。
ジュリエットすら震え上がらせる闇の権化。
なかなかに恐ろしいが、もっとやばいのがいるので悪人度は☆4だ。
⑤【冷血な貴婦人「クレアウィル」】
悪人度:★★★★★
続いては、ノアルスイユの紹介でジュリエットの友人となる未亡人、クレアウィルだ。
彼女は才知に溢れる大柄な美女で、学術や芸術に長けている一方でこの上なく高慢・冷徹な人物だ。
しかし本作に登場するからにはやはり悪魔的で、サン・フォンが動の悪とすればクレアウィルは静の悪だ。(実際激しい遊びもしているが)
彼女は「本当の悪人は、あくまで冷静に罪悪にふけるべきものだわ。」と、平常心のうちに悪事をやってのけることを信条としていた。
それは、欲の中に罪を見つけるのではなく罪の中に欲を見つける、すなわち悪事を悪であるという純粋な理由だけで愛し行うべきとする彼女の哲学に由来している。
そんなクレアウィルは、過激派のフェミニストでもある。
男女ともに血塗れに痛めつけることを好む彼女だが、女性に対しては愛着から、男性に対しては憎悪から同様の行為をしている。
また、サイコパス気質ゆえ殺人すら一切厭わないクレアウィルがその対象とするのは男性のみなのだ。
サン・フォンから逃れるため、一度はクレアウィルとはぐれたジュリエットだったが、下巻において奇跡の再会を果たしている。
(その際、クレアウィルは実の兄と結婚しており、過去には2人で数えきれない放蕩をしでかしたことが明らかになっている)
そこから2人はイタリアを旅しながら、招かれたナポリの豊年祭で千人規模の殺戮を楽しんだり、共通の友人をヴェスビオの火山口に突き落としたりした。
クレアウィルはジュリエットと最も悪事を共にした親友であり、ジュリエットの悪徳を最高潮にまで高めた人物だ。
作中、ジュリエットと並んで拷問・殺害した数はダントツでナンバー1だろう。
彼女の苛烈な内面と行いは、読者の心にもおぞましく刻まれていることと思う。
悪人度☆5。
⑥【静かなる魔女「ラ・デュラン」】
悪人度:★★★★★★★★★★
最後に紹介するのは、あらゆる毒薬を精製し売っているという"魔女"ラ・デュランだ。
彼女との出会いは、魔女の噂を耳にしたクレアウィルと共にジュリエットがデュランの家を訪ねて行ったことから始まる。
デュランは魔女と呼ばれるだけあって占いなど神秘にも精通しているようで、
名乗ってもいない2人の名をピタリと当てた。
この際、クレアウィルに向かってあなたは5年後に死ぬと予言する。
さらに、これは作中最大のミステリーとも言えるが、
唯物主義・現世快楽をベースとした当作において、説明し難い超常現象を引き起こしてもいる。
デュランは2人の目の前に"空気の精"と呼ばれる痩せこけた男をたちどころに出現させ、もう一度指を鳴らすと煙と共に消し去る芸当をした。
そんな摩訶不思議な魔女の家には、噂に違わぬ膨大な種類の毒薬があった。
ジュリエットとクレアウィルは、使う相手を妄想して昂りながら、いくつかの毒薬を購入した。
さて、この毒薬の精製ルートであるが、魔女というだけあって人体を原料にしたものが多い。
それも、ゆりかごで寝ている赤子だったりするものだから、サドの倫理観の逸脱は半端ではないことが窺える。
そしてそれらを含めた毒は、個人の毒殺はもちろんのこと、
「ペストを蔓延させることも、河に毒を流すことも、伝染病をひろめることも、田舎の空気を腐らせてしまうことも、家々や葡萄や果樹園を荒廃させてしまうこともできる」という、
公害レベルの劇薬揃いだった。
5年後、クレアウィルとイタリアを旅していたジュリエットは、アンコナの町で奇遇にもデュランに再会する。
再会を喜ぶ3人。
デュランの家にジュリエットらが招かれると、クレアウィルが席を外したタイミングを見計らってデュランが警告してくる。
クレアウィルがあなたの生命を狙っている、こっそり私だけに打ち明けてくれた、私はあなたのことを愛しているからそうはさせない、この毒薬を使ってやられる前にやってしまいなさい……
突然の話に衝撃を受けたジュリエットだったが、その話を聞き終わる頃にはクレアウィルへの怒りと憎悪が噴出した。
次の日、食事の席でジュリエットはデュランからもらった毒薬を盛ってクレアウィルを毒殺する。
だが後から分かったことでは、全てはジュリエットを独占したいがためのデュランの嘘であり、クレアウィルは全くの無実だったのだ。
己の欲のために巧みな嘘で他人を操り、自身は手を汚さずして敵を厄介払いさせる。
そしてその死はデュランが予言した5年後という時期にぴったり符合していた。
この狡猾さ、執念深さは他のヴィラン達に比べて群を抜いている。
変態と加虐者が跋扈する本作において明らかに異質な悪人である。
悪人度は驚異の☆7とする。
感想と結末考察
以上、悪徳の栄え(主に上巻)に登場する悪人たちを何人か紹介したが、その濃さに目眩がしたのではないだろうか。
このような人物たちが上巻下巻通して他にもたくさん登場し、終始ひたすら残酷な描写が続くのだ。
様々な意味で、これほど読んでいて辛くなる著書もなかなかない。
作中の悪人たちによる非道な行いの数々は気を病みそうになるものばかりで、
悪人度に関しては正直甲乙つけ難い。
今回は周辺人物にのみフォーカスしたが、主人公ジュリエットはというと、彼らの哲学を余す所なく汲み取ってきたのだから当然☆5は優に超えるだろう。
そして、それらのキャラクターたちを全て生み出した根源である著者サドこそが、思想的には最も悪人度の星数が多い人物であるだろうことも忘れてはならない。
淫乱、残酷、悪徳。
バラエティ豊かな悪人図鑑といった趣だが、やはり際立っていたのはラ・デュランではないだろうか。
描き方からしても、サドにとって特別な思い入れがあるキャラであるように思えた。
この作品はジュリエットが栄華を極めたまま物語の幕が降りるが、あとがきでは、ジュリエットの最期を飾る事件に関しては本人以外に知るところはなく、例えどんなストーリーを予想したところで真実の筋書きには遠く及ばないという旨が書かれている。
これは、ミロのヴィーナスの腕などで論じられるような「欠如の美」ともいうべき、虚無の中に完全を見出す思想が見て取れる。
それでも無粋なのは承知の上で、陳腐ながらもその最期を予想するに、
デュランが偏愛の末に騙し討ちでジュリエットを毒殺したのではないだろうか。
サン・フォンやノアルスイユの流血沙汰の性癖にも涼しい顔で応えてきたジュリエットである。
被虐の末に殺されるタマではないだろう。
稀代の悪女の最期は、それを上回る悪女による計略によってしか考えられない。
というより、ジュリエットがそこまでの悪女であるからにはそれに相応しい最期であってほしい、そうでなければ納得できないという一読者なりの淡い期待があるのであった。
《追記》
悪の同盟は愛による絆ではない。
そこにはいつあってもおかしくない裏切りの可能性が常に潜んでいる。
悪に溺れる者が本当に愛をもって守れるのは自分の身だけ。
そこに、悪徳の限界があるのだ。
"ジュリエットの最期"が何らかの"事件"によって幕引きされていることが作者本人によって明かされている以上、彼女は誰かの悪徳の犠牲になったはずである。
皮肉にも、サドは気付かぬうちにそれを証明する墓穴を掘ってしまったということなのだ。
悪徳の栄えは永遠でも完璧でもない。
他人にした行いは、身をもって必ず報いを受けるのである。
マルキ・ド・サド著
澁澤龍彦訳
河出文庫
↓Youtube↓
https://www.youtube.com/channel/UCvAdRIhON5dM6CtY80OI1sg
↓朱雀Twitter(X)↓
@Suzakujpn
↓朱雀インスタ↓
@suzakujpn
↓TiKToK↓
@suzakujpn
↓スキ♡してね!サポートも待ってます^ ^↓
タピオカミルクティーのタピオカ抜き飲みたいのでサポートしてください。 ♡
