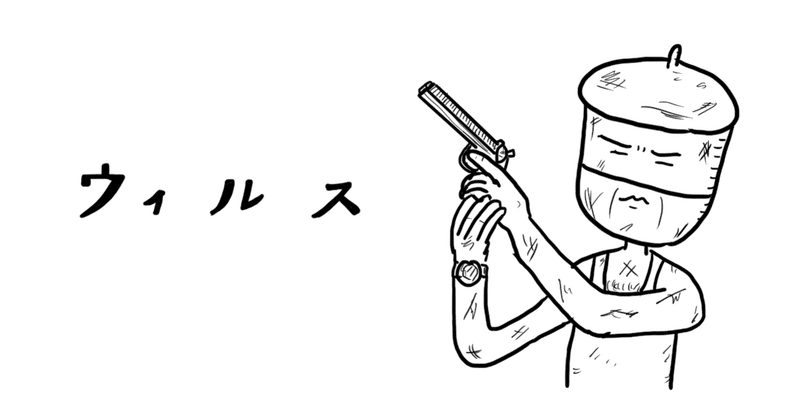
コロナ禍が終わった日なので、経営に関する「新しい現実」を見つめ直してみる
この世界は、人々の認識にが生み出すパラダイムによって形作られている。後々振り返ったとき、今日という日はそんな認識の変化の起点となる1日になるだろう。
ようやく2020年から3年以上続いたコロナ禍が終わった。
もちろん、ウイルスが無くなった訳じゃない。
けれども、3年前には未知のウイルスだったものが既知のウイルスとなり、法律上の定義が変更され、これからマスクをする人は徐々に減ってゆき、やがて時と共に過去の記憶となる。
そんなタイミングの今日だからこそ、コロナ禍を経て起こった経営に関する「新しい現実」を、リアルとオンラインのバランスという観点から改めて確認し直してみたい。
すでにリモートワークを廃止し、全員出社に戻した企業もあると聞く。ただ、この流れは再びリモート許容の方向へと向かわざるを得なくなるものと思われる。
昨年8月に発表されたとある調査データによると、2024年新卒社員の約65%が就職先の選定に働き方(出社かテレワークか)を意識すると回答している。コロナ禍以降に就職活動をしている今年の学生のデータを追加で見る必要はあるが、基本的にこの流れは今後も大きくは変わらないだろう。
働く側は、決して出社を拒否している訳ではない。むしろ適度な出社を望んでいる。適切な質・量のリアルなコミュニケーションを確保しつつ、リモートという選択肢も確保しながら、柔軟に働きたいと考えている。むしろ長く働き続けるためにも、それを重要な要素だと考えている。
どこまでリモートを許容できるかは業種や職種によって異なるだろうが、少なくとも企業の側は今後人材を確保するためにも、一定程度のリモートワークを組み込むことを前提とした仕事の設計に取り組む必要があることは確実だ。
会議に関しては、ほとんどの企業がすでにそうなっている様に、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド型が基本になるだろう。在宅ワークへの対応だけでなく、出張先や営業先から会議の時間だけ接続して参加できるのは、タイパの観点からも極めて合理的だ。かつての形に戻す必然性はほとんどない。
人材育成に関しては、理論や情報の取得はオンライン中心に、実践による能力習得は一部がリアルに戻る流れだと思う。スキルはオンラインでも学べるが、人としての成長は人との関わり合いの中で学ぶ必要がある。
実は会議と人材育成に関しては、「時間」と「空間」という2つの軸から考えると組み立てやすい。要するに、①共時性が必要のない会議・人材育成 ②共時性は必要だが空間は別で良い会議・人材育成 ③時間・空間ともに一緒でないと意味をなさない会議・人材育成 が存在するということだ。
とくに人材育成については、コロナ禍で後回しにせざるを得なかった部分があるはずだ。これをいかに回復させるかを考える必要があるのではないだろうか。
最後に、製品と流通チャネルについて。3年前の緊急事態宣言の時ほど急激ではないが、コロナ禍の終了によって流通チャネルは確実に変化する。顧客は元の動きに戻るのではなく、この3年間をふまえた新たな価値基準で行動するようになっている。
顧客価値と流通チャネルの双方が変化しているということは、これまでの事業戦略が機能しなくなる可能性があるという事。
「物価が上がったから」のような言い訳を聞くことも多いけど、本当にそれだけが理由なのか確認し直して欲しい。そもそも1年前から始まった物価上昇に対して戦略を練り直していないこと自体が大問題なのだから。
今回はこの3年で起こりつつある新しい現実のうち、「経営戦略の前提」を変えそうなものを挙げてみた。他にも沢山、3年間で変わった前提・現実ははあるはずだ。
あなたの身の周りで起こりつつある「新しい現実」は何だろうか?
この記事をきっかけに、ぜひ考えてみていただきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
