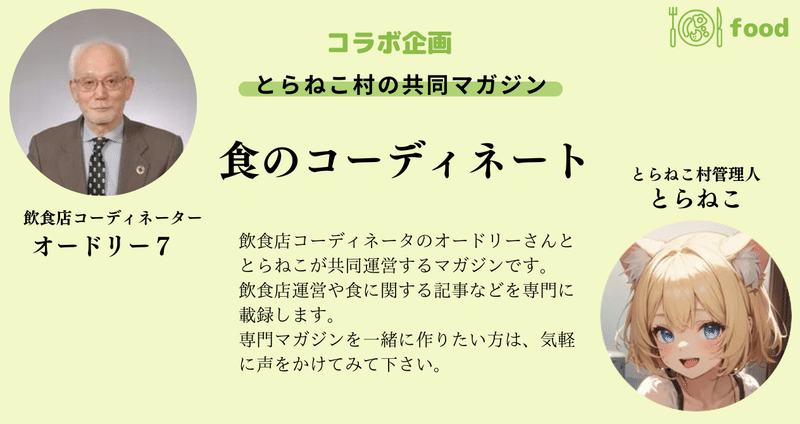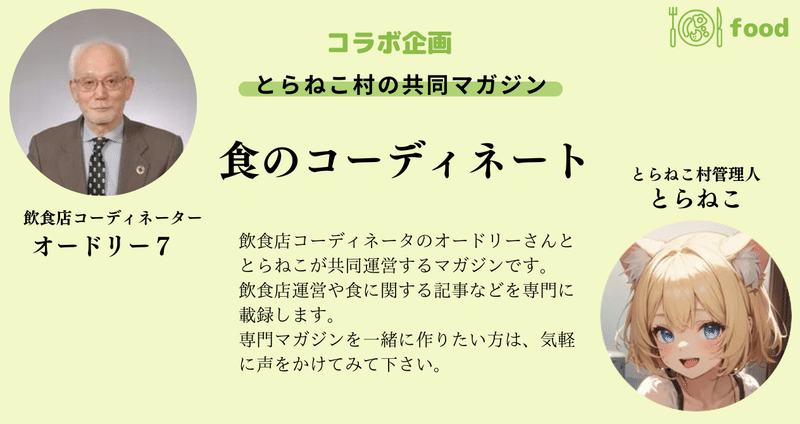飲食店未来学64:人手不足は魅力不足が原因です
飲食業界に関わらず、どの業界でも、人手不足や定着率の悪さに悩んでいます。私が思うには、やはり「仕事や職場の魅力不足」が最大の原因と思うのです。では、その魅力とはどんなものがあるか、飲食業界を例に、ちょっとだけ考えてみましょう。
最終的には、会社側と働く個人のエンゲージメント(相互信頼関係)と言われるが、私は、もっと奥深い「私の人生をここで費やす」という覚悟が生まれるほどの心がないと、そうはできないと思います。
仕事自体に魅力がある今は、猟師にしても、農家にしても、民芸品づ