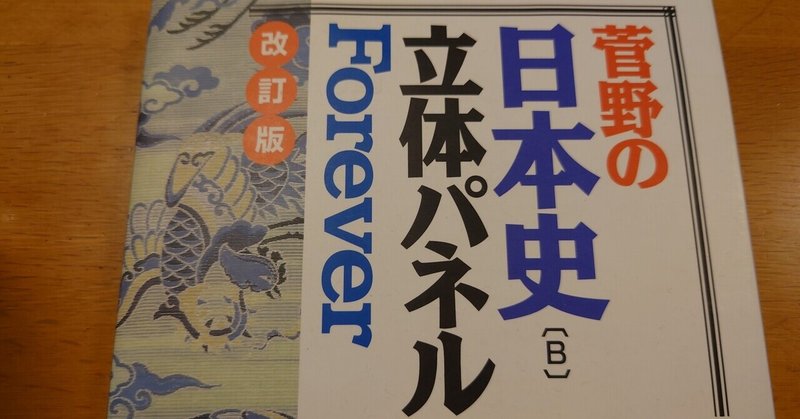
日本史の眠眠打破
言語という概念が生まれる前からの日本での人間活動の変遷を学ぶ科目、日本史。その学問としての歴史は古く、最古の歴史書資料として古事記が存在する。戦前日本は神国であったため、現在の日本史にあたる国史という教科は、学校教育の中でも特に重要視された。しかし、現代日本の教育にとって、日本史というのは余りにも眠気を催す科目である。私は日本史が好きだが、確かに今の標準的な授業体制では多くの睡眠学習者を出してしまうのは仕方がないとさえ思えてしまう。
この文章を読む事が既に眠い事かもしれない。しかし、私は日本史を一過性の暗記科目で終わらせては勿体ないと考えている。まず、そもそも暗記科目と割り切るにしても覚えやすい教育を施すことが適切である。今回は、悩めるスリーパー達に少しでも授業を受けてもらうための方法を考えていきたいと思う。(一番にやりたい仕事はゲーム制作ですが、非常勤講師もいいなと思っているこの頃です。)
①映像・図解を積極的に用いる
近年では大分減ってきてはいるのだが、未だに板書や口頭のみでの説明で、生徒への配慮を欠くような授業が存在している。歴史系科目は特に、教育者側の熱意が必要である。また、図を用いると言っても、ただ教科書の図をコピペするのは意味がない。そう考えたときに、授業内に時間をとって生徒に自ら図を整理することを課してもいいのではないかと思う。近年はアクティブラーニングを取り入れた授業が増加している。現在はまだうまく扱いきれていない教員が存在するが、能動的に考える仕組みを整備することは教育水準の向上に大きく寄与するであろう。勿論、教員側もその模範となるような解説が出来るようにしておかなければならないが、やはりただ板書を移すよりもより精密に内容が整理される。
②文化史とその時代の俗世間を絡めて説明する
眠い日本史の中でもその最たるものが日本文化史である。写実的に描かれた東大寺僧形八幡神像や、阿吽で知られる金剛力士像、世界最古の印刷物である百万塔陀羅尼など、かつての日本の文化を知るための多くの貴重な資料が教科書に並べられているが、あくまで並べられているに過ぎない。ひたすら作品を暗記させていく指導が多い文化史だが、その文化一つ一つを取れば、現代に繋がっているものも多い。例えば、平安時代の有名な作り物語に源氏物語があるが、内容を紐解くと日本最古の同人誌である。そう、今は自粛中のコミックマーケットで取引されているような同人誌の源流は、源氏物語に行き着くのである。このように、昔の文化については生徒に親近感を持たせる解説をすることは十分可能である。
まだまだ提案したいことはあるが、ひとまずはこれで。来年度からは、長年に渡り多くの受験生を苦しめた日本史Bは、日本史探求に名を変える。しかし、結局生徒がどれくらい日本史に興味を持って臨むことが出来るのかは、教壇に立つ者の手腕にかかっているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
