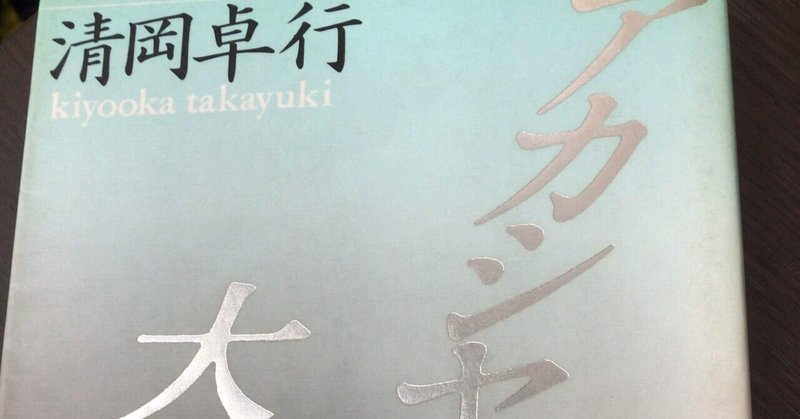
清岡卓行「アカシヤの大連」
暑くて肉体が苛まれている時に、読む本ではなかったことを明記しておきたい。意外に、というと著者に失礼になるが、記憶とふるさとの関係についての考察が難解で、とにかく頭を使う小説であったことは間違いない。
そもそも条件が悪かった。家から20分、キオスクで文庫本を2冊買うために、バス代をケチろうと徒歩で駅まで来た。本の代金として、チャージしようと思ったら財布がない。昨日、野菜を買った時に使ったエコバッグの中に入れたままであったことを思い出した。
余分なカードもなかったので、家まで20分の道のりを再び戻った。暑かった。さすがに家に戻った時には水を欲した。少し涼んで再度出発した。それで、身体にいささかのダメージが残っていたのである。もちろん文庫は買った。しかし、今時、ブンガクの文庫を2冊買っただけで2000円。中公とちくまだぜ?1000円程度かと思ったよ。
疲弊しながら開いた『アカシヤの大連』は、例の夏目漱石の『門』の読書感想文に出てきた原田(仮名)が好きだった作品の中の一つ。いや、一番好きと言っていたような気もする。あの当時は、大作家くらいしか知らなかったので、日本の芥川賞受賞作家とはいえ、身辺の内容をメインにした作家のことは知らなかった。
だから、そんな知る人ぞ知る作家の作品まで読んでるんだ、と原田のことを尊敬していた。で、私はあまり自分がないので、人が読んでいる本をとりあえず読んでいくということを目標としていて、原田が清岡の『アカシヤの大連』がいいといえば、清岡卓行を集めてみようということになった。
いや、実際は、清岡卓行という作家は、メインは詩作であり韻文であり、小説や散文は多くない。なので、文芸文庫で『アカシヤの大連』以外はなかった。他の文庫レーベルでもそう。なので、探したのはこの一冊。当時ブックオフで100円均一でゲットしたお宝。後生大事に抱えて、今に至るのだから、原田に対する私の思いの深さが判ろうというもの。
ではそれは、どんな作品なのか。
あらすじ
語り手が語る大連とは、日本の旧植民地である大連のことである。その大連に「彼」はノスタルジーを感じており、その「彼」が突如として起こした終戦間際の大連への旅行について、語り手は話そうとする。
「彼」は大連から東京に引き揚げてきて、もう21年になるという(1967)。妻と子どもと忙しくも楽しく暮らしていたときは、大連のことなど思い出したりすることは多くなかった。けれども、ごくまれにその記憶が浮かび上がってくる。
例えば、8年ほど前(1959)。地球儀を見ていたときに、在りし日の大連のあった遼東半島の地図を見て、思い出した。それはちょうどアルジェリア独立に際して、ド・ゴールの政策が支持されたという報道(1959)があったりして、植民地と自分の距離が重なったのかもしれないと回顧される。
また、6年ほど前(1961)。野球を見に行ったときに、グラウンドの証明に渡り鳥がぶつかり、落下した。その渡り鳥は、アカエリヒレアシシギという名前だ。その鳥の死体を譲り受けて、ふと、大連の子ども時代に、兵隊の銃をいじっていたら暴発して騒ぎになったことを思い出す。そのときに自分が死んでいたら、母親はどう思ったのかと、渡り鳥の死骸と自分の仮想的な死骸を重ね合わせる。
しかし、1年前(1966)に妻を亡くして、2人の男の子と暮らすようになって、しばしば大連のイメージを思い出すようになっていく。
「彼」は1945年3月下旬に内地から大連に向けて旅立った。抽象的な悩みを抱えた大学1年生のとき。帰ったら、戦争へと行かなければならないという思いを抱えながら、生まれ故郷である大連へと戻る旅行だ。この不安定な足場の中で懊悩する「彼」は、戻った。
4月の初めに大連の実家に来た。数日、疲れからか蕁麻疹が出たりして寝込んだ。寝込んでいる間、この1、2年で内地で経験したことを思い出していた。東京大空襲を、二子玉川の下宿から見たこと。死ぬ前に実家をみたくて、休学のための診断書をもらったこと。友人を連れて、大連への旅に出たこと。間釜連絡船の切符がどうしても手に入らなかったこと。撃沈されるかもしれない恐れに苛まれたこと。高校2年の学徒動員のときに、故郷の高知でまで行ったのに、即日帰郷になったこと。なぜか召集されなかったことに、罪悪感と喜びが混ざり合っていること。
結局、「彼」は下関から麗水に渡る臨時コースの船に乗った。その間、家族との思い出が浮かび上がってくる。小学生のときだ。旅順、哈爾浜、海水浴場。麗水につき、現地の人の家に泊めてもらう。列車に乗り、鴨緑江を超え、満州に入り、鳳凰城に近づいてくる。そして、列車は大連に到着した。
5月。大連の街は美しい。「彼」の郷愁を誘う。都市には美しい部分と、醜い部分とがある。光と影。大義名分と実態の矛盾。生まれ育ったふるさとである大連。内地から来た父母には日本に確固たるふるさとがある。「彼」のふるさとは大連である。
彼はふと、自分が大連の町に切なく感じているものは、主観的にはどんなに〈真実のふるさと〉であるとしても、客観的には〈にせのふるさと〉ということになるのかもしれないと思った。
学校で、大連のアカシヤは、ニセアカシヤというのだと習う。しかし、「彼」にとってニセアカシヤこそが真のアカシヤなのだ。
どこの愚かな博物学者がつけた名前か知らないが、にせアカシヤから「にせ」という刻印を剥ぎとって、今まで町のひとびとが呼んできた通り、彼はそこで咲き乱れている懐かしくも美しい植物を、単にアカシヤと呼ぼうと思った。
召集がやってくるまで、「彼」は戦争のことは一切忘れて、孤独な密室にふけろうと決意した。兄たちは戦争に行っている。姉たちの夫は満州で技師として働いている。弟は内地で高校に行っている。今、自分一人だけが、実家にいる。ただひたすら、無為に過ごしている。同じ日課の繰り返し。ぼんやりと暇つぶしにふけっている。
7月。ぼんやりと大連の風景をみながら、夢想にふけっている。子どものときのエロティックな光景や、印象に残った景色。海を見るのが好きだった。死に対する考察が湧きあがってくる。甘美な死の概念を、「彼」は知的に理解しきった気になっていた。しかし、一方で、女のエロティックなイメージが「彼」を生の側に押しとどめていた。
ここで「彼」は、大連に関する二つのテキストに関する考察を始める。森鴎外の『うた日記』にある「夢のうちの奢の花のひらきぬるだりにの市はわがあそびどころ」だ。もう一つは安西冬衛の「てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた」だった。この二つのテキストから、鴎外の個人的な夢の後景と、安西の国家の向こう側にあるむきだしの土地の観念の二つに引き込まれていった。
そして、原爆の報を聞き、やがて、終戦が訪れた。一週間も過ぎたころ、ロシア兵が進駐してきた。横暴には悩まされたが、その程度で済む生活だった。ソ連兵が、家に入って生活するようになったが、案外親しみ深かった。そんな日々にまぎれて、もう死の観念をもてあそぶことはなくなってしまっていた。
多くの日本人は内地へ引き上げていった。財産の少ない人から順番に引き揚げていった。技術者や医者などは現地に残り、社会機能を継続させていた。「彼」の家族もその一団の中にいた。「彼」は、家の物を整理しつつ、仕事を探した。
そして「彼」はとある化学技術者と知り合った。そして、そこの娘を紹介された。彼女とは、仲良くなり、そして恋に落ちた。
彼の内部によみがえった、観念としての、甘美な死と芳潤な生の対峙は、彼女の出現によって生におおきな重味が加わり、その拮抗はまったく安定したものとなっていった。「彼女と一緒なら、生きて行ける」という思いが、彼の胸をふくらませ、それは、やがて、魅惑の死をときどきはまったく忘れさせるようになっていた。
感想
分かりにくいな、と思ったのは、語り手が物語の主人公に据える「彼」が、語り手と同一人物である可能性が高いのに、わざわざ「彼」と三人称で呼ぶところだ。
私は、こう思った。私は、こう行為した。そう言ってくれれば語り手=私になって読みやすいのに、なぜ、同一人物っぽい「彼」をわざわざ「彼」と言ったりするのか。その効果や如何。
語り手がスイッチして、そのスイッチした語り手が、思い出にフラッシュバックするという形式が、錯綜していて案外にわかりにくい。大連に戻りついたのは語り手が思い出している「彼」なのだが、その「彼」が今度は1、2年まえの東京のことを思い出す、というスイッチが行われる。そして、「彼」が記憶の主体になっていくのだが、そこから、さらに現在へと突如として戻ったり、大連に関する考察などが挟まったりして、言うなればさまざまなエクリチュールが試されているという感じなのだ。
話としては、戦争に召集されるかもしれぬ大学生が、とりあえず実家の大連に戻って、死について色々考えたりして悶々としていたら、いつしか戦争が終わってしまい、ロシア兵も進駐してきたけれども、そこまで陰惨なことは起こらず、引き揚げするかしないか迷いながら、同じ技術者家族となんとか暮らしていたら、将来の妻と出会い、仲良くなった、というストーリーである。
メチャクチャ強引にまとめると上記の通りで、ドラマ性も案外薄めで、戦中の話であるにも関わらず、幸福感に満ちている、それ故に不思議な作品である。
「死について色々考えたりして悶々として」のところが、文章量としては結構多くて、安部工房が戦中にリルケなどを読みながら死ということを考察していたのと同じように、死のイメージと親しもうとしていた考察が描かれる。難しいのは、想念の回想なので、その考察が現在の語り手と過去の語り手のどちらに帰属するのかが不文明で、その曖昧さを味と捉えるか、不徹底と捉えるかの違いで、芥川賞の選評が別れたように思われた。瀧井孝作のように、私の目が一つの声ならんと欲する人にとっては、語り手と語られ手が明らかに同一であるにも関わらず、分離することで距離を生み出そうとする技術に対しては、割り切れなさを感じるものだろうし、井上靖のように客観化することで物語と作者の距離が担保されるという信念がある人ならば、記憶の二重化は客観性のある物質のような記憶として感じられたのかもしれない。
あれだけ終戦末期に、死についてあれこれ考えていた「彼」が、戦争が終わったと同時にその想念から解放されて、急に性や恋愛という生の最たるものに関心が移ることに関してはアレレ、と思わなくもないのだが、戦争文学というジャンルにおいて、逆説的にこの末期こそが幸福だったと裏返すような視座は、国境付近にいた人たちからすると、なんなんだよと思ってしまうものなのかもしれないけれど、ちょっと距離を置いてジャンル全体として眺めてみると興味深いと言える。
それにしても、現金なものである、といったらルサンチマンに過ぎようか。構成的には、なんだかとても面白いものを持っている『アカシヤの大連』だが、原田は、そうした技術的な部分が好きだったわけではないだろう。鬱々とした毎日に潤いを与えてくれる女性の出現と、その女性の信奉という結末部への期待が、この作品への傾倒につながっていたのではないか。
いや、それはあまりに原田をバカにした物言いだろうか。
原田の彼女の相談の中には、《あまりにも繰り返し彼女のことを大仰にほめたたえる振舞いの意図》は何か、というものがあった。今なら、気にしすぎではないか、と言うかもしれないが、あの頃はどうしても、その種の原田の振舞いを私も批判的に解釈せざるを得なかった。原田が『アカシヤの大連』ごっこをしていたのならば、それは幼稚と言わざるを得ない。
しかし、さすがにそのような作品への没入と模倣をするかというと・・・結局私もまた、客観を装いながら、原田と彼女の仲を裂くことを言ってしまった。未熟というか、幼かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
