
meet CTOs vol.3~CADDi・LayerXと創業期の壁~
meet CTOsはさまざまな会社やフェーズを経験してきた先輩CTOを招き、議論を深めるイベントとなっています。
非連続な成長を遂げるために必要なエンジニア組織の創り方や、資金調達前・直後のスタートアップを牽引するCTOの役割、直面する課題など、ここでしか聞けないリアルな実体験を聞くことができます。
去る2021年9月28日には「meet CTOs〜vol.3 CADDi・LayerXと創業期の壁」と題したイベントが行われ、キャディでCTOを務める小橋昭文さんやLayerX 代表取締役CTOの松本勇気さん、日本マイクロソフトの「デプロイ王子」こと廣瀬一海さん、同じくモデレーターとして参加の南澤 拓法さん、Sun*のCTO’sで活躍する金子穂積の計5名が登壇。
創業期のCTOが持つべきマインドセットや立ち振る舞い、時間の使い方などを話し合うセッションとなりました。
創業期の2人目エンジニアに求められる素養とは?
トークセッションでは、モデレーターの南澤さんがあらかじめ用意した質問を中心に登壇者へ伺っていきました。
まず最初は「0→1フェーズでの2人目エンジニアの見つけ方や必須要件について」です。
創業間もない頃、ビジネスの基盤を固めてグロースさせるために、1人目であるCTOに次ぐ、2人目のエンジニアを社員として迎え入れる際、どんなスキルセットや考えを持った人材がフィットするのか。
名もないスタートアップ企業にジョインしてもらうために採用で心がけることは何か。
ユーザーに支持されるプロダクトを作るために、2人目エンジニアの採用は非常に肝となることでしょう。
もともとアメリカではハードウェア中心の開発に携わり、製造業の知見を有していたことから3年半前にキャディを創業した小橋さんは、現在40人超のエンジニア組織を統括しています。
そんな小橋さんは「会社の状況にもよるが、事業として成立させないといけないので、CTOは何でもやる覚悟を持った方がいい」と話します。
「キャディの創業当初は、コードを書く以外にも総務や労務の仕事もやっていました。とにもかくにも、事業を回すことで精一杯なので、CTOの業務範囲はエンジニアとしてのロール以外もこなす必要があると思いますね。キャディの2人目エンジニアの採用に関しては、私自身今まで海外にいたということもあり、日本国内の人脈が皆無でした。それが弱みであり、逆に強みでもあったんです。
友人に『業務委託でもいいからちょっと手伝って』と声がけできない分、2人目にふさわしい人材についてゼロベースで考えることができたんですよ。そんななか、自分の知見が不足しているWebアプリケーション開発の経験が豊富なエンジニアを採用しようと決めました。ソフトウェア開発は、小さくできればできるほどアジリティを担保できるので、エンジニアとしての素養はもちろん、自ら進んでいけるフレキシビリティな姿勢を持ち合わせているのが大切だと思います」
技術よりも、Willを強く持った人材の方がフィットする
一方、Gunosy、DMMではCTOとして技術組織全体の改革を担い、LayerXではフィンテックやプライバシーテックを中心に事業へとコミットしている松本さんは「創業期は“ガラガラポン”な状態ゆえ、ピボットや試行錯誤の連続なのでそれを楽しめる気概あるかどうか」がひとつの判断軸になると言います。
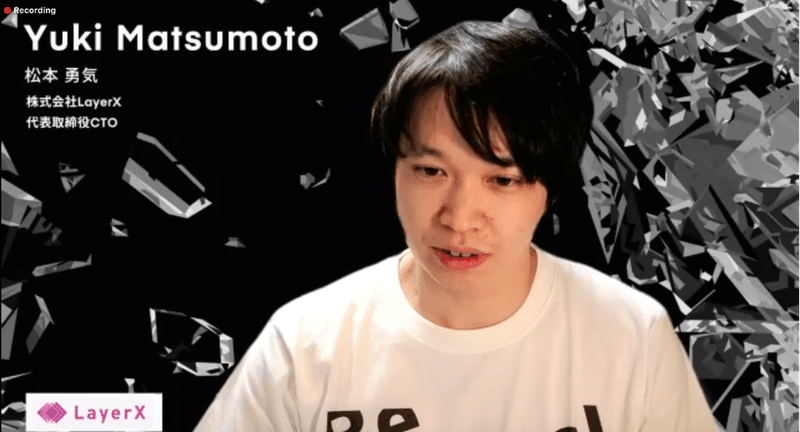
「最初からユーザーに刺さるプロダクトを生み出せるのは、奇跡に近いこと。戦略の見直しやターゲットの変更などはざらにあるので、2~5人目くらいのエンジニアを採用する際は『自分で作ったものを平気で捨てられる気質』が求められると考えています。そういう意味では技術力ではなく、探索・実験が好きなマインドセットがある方がマッチする。
開発だけやっているフェーズではないので、『さっさと小さく作って試そう』というコスパ思考があるかどうかがキーになりますね。エンジニアとして経験がある人材と、経験自体は浅いもののWillが強い人材なら、Willが強く、エネルギーのある方が絶対いい。キャッチアップしながら0→1はなんでもやるという心構えのある人材は、創業期においては重要な要件になるでしょう」
Sun*のCTOsの一員として活躍する金子も「探すのは難しいかもしれませんが、創業時のカオスな状況を楽しめる人材が、2人目エンジニアには適任だと思います。加えて事業自体に感銘してくれ、CTOとカウンターパートとなってコミュニケーションできるのも大事な要素です。総じて、経験が浅くてもキャッチアップ能力に優れ、コミット力が高ければ十分にワークする。逆に、普通の社員ポジションを求めている人材は合わないでしょう」と述べました。

Microsoft Azureの第一人者として知られ、現在はエンタープライズ向けのアーキテクトを行なっている廣瀬さんは「キャッチアップ能力や強いWillを持っていないと、道半ばで心が折れてしまう」とし、「最近感じているのは、各業界や業種のドメイン知識があるかないかでも変わってくると思っています。プロダクトを成長させる上で、業界慣習や構造を理解していればアドバンテージになる。業界知識に加え、エンジニアリングもわかる人材は重宝するでしょう」と語りました。
CTOの時間の使い方は経営判断に近い
続いては「マネジメントと開発者寄りの動きはどうバランスを取っているのか」についてです。CTOポジションは、コードを書くこと以外にも、エンジニア組織全体のマネジメントひいては会社組織の成長を技術的視点から支える役目をこなさなければなりません。
言うなれば、マネジメントと開発者としての時間配分のバランスいかんで、事業に大きなインパクトを与えるわけです。
「明確な答えはないものの、採用には3〜5割の工数を割いている」と語ったのは松本さん。
「優秀なエンジニアを集められるかが重要なので、一番は採用を頑張りつつ、状況に応じてコードを書いたりマネジメントのMTGを行ったりしています。ただ、常にトレードオフの連続なので、事業を前進させることは前提に、その時々で時間をかける優先順位を決めていますね」
小橋さんも「自分の時間の使い方はある種、経営の判断と近しい」とし、次のように説明しました。

「『人を見ているか、コードを見ているか』ではなく、組織や事業のマネジメントなど多角的な視野を持ちながら、時間の使いどころを決めて行かなければならないのがCTOです。最近では半年後、1年後のスケールを見据えたテクノロジーマネジメントも行なっており、どういう技術に投資していくべきかを日々考えていますね」
対する廣瀬さんは、「エンジニア組織が10人を超えるとコストコントロールが必要になる」ことに言及しました。
「エンジニア組織が拡張するにつれ、1人当たりの生産性が非常に大事になってきます。ガバナンス、セキュリティ、コストなどあらゆる要素を見える化しておき、経営判断できる数字を揃えることが、特に急成長スタートアップや上場準備に入った企業にとって重要になる。ことエンジニア組織においては、月次の人件費、クラウド費、開発費用などを全てスコアリングすることで、現状かかっているコストを可視化でき、改善できる点が明確になるので、組織成長に合わせたテクノロジーマネジメントを意識するといいのではないでしょうか」
風通しの良いエンジニア組織を創るには?
3つ目の質問は「後から入社した人を、既存社員の上に立たせる必要が出た場合、どう解決するべきか」。
ハイレイヤーやマネジメント層の採用の場合、プロパーではなく外から入社した人材がテックリードやマネージャーに就任することも多くあります。しかし、関係性の欠如やコミュニケーションロスによる既存メンバーとの軋轢が生まれることもあり、一筋縄ではいかないケースもあるでしょう。
こういった課題に対し、どのように対処していけばいいのでしょうか。
金子はSunAsteriskのエンジニア組織を例示し、こう話しました。
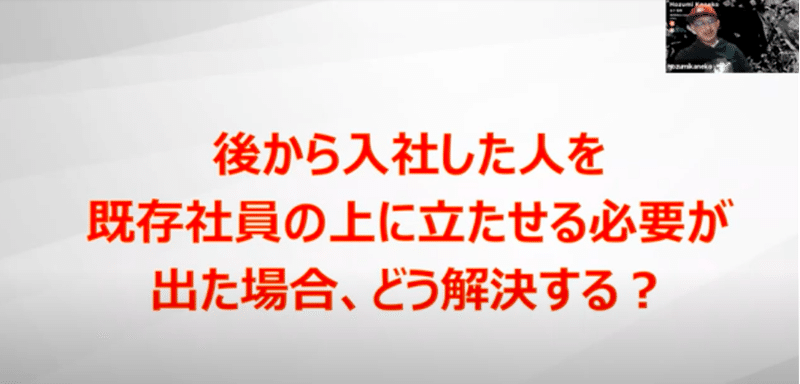
「うちの場合、若手エンジニアがユニットマネージャーに就任し、ベテランはその人のサポートに周る体制にしています。若手が活躍できる土壌を整え、チャンスを与えるのはもちろん、キャリアを積む上でもいい相乗効果が生まれると考えています。でも重要なのが、もともと話せる間柄を作っておくこと。プロジェクトを進める上での方向性や疑問点は率直に相談し、適宜対話できる人間関係があってこそ、成り立っている。ここを蔑ろにはできないと思いますね」
松本さんは「抜擢人事は前々からしっかりと計画することが必要になる」と説きます。
「組織図をあらかじめ設計しておき、キャリアアップの要項やキャリアパスの設定など、事細かに決めておくことが良いエンジニア組織を構築する上では欠かせません。というのも、いきなり外から入ってきた人をマネージャーに着かせると、そのポジションを狙っていたエンジニアのモチベーションを下げたり、距離感が生まれたりする原因になる。外部人材は数ヶ月くらい、社内で下積みしてパフォーマンス出してもらってから上に立たせないと、既存メンバーのやる気にも影響するので、計画性が何よりも大切になってきます」
小橋さんは「上下ではなく、組織の中でどういうロールを務めるか、ミッションは何かの方が重要」だと意見を述べました。
「組織構造上、指揮命令が発生する役職を決めるのは大事ですが、最終的には会社の成長に貢献できる組織であるかが問われると思っています。キャディでは、組織設計の幅や多様性を尊重していて、できる限りフラットな組織を意識しています。誰が上とかではなく、人によって得意不得意があるのを加味して、適材適所にロールを当てはめていくことに取り組んでいますね」
廣瀬さんはマイクロソフトの採用に関して例を挙げ、「組織の上下で考えないのが本質なのでは」と話しました。
「マイクロソフトは全ての職種でロールが決まっており、必ずしもピープルマネジャーの給与が高いわけではありません。また、新たなにポジションを募集する際は社内外から公募する形をとっています。あくまで、ジョブディスクプリションとロールが見合っているかをフラットに判断しているので、社内外問わず面接回数は同じなんです。ポジションにフィットする人材を公平に判断しているからこそ、組織の上に立つという考え方はあまりしていないのが率直な意見です」
CEOはビジョンを持ち、ロジカルであれ
4つ目は「テックリードでないCEOが、どこまでテクノロジー知識を抑えておく必要があるか」という、事業成長に寄与するテーマです。
ビジネスサイドとして、数字を作るためのマーケティングやセールスなどの戦略を描けるCEOが、テクノロジーの知識はどの程度理解しておくのがベストなのでしょうか。
松本さんは「とにかくロジカルであってほしい」と切り出しました。
「技術的なことはエンジニアチームに任せてもらっていいので、ロジカルに物事を考えられる素養が重要。もちろん、技術を勉強する気持ちがあるかどうかも必要ですが、CEOがCTOを信頼できるかが最終的には物を言うでしょう。エンジニアの考える技術戦略がうまく伝わらなかったら、自分の伝え方が悪いと思うようにしていますね。これは、DMM時代に得た教訓として肝に命じています」
廣瀬さんはロジカルに加えて「成長に必要なビジネスモデルを理解している」ことも求められると言います。
「サブスクリプションやSaaSなど、今伸びているサービスやプロダクトのビジネスモデルを理解しておくこと。さらには、テクノロジーがどのように使われているかも把握していれば、CTOとのテクノロジー関連の対話も腹落ちしやすくなると思います」
また、金子は「CEOはテックよりもパッションが大事だと思います。プロダクトやサービスへの熱い想いを持ち、既存の変えたいという志は、時に新たな視点を与えてくれます」とし、小橋さんも『キャディはレガシー産業である製造業をテクノロジーの力で変えるという創業時の想いに、エンジニアも共感してメンバーが集まっています」と、CEOがビジョンドリブンであることの重要性を説きました。
グローバルと向き合うなら、海外エンジニア採用は必須
最後は「開発組織の国際化並びに、海外エンジニア採用において取り組んでいること」という質問のもと、日本のエンジニア不足が叫ばれるなか、海外人材の活用における所感を語り合う場となりました。
松本さんは「今は日本だけの採用になっていますが、将来的には海外拠点も視野に入れていきたいと経営層の間で話しています。現地に乗り込んで、新規プロダクトを立ち上げる際に、海外のエンジニアと共創して作っていくこともあるでしょう。海外拠点の立ち上げはラクスルさんがすごい上手いなと思っていてリスペクトしているので、自分たちも成功事例を参考に取り組んでいきたいと思っています」と述べました。
小橋さんも「グローバルと向き合うなら、海外エンジニアは必須だと捉えています。採用もそうですし、将来的に海外拠点を作る際も、日本人以外のエンジニアは必要になってきます。現在はどういうスキルセットがあればいいのかなど、日本語がネイティブではない人材の採用要件を模索している段階ですね」とグローバル展開に向けた準備について話しました。
創業期から非連続な成長を続ける企業のCTOや、多くのスタートアップ支援に携わる当事者だからこそ言えるような、現場感が伝わるイベントとなりました。
今後もmeet CTOsでは、さまざまなCTOをお招きしたセッションを行っていく予定です。
乞うご期待ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
