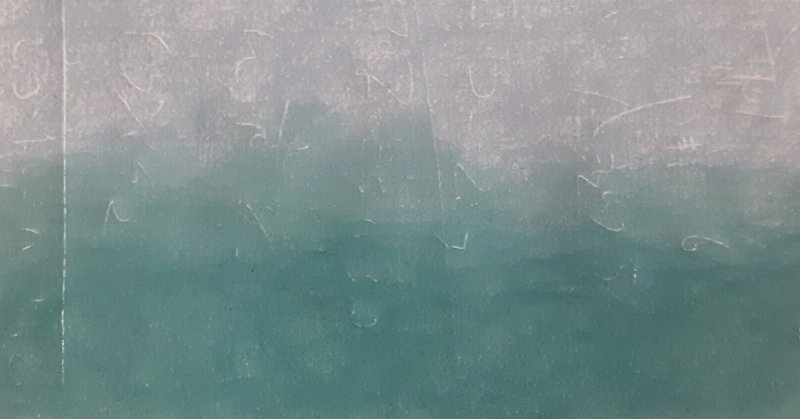
【小説】○と△と×と(#1)
あらゆるものが二重に見えるようになってきて、数をきちんと数えることができなくなってきた。私は困った。大きなビニールにぎっしりと詰まったクリップを大、中、小に分類してそれぞれきっちり100個づつ小さなビニールに分けて入れるのがあたしの仕事なのだった。あたしは職場で一番すばやくクリップを分類することができ、しかも絶対に間違えずに100個数えることができたので重宝されていた。そのあたしが、作業が遅くなった上に、大中小や数を間違えるようになったので、ある日、リーダーの人に呼び出されて、今週いっぱいでやめてくれと言われた。つまりクビだ。
あたしはあまり物を食べないし、学生時代に買い集めた本やCDやDVDがあれば退屈せず、使うお金は家賃と光熱費くらいだ。ひと月くらいなら何もしないでだいじょうぶだ。
しばらく部屋でぼんやりしていると、二重に見えるのが治ってきたので、そろそろ仕事を探そうと思ってネットの求人サイトを開いた。三日間の短期バイトが見つかった。「簡単な作業」としか書かれていない。屋外の仕事らしいが、特別な技術も必要ないわりに時給もいいので応募したら採用された。一日五時間程度だしリハビリにはちょうどいい。
集合場所は、家から電車で一時間ほどの駅だった。送迎のバスに乗ると、山を上って行った。下ろされた場所は広い草原で、大小さまざまな岩が見渡すかぎりごろごろ転がっていた。そんな光景を目にしたことがなかったので、あたしは、しばらく呆然と岩の群れを眺めていた。博物館で見たことのある火山岩みたいな穴だらけのものもあれば、つるんとした岩もあった。バイトは十人くらいで、年齢性別はさまざまだった。学生っぽい男女も数人いたし、主婦や、おじいさんといっていい年の人もいた。
係の人の準備ができるまで、草の上に座って待っていた、誰もが黙ってもじもじして所在なさげだった。こんな仕事に応募してくるのは、人と話すのが苦手なコミュ障気味の人が多い。クリップの職場もこんな感じだった。一人だけ、髪を金色に染めたギャルっぽい女子がいたが、待っている間ずっと背を丸めてパズル雑誌に顔を埋めていた。
しばらくして係の人に、ゼッケンとスプレー缶を配られた。あたしがもらったゼッケンには「△」と書かれていた。近くのはげたおじさんは「〇」でその隣のギャルっぽい女子は「×」だった。
配られたゼッケンを全員が装着し終わると、係の人の説明が始まった。
スプレー缶は白い塗料らしい。それを使って岩のひとつひとつに「〇△×」の記号を書いていく。書くのは、自分がつけているゼッケンに記された記号だ。岩の大きさに収まるようにできるだけ大きく書く。
これがあたしたちの仕事だった。
どの岩に書いてもかまわないが守るべきルールが二つあった。
①すでに何らかの記号が書かれている岩に重ねて書いてはいけない
②一つの岩に書き終えると、そこから最低二十歩移動したところの岩に書くこと
係の人の合図で、作業が始まった。空は雲がまったくなく貼りつけたように青かった。
あたしはひたすら岩にスプレー缶で「△」を描いて回った。言われたとおりに二十歩数えて歩き、また別の岩に△を描いた。
作業しながら、いったい、これは何のためにやっているのかという疑問が頭に浮かんだ。係の人からは何の説明もなかった。別にお金さえもらえれば気にならないのか、誰も質問もしなかった。作業しながら色々考えていたがそのうちどうでもよくなった。
始めのうちクリップの時のように効率を念頭においてすばやく△を描いて全力で次の岩に移動していたが、大小様々な岩の間を縫って歩いているうちにだんだん疲れてきた。体力にはあまり自信があるほうではないのだ。周囲の人を見ていると、おじいさんやおばさんは、疲れというより最初からそんな感じらしく、けっこうだらだらと作業をしている。ときおり、スピーカーを通した係の人の声が聞こえた。ゼッケンと違う記号を書いたり、二十歩歩かない人に注意をしているのだ。それさえ守っていれば、別に作業が遅くても何も言われないようなので、あたしも、ちょっとペースを落とすことにした。
「少し休みませんか、疲れるでしょ」
一時間ほどして、学生っぽい女子に声をかけられた。彼女は巨大な岩の裏にしゃがんでペットボトルのお茶を飲んでいた。あたしも便乗することにした。ここなら係の人からは見えない。
「ところで、これ、何なんですかね。〇とか△とか岩に描いて、何の意味があるんですかね。採石の目印かなんかですか」
例の疑問を彼女に投げかけてみた。彼女は、肩のあたりですっぱり切りそろえた黒い髪の両耳の脇の一部だけ三つ編みで、吸い込まれるような大きな目をしていた。
「アートですよ」
「アート?」
「コンセプチュアル・アートでもあるし、環境アートともいえますね」
意味がわからずぼんやりしているあたしに、女子は笑いながら説明してくれた。
「芸術形態の一種ですよ」
女子の説明によると、自然に人為的に手を加えて見たことのない光景を現出させる、環境を利用したアートなのだそうだ。女子は美大の学生で、大学の学生部を通してバイトに来たらしい。そういえば、数人の係の人とは別に一人だけジャケットを着て気取って椅子に座っている人がいたが、あの人がいわゆる作者、つまりアーティストなのだろう。
あたしは本も読むし映画も好きなのだが、ライトノベルやホラーややくざものなどの芸術性とはほど遠いものばかりでいわゆるアートというものには縁もゆかりもないが、そんなあたしが、アートの制作に加担しているという事実にやけに興奮した。
昼には弁当とお茶が支給された。筆書きで店の名前が印刷された、きちんとした紙の箱に入って、いくつも仕切りのある高そうな弁当だった。コンビニ弁当しか食べたことのないあたしは、なんだか自分が大切にされているような気がしてうれしくなった。
午後から、あたしは、がむしゃらにがんばった。クリップの時も、がんばっていたが、動機がぜんぜん違っていた。クリップの時は、別にがんばりたくてがんばっていたわけではなく。単に上司に認められたかったからだ。けれども、今、あたしは、ひたすら岩に△を描くことによって、アートを制作している。そのことが気分を高揚させ、あたしは、純粋にがんばりたくてがんばっていたのである。
(#2につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
