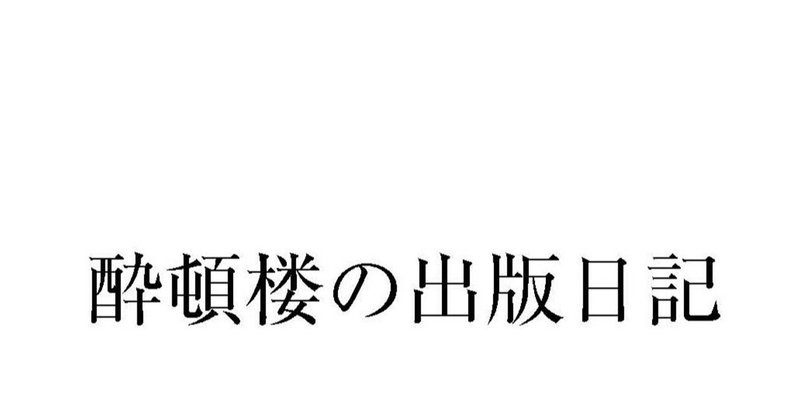
「一億総作家時代」も近い?
今朝の中国新聞「文化欄」に興味深い記事が掲載されていました。
『時代(とき)のしるし』というシリーズ企画で、今回のお題が「進撃のネット小説」。投稿サイトのネット小説から「夢を実現して」著作が書店に並ぶ〝作家〟がつぎつぎに生まれているという内容です。
寡聞にして知りませんでしたが、たとえば「エブリスタ」とか「小説家になろう」の二大小説投稿サイトがあって、これらのサイトに書き手が自作を無料で公開し、その作品が読者が評価されることで版元から出版される(こともある)という麗しいシステムが作動ちう、というのです。
エブリスタには現在100万本の作品が掲載されているといいます。
もちろんすべてではないにしても、ほとんどの原稿が「作家になりたい」という夢を叶えたい、という動機で投稿されているのでしょうから、その願望の熱量には圧倒されるばかりです。
この記事にもありましたが、「作家としてデビューしようと思えば公募新人賞で受賞し、出版社を通して本を出すのが、これまでの王道」だったのが、「今や、作家になろうと思えば誰でもなれる—。そんな時代が来たのだろうか」。
「かつてプロでない作家が作品を公表する場は同人誌などに限られていた。作品を広く世に送り出すかどうかの決定権はほとんど出版社の編集者にあった」が、「今では(中略)書籍流通の末端だった読者が、作品の方向性や良し悪しを左右するという逆転現象が起きている」
たしかに、うるわしい状況ではあります。
かつてブログがネットに氾濫しはじめたとき、プロの物書きにも劣らない書き手が市井にごまんといることが知られることになり、文芸言論界隈のシステムがいかに旧弊で硬直していたかが露呈してしまった苦い過去がありますが、既得権益の壁をぶち抜いてしまったこうしたネットの怒涛力は、その勢いを止めそうにもありません。
それにしても、いい時代になったものです。
物書きへの登竜門の門戸は広くなり、その敷居はほぼなくなったも同然。ぼくのように出版社を自らつくって、そこから作品を自費で出版し、怪しい文学賞をもらったことにして(本の帯の惹句で読者を釣るという風潮に対するパロディのつもりもあったのですが、著者と方法を間違ってましたね・笑)場所と作家を僭称するという反則技を使うまでもなく、労せずして作家デビューの可能性が広がったわけですから。
そこの作家志望のあなた…、
著書が店頭に平積みされる日はもうすぐそこですよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
