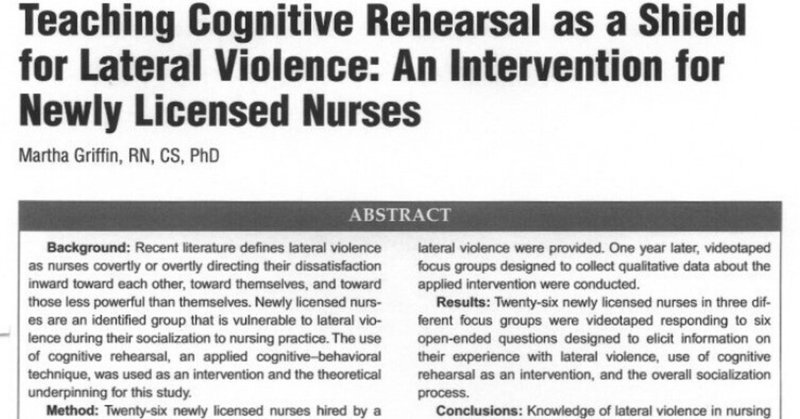
【職場いじめの認知的リハーサルプログラムオリジナル】Teaching Cognitive Rehearsal as a Shieldfor Lateral Violence: An Intervention forNewly Licensed Nurses
概要
新人看護師はいじめにあいやすい (恐ろしい導入になっている。よくある新人看護師のメンタルヘルスに関する講義の理由は、入職後の現実とのギャップやついていけない苦しみに対するセルフケアトレーニングと銘打たれているが、現実的にはいじめの影響があると明示されている)。認知的リハーサルのいじめに対する効果を検証することを目的とする。ボストンの急性期病棟における26名の新人看護師を対象に、職場いじめと認知的リハーサルによる対応に関するプログラムを実施した。適切な対応が記載されたキューカードを配布した。一年後にフォーカスグループで効果を検証した結果、プログラムによるいじめの知識は看護師がいじめを非個人化して受け止められるようにして、いじめと対応方法を学び続けられるようにした。また、認知的反応は、いじめと対峙するために役立った。全体として、研究参加者の職場定着率はプラスの影響を受けた。
問題と目的
(尚、職場いじめの恐ろしい点は、理論的には学校のいじめは教師や大人が介入するのが道徳的・倫理的観点から承認されているが、職場いじめは誰がどのように介入するか・するべきかという観点が全くないことである)
(ハラスメント対策も実際には国の主導で各会社のトップがハラスメントをなくすと方針を銘打っているわけで)
(本気でなくしたければ、その他いじめ行為も絶対に許さないと公表して取り組めばいいわけだがそれは法的に強制されていないからする必要がないわけである)
(したがって生じても誰も止めようとしないし、トップが止める必要がないとしている)
(何かもめごとが生じた場合に会社はこう言ってくる「相談窓口は設置しましたからそこをご利用ください」「調べましたがむずかしいところですがハラスメントではありませんでした」)
(それが今の日本社会であり、そのもとでの新人看護師への職場いじめの論文である)
1980年ごろから看護師の職場いじめは議論されてきた
看護師が階層構造上抑圧されたポジションにあることが大きな要因だとされている (そうかもしれないが、それなら看護師だけにとどまらず理論的に適応されうる)
(要するに、組織内で独立して意思決定を行えない部署があればすべて同じ理論の適応対象となる)
看護師の職場いじめの具体例は以下のものである
infighting among nureses
withholding pertinent information
sabotage
scapegoating
criticism
failure to respect confidences and privacy
つまり繰り返すが看護師の日常そのものであり上層部の看護師が暗黙のうちに肯定しているもので、あたりまえ、受け入れられない人はやめるしかない、それが理想と現実といいきかせられていることそのものである
United Statesでは、看護師の退職率は33%-37%
新人看護師の退職率は55-61%
60%の新人看護師は6か月以内にいじめにより退職している
(United Statesで日本と同様のことが指摘されていることから、看護師のパーソナリティーに帰属できるように見えても、理論的に説明したほうが適切だと考えられる)
いじめへの気づきを構築する

新人看護師に職場いじめの教育をするのは効果的と考えられる
認知的学習理論は、個人が因果 (ABC) を理解することに焦点づけている
認知的法理略は自己理解して環境に働きかける方法である
認知的リハーサルは衝動制御方法として教示される
教示を受けることでイベントへの反応を変えることができるいじめを理解した理論に基づいて対処することで、侮辱以外の処理を行うことができる
本研究の目的は
看護師の職場いじめの原因とその表出を理解できる理論的基盤とプロとしての実践を提供する
新人看護師の職場いじめへの脆弱性を周知して認める
職場いじめの典型例への対応を認知的にリハーサルしておくこと
である
方法
探索的な介入研究
新人看護師26名 (マサチューセッツ州のボストン)
新人研修の日に2時間で介入を実施
最初の一時間は職場いじめの理論的公正と看護実践、プロフェッショナリズムに及ぼす影響及び看護師の中でも脆弱なグループに関する講義を行った
次の一時間は、最も典型的な職場いじめに対する認知的リハーサルと適切な対応を行った

プログラムの最後に、2枚のラミネートカードを手渡された
最初の一枚は広くプロとして受け入れられている行動

二枚目のカードはキューカードで、10の典型的ないじめに対する適切な対処法が記載されている
(かなり細かいが、日本で記載の言葉を使うとけんかになるか、さらなるいじめにあうと思われる)
結果
参加した26名の新人看護師は全新人看護師の39%であり、男性2めいであった
一つ目の質問では、働き始めてからいじめを見たことがあるものは96.1%で46%が自分に向けられたと回答
二つ目の質問では、いじめにあった際に100%が責任者に伝えたと述べたが、46%はそれが正しい行動であったとしてもとても困難であり、泣いたり何とか声を紡ぎだして話したと述べた
その際に直接自分がショックを受けたと伝えたもののうち、58%は謝罪を受け、17%はなにもなく、残りのものはおよそ2週間程度無視された
三つ目の質問では、全看護師がその場でカードを使わなかったが、学んだ内容をいかした
92%が講義を覚えていたがその場で見る必要がなく、85%がカードによってエンパワーメントされたと述べた
また、4%が実際にそのセリフを相手に述べた
(こんな当たり前のことが記載された紙を持つだけでエンパワーメントされるほどに医療現場における看護職やスタッフのいじめはひどい)
四つ目・五つ目の質問では、病院を辞めようと考えていた4人の新人看護士が院内の別のポジションで働いていた
最後の質問では、ほぼすべての参加者96%が、全看護職にいじめのプログラムを行ったほうが良いと述べた
文献
Griffin, M. (2004). Teaching cognitive rehearsal as a shield for lateral violence: An intervention for newly licensed nurses. The journal of continuing education in nursing, 35(6), 257-263.
感想
適切な対応の記載はやはりむずかしい
しかし間違いを記載することで多くの看護師がエンパワーメントされることは明確に示されている
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
