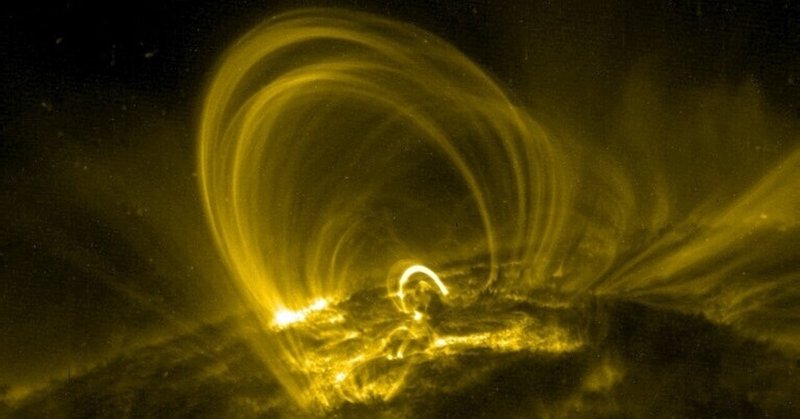
サミュエル・R・ディレイニー「コロナ」書評
今週2本目の書評は、八木あかりさんです。
サミュエル・R・ディレイニー「コロナ」(『ドリフトグラス』収録)
評者:八木あかり
音楽で世界を変える、なんてことはできないのかもしれない。しかし、音楽によって人が救われたり、人と人とがつながったりすることはあるのではないだろうか。これはその一瞬の輝きと奇跡を描く、優しさに満ち溢れた短編である。
人の心を読む能力を持った少女リーが、悪夢にうなされている入院中の宇宙港職員バディを悪夢から起こすことでふたりは出会う。その少女リーは人の心が読めるがために、いつも死にたがっていた。見知らぬ人の苦しみや恐怖を見続けているが、それを助けることができず自分までつらい思いをしていた。そんなリーが唯一助けることができたのがバディだった。ふたりの共通の話題としてあがるのが、銀河系でヒットしている「コロナ」を歌う歌手ブライアン・ファウストだった。バディはファウストを見るチャンスがある。整備工での勤め先にファウストの船が停まっているからだ。リーはファウストを見たいというが、医者に連れ戻されてしまう。代わりにバディはファウストがライブをするのを見に行く。何千人もの人々、バディも含めて、その歌声に聴きほれた。遠くの病室からバディと繋がったリーも、その歌声に聴きほれた。リーの死にたい気持ちは、ちょっぴり遠のいていた。
トロくて乱暴で金髪のバディがはじめてファウストの歌声を耳にしたのは、ケネディ宇宙港に勤めて一年たったころのことだった。その歌はニューヨークじゅうのラジオというラジオから流れ、宇宙船格納庫の内壁各所に埋めこまれたスピーカーからも流れていた。
重なり合うリズム、一転して訪れる静寂、つづいて朗々と響きわたるソロ・ヴォーカル、その上に、けたたましいオルガン、ものがなしいオーボエ、ベースとシンバルが重なっていく。
「バディはあまりものを考えない」にもかかわらず、こんなにも鋭く音を聴き取っている。これには私は驚いた。この表現でファウストの音楽がどんなものか、なんとなくだが私にも想像することができた。また、職場のビムに「ファウストの音楽は好きか?」と聞かれたときにバディはこう感じている。
音楽の奔流が耳からなだれこみ、心をかきまわして、さまざまなものをばらばらにしていく。断固たる韻律、たびたび引き込まれるシンコペーション、自分には捕捉しきれないほどの速い演奏にこめられたさまざまな想い。そのほとんどが、すばらしい想いばかりだ。だが、そのうちのいくつかは……。
「そのうちのいくつかは……。」とは何だったのだろうか。音楽の感じ方は人それぞれであるが、なんかヘンだ、と感じたバディにビムはさらっと「そういうやつはたくさんいる。」と言う。この短編の時代、1960年代にはサイケデリック・ムーブメントが起こった。サイケデリックミュージックでは、音響機器、エレキギター、エフェクター、残響、効果音などが利用されることが多い。バディらの感じた違和感というのはこういうものだったのではないだろうか。ファウストの音楽は万人受けするミュージックのなかにブラックな要素が入っていて、そこに何かしらの違和感があるからこそ、やみつきになり銀河系でヒットしているのではないかと私は考える。
私はこの短編で、音楽の力は偉大だと感じた。ずっと死にたがっていた少女の死にたい気持ちを少しでも遠ざけることができたのは、少なくともこの時点では音楽だけだったと思う。今、実際に私たちが生きている時代に流行している新型コロナウイルスの影響で、多くのライブが中止になったり無観客配信に切り替わったりしている。生の音楽にかえられるものこそないが、配信でもリアルタイムでライブを楽しむことができ、そこには多くの感動がある。それと同じように、少女リーは憧れのファウストを生で観ることはできなかったが、バディの脳内をとおしてリアルタイムで観ることができた。そのおかげでリーは少し救われたのだった。音楽で世界を変えることはできなくとも、人と人とがつながり、誰かを救うことはできるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
