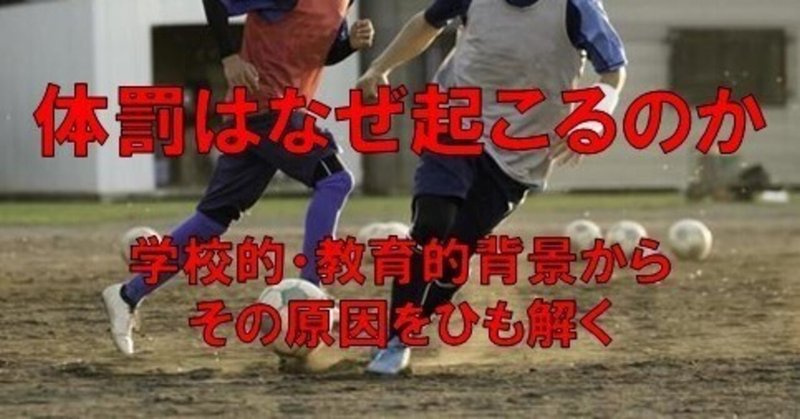
教育は人を変えられるか、という問いから学校での体罰問題をひも解く
コーチが部員に暴行を加える動画がネット上で拡散され、その後の不可解な対応を含めて炎上している熊本県八代市の○○高校サッカー部で新たな問題が浮上した。
騒動の発端となった動画を撮影し、投稿した2人の部員を糾弾する男性の音声が25日、ネット上で公開された。同校のサッカー部の指導者と見られる男性は自らを「完全な被害者」とし、さらに「俺が弁護士たちに被害を受けたと訴えたらどうするか?」と、脅迫まがいの言葉を2人へ向けている。 学校側はこの日、全校生徒約1000人を学年ごとに分けた集会を開催。不安を抱かせている状況を謝罪するなど心のケアに努めた一方で、○○監督(49)は日本テレビ系で生放送されている朝の情報番組「スッキリ」に緊急出演。サッカー部内で起こっている一連の騒動に「責任はすべてわれわれ大人にあります」と涙ながらに頭を下げていた。
上記、記事リンクより高校名、個人名を伏せて掲載
ある高校のスポーツチームでの暴行問題が、最近のニュースの話題になっています。
指導者から暴行を受けている部員の動画がSNSで拡散され、その後、暴行を受けた生徒を含めたスポーツチームが謝罪動画をアップした、という経緯があります。その後、謝罪動画は削除されました。
こうした躾、あるいは体罰とラベリングされる暴行行為は、なぜ教育的指導として、生徒、指導者に許容されてしまうのでしょうか。本記事では、この問題を2つの点からひも解いてみましょう。
1.教育は人を変えることができる、という強硬さに潜む危険
「学習は観察だ」という見方があります。教師は、人を成長させようと手間暇かけて日々、生徒を相手に指導をしています。そして、指導の成果として、学習前後の変化が可視化され、それが教師によって観察され、生徒への評価が実現します。これが円滑に上手くいけば、教師側には「この子は学んだ!」とか、生徒側には「僕は成長した!」という感情が双方にもたらされることになるでしょう。
このような指導と評価の歯車がかみ合わなかった場合、どのようなことが起きるでしょうか。
生徒に期待される変化が可視化されない場合、言い換えると、教師にとって自身の教育指導の成果が生徒から観察不可能であるときには、生徒は「学んでいない」「成長していない」「変化していない」と捉えられることになります。その際、熟達した教師ならば、期待される成果を可視化しようと、さまざまな指導や評価の方法を試してみることになるでしょう。しかし、このような代替手段を執ることができない未熟な教師にとっては、生徒の変化を観察することができずに、「この生徒は学ばなかった」「あの子の成長は見えなかった」と生徒側の問題として捉えられることになるでしょう。
生徒の学習は教師の観察によって操作的に創られた変化だということができます。生徒の学習が教師による観察次第ならば、「教育は人を変えることができる」という強い前提をもっている教師は、言わば一方通行的に強気に観察を試みることになるでしょう。そして、観察ができなかった時に、この望ましくない教師らしさの表れとしての一方的で強気な行為が、不適切な躾、体罰として行われてしまいます。
生徒の学習は、教師の操作が強く影響するものです。学習は、教育的文脈における特別な観察という営みの結果です。教師と生徒の考えの不一致や、いたずらや悪事、怠けなどの生徒の未熟な行為によって、学習という観察を為すことができなくても、躾、体罰によって強硬的に人を変えようとする行為は、とても危険であり、教育としては適切ではないでしょう。
2.学校という特別な価値づけが行われている環境
しばしば、教育的という言葉は、やっかいな言い回しになることがあります。学校は、学習のために創られた特別な教育的環境です。日常文脈では通用しなくても、学校文脈では教育的指導の名の下で、不適切に許容されてしまうことがあります。
体罰は紛れもない暴行行為です。街で大人が子どもを殴れば、明らかな犯罪でしょう。しかし、同じような行為でも、教育の範疇に収まるならば、それは教師にも生徒にも教育的指導と捉えられることがあるのです。
これは、暴行行為に限った話ではないように思われます。例えば、学習に不必要なものを持ってきたから、教師が生徒の私物を取り上げた場合はどうでしょうか。これも、街中で大人が子どもの私物を取り上げた場合と照らすと、適切であるとは言えないでしょう。
このような教育的指導は、特別な解釈がなされることが多くあります。少し話題を広げてみましょう。
私は研究者になる前は、小学校教員として、その前は、児童相談所職員として、さまざまな虐待事案について対応してきました。その対応の中で、身体的虐待を受けた子どもの多くは口をそろえて「悪いことをした僕(私)が悪いんだ。お父(母)さんは悪くない。」と言っていました。身体的虐待も大人から子どもへの明らかな暴行行為であることは間違いありません。
ここからわかることは、家庭教育の内においても教育的という言葉は、日常文脈とは異なる解釈がなされているということです。今回の被害生徒自身の謝罪動画のアップの一連の流れも、この不適切な解釈の観点から説明ができるでしょう。
教育や子育ての文脈では、明らかな犯罪行為も、学校(あるいは家庭)の中で行われれば、不適切に教育的と解釈され、罪を問われないばかりか、支持したり美談化したりする人まで現れます。教育や支援に関わる大人は、不適切な教育的な解釈を、今ここで再認識し、教育的という言葉そのものを改めて評価していく必要があるでしょう。
研究費サポートのお願い
ここまで読んでみて、無料で読める以上の価値があると感じ、有意義な知識を得ることができたと感じたら、「気に入ったらサポート」からお心づけをいいただければ幸いです。任意に選んだ教育団体への寄付、または、学術研究を向上させ、教育現場へ還元させるための教育研究の資金に充てさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
