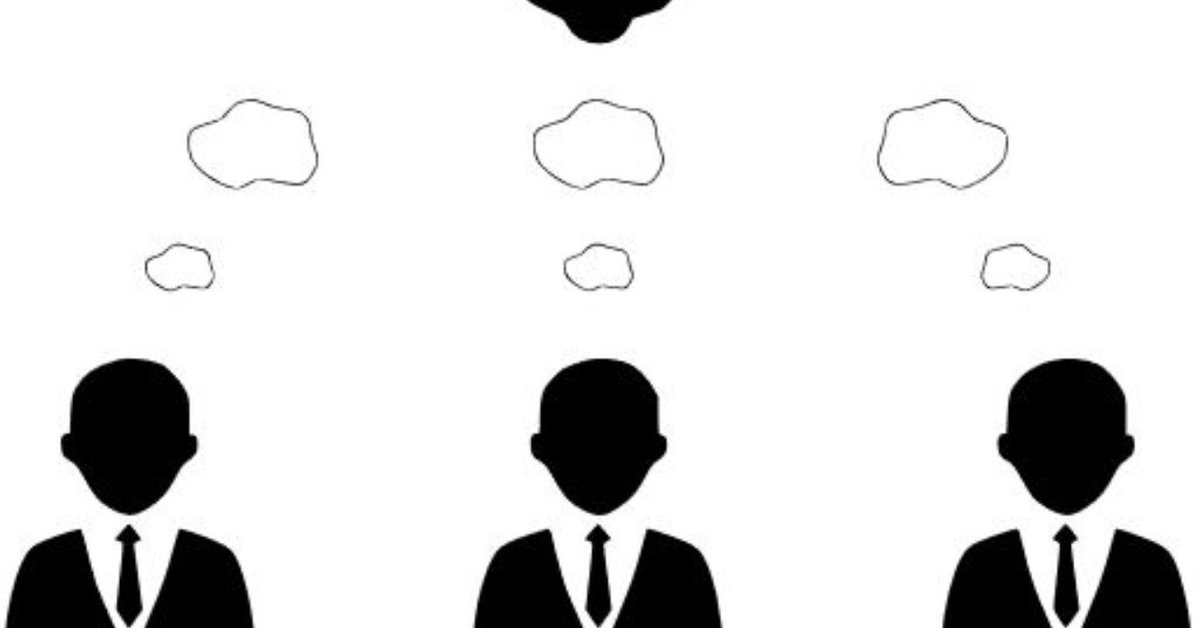
何から何まで全て記憶する必要はない
たまにどこからともなく聞こえてくる
「えー、そんなことも知らないのー」
どうなんでしょう。何の話題で盛り上がっているかは知りませんが、傍から聞いてていつも思うのは、
「なんで、知ってる必要があるの?」
です。いや、時事やゴシップは、井戸端会議や知り合いと話すときのネタとして新鮮なものを知っておいた方が良いかな?とは思います。まぁ、すぐ忘れてしまうんでしょうけど。でも、1週間~1か月程度は困らない程度に「そう言うことがあったんだー」的なことは知っておいた方が良いシーンも多いと思います。
けれども、オフィシャル…仕事となるとどうでしょうか。
仕事ってそんなに暗記が必要ですか?
私は、たまたま短期記憶と長期記憶の使い分けに慣れているのか、意外と記憶力はいい方です。けれども、記憶力があって「すごい」と言われることはあっても、記憶していなくて「仕事ができない」シーンに出会ったことがありません。
ビジネスの場では「いった/いわない」と言った水掛け論になって責任の転嫁などが行われないように、記録化することが一般的です。記憶に頼った仕事がどれだけアテにならないかは嫌というほど身にしみてわかっています。特に対外的な場ではそうでしょう。
余談ですが、民法に規定している13種類の典型契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)のうち、消費貸借、使用貸借、寄託以外は諾成契約の扱いとなります。諾成契約とは、当事者の合意のみで契約の効力が生じることで、当然ながら口約束でも、成立する契約のことを意味します。わざわざ契約書を残し、双方の合意の証としてサインや押印をするのは、法律がそう定めていたとしても、裁判自体は「証拠」を元に判断するため、裁判で勝つためにはどうしても必要となるから、というだけです。
契約書、仕様書、設計書、議事録、etc.…これらはすべて、
記憶と思い込みによって、問題が生じないよう、
その時の情報を切り取って、記録に閉じ込め、管理する
ために作成されているものです。スナップショットとも言います。用途はもちろん、あとで見返して「当時の時間軸から現在の時間軸へ、正確な情報を伝達するため」です。問題が起きたときに証跡とするのも、同じ目的からきたものです。もちろん、メールも同じ効果が期待できます。
本来は、ただのコミュニケーションツールなのでしょうが、たとえば、仕様書や設計書は、次の工程担当者へ引継がれるコミュニケーションツールであると同時に、前の工程と次の工程との時間軸を橋渡しするための記録と言う目的もあるわけです。
本当に必要なのは「情報」を取り扱う技術
東京大学の定期試験をご存知でしょうか。

東京大学では、原則として辞書や参考書、文献等の持ち込みを多くの課程で許可されているものがあるそうです。試験で求められている"実力"のコンセプトが、試験のためだけの「記憶力」「暗記力」ではなく、社会人になった後、与えられた情報から自分で調査、分析をおこなって自分なりの解答を導き出す「応用力」を養うことに重きを置いているから、と言われています(本当かどうかは知りません)。
本当かどうかはともかく、もし本当であれば、これは社会に出た時にとても有効性が高く、非常に効果的です。
既に知識としてはご存じかとは思いますが、世の中に出てしまえばマニュアルがどんなに存在してもマニュアル通りに事が進むと言うことがあまりありません。学生時代に学んだ勉強の内容もそのまま活用できる機会は皆無と言っていいでしょう。
だから、暗記力だけに頼って能力偏重すると、学生時代のテストにおいてはそこそこの点数が取れたとしても、社会では応用することができずに潰れてしまう人と言うのは珍しくありません。高学歴+就職難と言うのは、そういった側面もあるのでしょう。
いまだ、「学歴」に重きが置かれていた時代を生きた"団塊"の世代、"ロスジェネ"世代が中心となって世の中を回しているために、学歴重視をする人はまだまだたくさんいます。けれども、時代は変わり、それだけで仕事の良し悪しが決まることがあまり無い、ということも少なからず理解されるようになり、今では、学生時代の「テストの点数が高い」「いい大学に入れた」はあまり自慢にならなくなってきています。
実際、私も(まぁ色々あって)三流大出身ですが、ことITのビジネスにおいて出身大学云々で後れを取るようなことは一度もありません。一流大学出身者で「あの人のこういうところが凄いなー」と思うことは幾度もありましたけど、尖っている人が多かったのか、総合的にすごいイメージはありませんでした(だからそういう人たちの起こした問題を尻拭いすることが多かったわけで)。
社会人における評価と言うのは、そこで
何を得て、何が活かせているのか?
何を活かして、どのような成果を出せるのか?
が重要で、どんなに頭の回転が速いかとか、どんなに記憶力が優れているかは、結果を出すためのファクターになることはあっても、結果として残せない以上、それ自体が評価の対象になることはありません。そうした地力とその地力に基づいた結果こそが全てなのです。
当然、結果だけではダメで、必ず実力が伴っていなければなりません。運任せの場合、「運も実力のうち」と言う人もいますが、常に運がいい人というものがいない以上、運が悪い時に大きなプロジェクトを任せると会社を傾かせかねないからです。
何でも頭に詰め込むのは、メモリの無駄遣い

そもそも人間の脳と言うのはエビングハウスの忘却曲線でも提起されているように、覚えたものはかなりの速度で忘れるようにできています。忘れにくくすることは出来ても、「100%忘れない脳」と言うのは作ることが出来なくなっています。
そんな脳のために、無理やり色んな事を詰め込んで記憶するのは、メモリの無駄遣いであり、そのためだけに暗記する努力をする時間は人生の無駄遣いです。
コンピューターを見てもわかると思います。
ハードディスクがあって、メモリがあって、CPUがあります。メモリの役割は、「毎回ハードディスクから読み取ろうとすると、時間がかかるので、頻繁に読みだす情報はメモリに置いて、速度向上を図ろう」と言うものです。逆に言えば、頻繁に読みださない情報はハードディスクに入れておいた方が効率がいいのです。
よく、机の上に広げてすぐに作業に取り掛かる情報(メモリ)と、後で取り出すために引き出しにしまう情報(ハードディスク)なんて例で説明されますよね。
私たちのビジネスの現場においては、
メモリ :記憶
ハードディスク:記録
とイメージしてみてください。記録には、紙、電子ファイルはもちろん、Webサイトでもいいでしょう。そうしたものを駆使すればいいだけです。
よって、全て頭に詰め込もうとするのは止めましょう。新人の時に、よく「メモをとれ」と言われるのも、そのためです。所詮、人間はそれほど完璧にはできていないものです。稀に「なんでそんなことも覚えてないんだ!?」と怒鳴りつけている親や上司などの話を聞きますが、これは本末転倒です。そういう記憶に頼ろうとする人ほど、覚えることが多すぎ、大抵記憶力が浅くなって、すぐにボロが出ます。
こと、社会人になってしまえば、ノートやメモを取ることも強制しません(取っても構いません)。取っておけば、いちいち記憶に頼る必要もなく、あとでカンニングし放題で、しかも学生時代と違って、カンニングしても怒られるどころか、カンニングしたおかげで成功を納めたら褒められるというオマケまでついてくるだけです。
メモリ(記憶)の使い道
但し、当然と言えば当然ですが、全てが「忘れて良いことか?」と言うと、そう言うわけではありません。やはり最低限覚えていてもらいたいことはあります。それは
• INDEX(目次)
• あらすじ(本質)
この2点だけは可能な限りおさえておきましょう。
INDEXとは、"どこを見れば書いてあるか"、"誰に聞けばわかるか"と言う目次のようなものです。これだけ覚えておけば、あとは外部記憶装置(本、インターネット、他人の記憶、等)を利用することで、多くの問題は解決します。
あらすじとは…そうですね「要約したタイトル」と考えてください。私たちソフトウェアエンジニアリングの世界では、障害管理/バグ管理をする際につける個票タイトルが、これに該当します。
たとえば、
ある数値項目に"0"を入力し、登録ボタンを押下した時、〇〇処理の中でゼロ除算が発生し、システムエラーとなった。この時、エラー処理が記載されていなかったために、システムエラーそのものが画面に出てしまった。
と言った欠陥があったとします。「ゼロ除算」させてはいけない仕様なのか、それとも「エラー処理」が存在しないことがいけない仕様だったのか、あるいはその両方かはわかりませんが、要約すると
「ゼロ除算時のシステム例外がそのまま現れ、処理が進まなくなった」
となります。これがあらすじです。実際に記憶にとどめておくのはもっと短くてもいいでしょう。キーワードでもかまいません。INDEXと一緒に紐づけて記憶しておけば、いざ必要になった時にハードディスクに問い合わせればいいだけなのです。
メモや記録なら「内部ハードディスク」、他人、本やWebなら「外部ハードディスク」と私は呼んでいます。
そして、そのINDEXすら忘れそうになったら反復して過去の記憶を呼び覚まし、常に再認可能な状態にしておきましょう。そうすれば、いざと言う時に「あ、これ聞いたことある」という閃きから、何を確認すればいいか?が判るようになるはずです。さらに"思い出す"と言う反復を繰り返せば、覚える気が無くても身体が勝手に沁み込むように覚えてくれます。
とはいえ、それだけでは少し不足です。
先ほど、メモリとハードディスクの違いを説明しましたが、やはり頻繁に利活用する喫緊の情報は極力取り出しやすいようにメモリ側に蓄えておいた方がいいでしょう。ですが、1日に1度も用いないような情報であれば、さっさとハードディスク側に記録した方が、負担は少ないと思います。
これによって、脳内メモリを無駄に消費することが無くなり、より効率的な作業が進められるようになるでしょう(稀に何でも記憶できている宇宙人みたいな人がいますが、一部の天才気質の人だけが可能なので参考・模倣の対象にはなりません)。
いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。
