
Daily Success Builders 2023-11-07
【トレンド最前線】
トレンドとは、時代の趨勢、潮流、流行のことです。ファッション、マーケティング、経済動向分析などの分野でよく使用されます。トレンドには、短期的なものから長期的なものまでさまざまなものがあります。短期的なトレンドは、数週間から数ヶ月で変化し、長期的なトレンドは、数年から数十年で変化します。トレンドは、さまざまな要因によって形成されます。経済状況、社会情勢、技術革新、文化的変化などがトレンドの形成に影響を与えます。
トレンドを把握することは、ビジネスやマーケティングにおいて重要です。トレンドを把握することで、消費者のニーズや価値観を理解し、適切な商品やサービスを提供することができるからです。本稿ではトレンドの最前線をお伝えします。
SNSでバズったものはトレンドになる?
SNSは、多くの人が気軽に情報発信や情報共有ができるプラットフォームです。そのため、SNSでバズったものは、多くの人に短期間で認知され、拡散される可能性があります。
また、SNSは、人々の興味や関心を反映しやすいプラットフォームです。そのため、SNSでバズったものは、人々の興味や関心を刺激し、トレンドになる可能性が高いと言えます。
実際に、近年では、SNSでバズったものがトレンドになる事例が多く見られます。
例えば、2022年には、TikTokで「#シンエヴァ」というハッシュタグが流行し、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が再び注目を集めました。また、2023年には、Twitterで「#ウマ娘」というハッシュタグが流行し、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」が人気を博しました。
もちろん、SNSでバズったものが必ずしもトレンドになるわけではありません。しかし、SNSはトレンドを形成する上で重要な役割を果たしており、SNSでバズったものはトレンドになる可能性が高いと言えます。
SNSでバズるためのポイント
インパクトのある内容や表現
共感や共感を生み出す内容
拡散しやすい内容
これらのポイントを押さえてSNSで発信することで、バズる確率を高めることができます。
2024年にSNSでバズりそうなもの

TikTokやYouTube Shortsなどの短尺動画
TikTokやYouTube Shortsなどの短尺動画は、2023年も引き続き人気を博しており、2024年もバズりコンテンツの中心となるでしょう。短尺動画は、視聴者の注意を引きやすく、シェアもしやすいため、バズりやすいという特徴があります。
インフルエンサーによる情報発信
インフルエンサーによる情報発信は、2023年も多くの人の注目を集めました。2024年も、インフルエンサーによる商品やサービスの紹介、トレンド情報の発信などがバズりやすくなるでしょう。
サステナビリティや社会貢献に関するコンテンツ
サステナビリティや社会貢献に関するコンテンツは、2023年も注目を集めました。2024年も、環境や社会問題に関する意識の高まりから、これらのコンテンツがバズりやすくなるでしょう。
VRやARなどのテクノロジーを活用したコンテンツ
VRやARなどのテクノロジーを活用したコンテンツは、2023年も徐々に普及し始めています。2024年には、より多くの人がVRやARを体験できるようになり、これらのテクノロジーを活用したコンテンツがバズりやすくなるでしょう。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
TikTokで流行した「#〇〇チャレンジ」などのハッシュタグキャンペーン
YouTuberが紹介した商品やサービス
インフルエンサーが行った社会貢献活動
VRやARを活用したゲームやエンタメコンテンツ
もちろん、バズるかどうかは、コンテンツの内容やタイミングなど、さまざまな要因によって決まります。しかし、上記のようなトレンドを押さえておくことで、バズりコンテンツを作り出す可能性を高めることができるでしょう。
バズらせる方法とは
インフルエンサーが使っているバズらせる方法は、大きく分けて以下の3つです。
トレンドを押さえた投稿
SNSでバズる投稿は、多くの場合、トレンドを押さえたものです。そのため、インフルエンサーは、常にトレンドをチェックして、それに合った投稿をするように心がけています。
共感を呼ぶ投稿
人は、共感できるものに惹かれる傾向があります。そのため、インフルエンサーは、自分の経験や考えを率直に語ることによって、共感を呼ぶ投稿をするようにしています。
拡散を狙った投稿
バズらせるためには、拡散が重要です。そのため、インフルエンサーは、ハッシュタグやタグ付けなどの機能を活用して、拡散を狙った投稿をするようにしています。
具体的な例としては、以下のような投稿が挙げられます。
流行している言葉やフレーズを使った投稿
身近な話題や体験談を語った投稿
芸能人や有名人とのコラボ投稿
視聴者参加型の投稿
また、インフルエンサーは、バズらせるために、以下のような工夫もしています。
定期的に投稿して、ユーザーの目に留まるようにする
投稿の質を高めて、ユーザーの興味を引きつける
フォロワーと積極的に交流して、親密な関係を築く
もちろん、バズらせるのは簡単なことではありません。しかし、上記のような方法を参考にすることで、バズらせる可能性を高めることができます。
以下に、インフルエンサーがバズらせるために行っている具体的な施策をいくつかご紹介します。
トレンドの音源やハッシュタグを活用する
TikTokでは、トレンドの音源やハッシュタグを活用することで、より多くのユーザーにリーチしやすくなります。
視聴者参加型の企画を行う
ユーザーが参加できる企画を行うことで、ユーザーのエンゲージメントを高めることができます。
インフルエンサー同士のコラボを行う
同じジャンルで活躍するインフルエンサーとコラボすることで、より多くのユーザーにリーチすることができます。
PRを活用する
企業からPRを依頼してもらうことで、より多くのユーザーにリーチすることができます。
バズらせるためには、どのような投稿がユーザーに受け入れられるのか、常にアンテナを張り巡らせることが大切です。また、トライアンドエラーを繰り返して、より効果的な方法を探ることも重要です。

ステマ規制とは
インフルエンサーがバズらせる時、ステマ規制に注意する必要があります。ステマ規制とは、2023年10月1日から施行された、ステルスマーケティング(ステマ)を規制する法律です。ステマとは、消費者に広告であると明記せずに隠した販促・宣伝行為のことで、SNSの普及に伴い、近年増加していました。
ステマ規制では、以下の2つの条件を満たす広告は、不当表示に該当し、景品表示法違反となります。
商品やサービスの提供する事業者による表示であること
事業者による表示であることを、一般消費者が判別することが困難であること
具体的には、以下のようなものがステマ規制の対象となります。
インフルエンサーや著名人に商品やサービスを無料で提供し、その感想や評価をSNSで発信してもらう
消費者に商品やサービスを無料で提供し、その感想や評価をブログや口コミサイトで投稿してもらう
商品やサービスのレビューを偽装する
ステマ規制の対象となった場合、事業者には以下の罰則が科される可能性があります。
2年以下の懲役または300万円以下の罰金
または、その両方
ステマ規制の目的は、消費者が商品やサービスを適切に判断できるようにし、消費者の利益を守ることです。
ステマ規制の導入により、SNSやインターネット上での広告表示がより透明化し、消費者がより適切な情報に基づいて商品やサービスを選べるようになることが期待されています。
ステマ規制がインフルエンサーに与えた影響
ステマ規制は、インフルエンサーに以下の3つの影響を与えました。
広告であることを明確に表示する必要がある
企業からの依頼内容をより慎重に検討する必要がある
消費者の信頼を維持する必要性が高まる
1. 広告であることを明確に表示する必要がある
ステマ規制では、広告であることを明確に表示しない限り、不当表示に該当し、景品表示法違反となります。そのため、インフルエンサーは、商品やサービスの紹介を行う際には、必ず「広告」「宣伝」「PR」などの表記を明確に行う必要があります。
2. 企業からの依頼内容をより慎重に検討する必要がある
企業からの依頼内容によっては、ステマとみなされる可能性があるため、インフルエンサーは、企業からの依頼内容をより慎重に検討する必要があります。具体的には、以下の点に注意する必要があります。
広告であることを明確に表示する必要があるか
商品やサービスの内容を正しく伝えることができるか
消費者に誤解を与える内容ではないか
3. 消費者の信頼を維持する必要性が高まる
ステマ規制の導入により、消費者は、インフルエンサーの投稿が広告であるかどうかをより意識するようになると考えられます。そのため、インフルエンサーは、消費者の信頼を維持するために、以下の点に注意する必要があります。
常に正しい情報を発信する
商品やサービスの内容を正しく伝える
消費者に誤解を与える内容は避ける
ステマ規制は、インフルエンサーの活動に一定の制限を課すものであり、インフルエンサーは、新たなルールを遵守し、消費者の信頼を維持していくことが求められます。
【昭和な毒舌コラム】
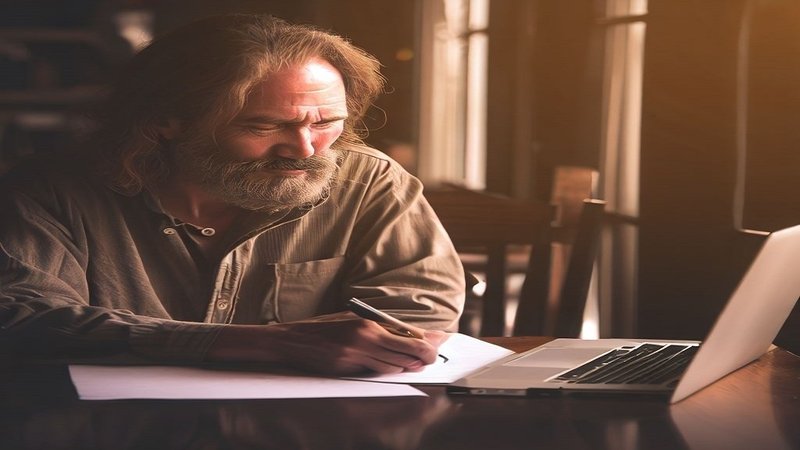
昭和生まれの俺は、最近の流行に追いつけなくて焦ってる。
TikTokやYouTubeで新しいトレンドが次々と生まれて、SNSであっという間に広がっていく。俺は、それらをリアルタイムで追いかけるのに必死なんだけど、なかなかついていけなくて……。
例えば、最近は「インフルエンサー」という言葉をよく耳にする。インフルエンサーって、SNSでフォロワーがたくさんいて、トレンドの発信者として影響力がある人のことだろ。
インフルエンサーは、ファッションやメイク、グルメなど、さまざまなジャンルで流行を生み出してる。俺も、インフルエンサーの投稿を参考にして、トレンドをキャッチアップしようとしてるんだけど、なかなかうまくいかないんだよ。
例えば、あるインフルエンサーが紹介してたメイク方法を試してみたんだけど、どうも似合わなかった。また、別のインフルエンサーがおすすめしてたグルメ店に行ったんだけど、俺の好みとは違った。
インフルエンサーは、フォロワーがたくさんいるから、トレンドを作り出せるんだろう。でも、その影響力が大きすぎるせいで、フォロワーがインフルエンサーの意見に盲目的に従っちゃうこともある。
俺は、インフルエンサーの流行を盲目的に追いかけるのではなく、自分の感覚を大切にして、自分にとって本当にいいものを選びたいと思う。
でも、昭和生まれの俺には、最新のトレンドについていけるだけの知識や感覚が欠けてる。そのため、インフルエンサーの流行に振り回されてしまい、自分のスタイルを見失っちゃうこともある。
それでも、俺はインフルエンサーの活躍を尊敬してる。彼らは、SNSという新しいプラットフォームを駆使して、新しいトレンドを生み出してる。
俺も、彼らのように、自分の感覚を大切にしながら、新しいトレンドをキャッチアップしていきたいと思う。
そのためには、まずはインフルエンサーの投稿をよく観察して、彼らのトレンド発信の仕方を学ぶ必要があるだろう。また、自分の感性を磨くために、さまざまなことに興味を持って、新しいことに挑戦していきたいと思う。
昭和生まれのおじさんとして、令和の流行に追いつくために、これからも努力していくつもりだぜ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
