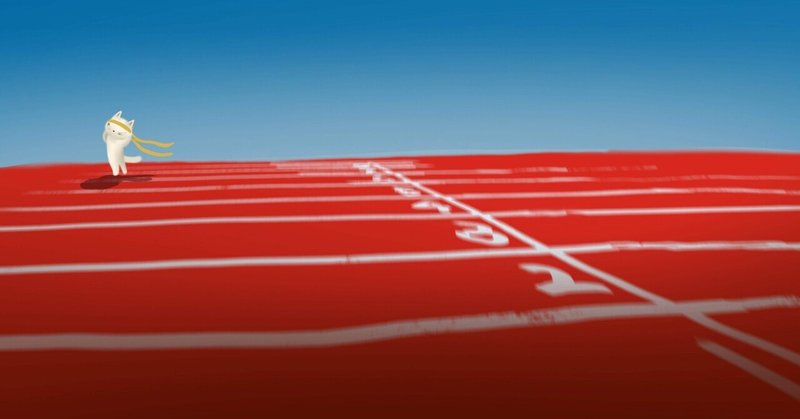
短編小説 「徒競走」
その日、中学校の徒競走でビリッケツになった。
小学校一年生の時から徒競走で負け知らずだった、僕は女の子から注目の的だった。小学校では足が速いやつか顔がかっこいいやつがモテた。僕は足が速いということでモテていた。体格も他と比べて大きいわけでもなく、頭もいいわけでもない。むしろちょっと悪かったかもしれない。
徒競走以外にサッカーもすこし得意だった。得意といってもフォワードを任されるような能力は僕にはなかったけど、そこそこチームには必要な存在だった。
毎年のバレンタインデーには、両手に抱えきれないほどチョコをもらった。友達は羨ましそうに指をくわえてみていた。チョコは甘苦くて好きじゃなかったから、友達の下駄箱にこっそり入れたりしていた、友達はそれを大きな声をだして喜んでいた、僕からのチョコだと知らずに。小学校がいつまでも続いてほしいと思っていた、女の子からモテて、一番になれる場所があって、もてはやしてくれる人たちがいて、雲の上でぷかぷか浮かんでいるような気分になれた。
中学校でも徒競走で無双してすごせる、小学校の延長戦と考えれば、この先どう考えても明るい未来しか待っていない。
実際は違った。中学校最初の体育で五〇メートルの徒競走があって、そこでいつものように走った。結果は三位だった。クラスで三位、学年だったら何位だったんだと頭に浮かんだ。一位とニ位は僕と別の小学校のやつだった、陸上をやっていたわけでもなく、二人とも小学校の徒競走では一位になったことはないといっていた。
僕は一位以外になったことがなかった。
小学校から同じクラスだった、鼻水の田中が手を叩いていた。消えていなくなれと祈った。普通考えれば走った者に対しての労いの拍手だ、だけど僕には手を叩いたやつが同じ土俵に来たこと出迎えの拍手に感じた。
部活は陸上部に入部した。もっと速く走りたい、一番を取り返したいから、それ専門に戦う戦士になりたかった。僕が一番だと証明したかった。だけど、入部早々に戦士になることは無理だと告げられた。僕は短距離に向いていないそうだ。長距離なら今後の練習とやる気次第だといわれた。僕もそう感じた、入部早々に五〇メートル走をやることになって、そこではビリッケツになった。僕と前の人とは二メートル差があった。すこし休んでもう一度走ったがやはり同じだった。
長距離はそこそこの結果が出た。全国大会でそれなりに戦えるといわれた。僕は短距離で一番になりたい、何十分も何時間も走るのはごめんだ。陸上部に籍を残したまま、部活をやめた。走るのはこりごりだった。勉強を頑張ろうと決めた、しかし、それもうまくいかなかった。成績が貼り出されて、みんなの笑いものになった。それから一週間調子が悪いといって学校を休んだ。
一週間休んだだけで授業についていくのが難しくなった。何もかもが崩れた、このまま谷底に落ちていくのが目に見えていた。もうどうすることもできない、そう思った。久しぶりに食べた給食が不味かった、味が薄く感じたんだ。小学校と同じメニューで同じ給食センターが作っているのに小学校の時と味が違っていた。
休み時間に鼻水をたらした田中がノートを持ってきた。
「いらない」と、僕は突き返した。授業の内容なら先生がまとめたプリントあったから、田中の哀れみなんか必要なかった。
「そうじゃないよ」と、田中がもう一度ノートを差し出した。「見てほしいんだ」ノートをよく見るとスケッチブックと汚いひらがなで書かれていた。
「見るから鼻かめよ」と、僕は受け取った。
一ページ開いた。
二ページ目も開いた。
「キモい」と、僕は正直な感想をいった。実際、キモかった、小学生の僕が必死な顔をして走っている絵が描かれていたからだ。それも、写真のように正確に精巧に。
パラパラめくると最後のページに中学生の僕が描かれていた、悔しそうに怒りがこもった表情で花壇に咲く赤いガーベラを引っこ抜いてる姿だった。
「最後が一番いい」と、僕はいった。「貰うよ、モデル代だ」そしてそのページをちぎった。
田中は笑っていた、かんだはずの鼻から鼻水がたれていた。
時間を割いてくれてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
