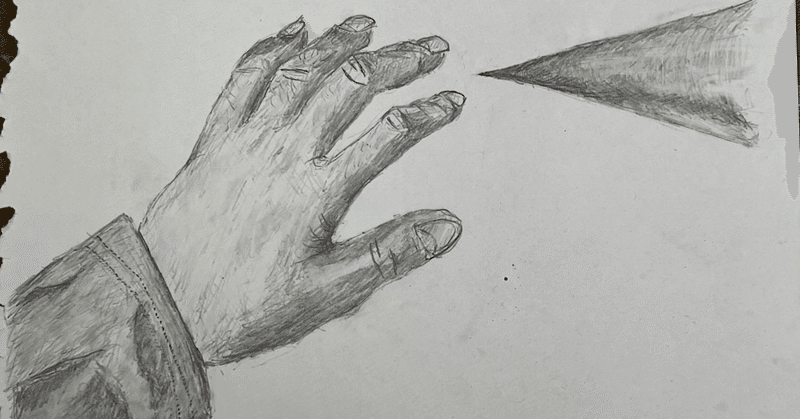
○拷問投票9【第一章 〜毒蛇の契約〜】
俗称としては、拷問投票法だ。正式な略称は、刑罰投票法である。法律そのものの正式名称としては、少々長いが、『積極的刑罰措置の実施にあたっての国民による投票等に関する法律』である。ちなみに、海外の研究者たちからは『Torture low』と呼ばれ、単に拷問法ということになっている。
いずれにせよ、この法律を構成する要素が大きく分けてふたつ存在していることは、前者三つの名称が示唆している。
すなわち、『拷問』と、『投票』の、ふたつの要素だ。
そのふたつの言葉から簡単に連想できるとおり、この法律は、投票によって拷問しようとするものである。
より正確に言うならば、凶悪犯罪者への刑罰としての拷問を実施するにあたって国民による投票という手続きを踏むものである。
それくらいのことは日本国民なら常識として誰でも知っている。日本国憲法を国民投票によって改正できることを誰もが知っているのと同様だ。しかしながら、具体的にどのような手続きに基づいて日本国憲法を改正できるのかについては一般的な日本国民でさえ深くは知らないのと同様に、拷問投票法の具体的な中身については、それほど周知されているわけではない。
現に、法学部を出ている佐藤でさえ、具体的な中身については無知であった。高校のときの社会科で、裁判員制度と一緒に最新の動向として勉強した記憶がうっすらと残っている程度である。
だからこそ、『実務のための刑罰投票法』を手に取らざるを得なかった。
まずは、『拷問』についての理解を深めなければならない。単に拷問と呼ぶならば、爪を剥いだり、電気ショックを与えたり、性的な恥辱を与えたりすることを想像してしまう佐藤である。
当然、そのような類の残虐な拷問を現代の法律で規定することはできない。そもそも日本国憲法には明文で『残虐な刑罰は禁止する』とあるので、その類の明らかな拷問は違憲評価を受けるに決まっている。
国民からは、死刑以上の厳罰を新たに新設すべきだという声が強まっていた。
国民と憲法によって板挟みされていたその狭間で、法律家たちは頭を悩ましていたわけである。
一部には、いさぎよく憲法を改正すればいいじゃないか、いまの世論なら改正することに困難はない、という声もあった。この声に対しては、国際人権団体からの批判をはじめとした国際的な圧力がかかり、ストップがかかったという事情があるらしい。
その中、拷問投票法の起案者である天才経済学者、山室真司は、憲法への配慮について苦心した挙句、『積極的刑罰措置』という新たな刑罰を提案した。
これは建前に過ぎないものの、身体への肉体的な拷問ではなく、精神の自由に対する制限という特徴を有している。このアイディアは現行の拷問投票法第二条において明示されている。
この第二条の言い分は、簡単だ。
この新たな刑罰は、拘禁刑の延長線上に位置するものであり、ただその対象が身体の自由ではなく精神の自由であるに過ぎない、というのである。誰でも自分の好き勝手に物事を考える自由を持っているが、そこに介入し、自分の好き勝手に物事を考えることができない状態にする。つまり、脳みその内部に介入することによって、脳みその中の自由を制限するという発想だ。
そのための手段として、第二条は医薬品を用いることを規定している。
条文ではかなり抽象的に規定されている。実際には、向精神薬市場で世界的なシェアを誇る日本の医薬品企業一社の開発した『アメーバ』の使用が想定されている。
この『アメーバ』は、統合失調症の幻覚や妄想を抑制する技術を応用して生み出されたもので、健常者に投与することによって激しい幻覚や妄想を生み出すことのできる医薬品である。マウスでの実験においては、投与後、一時間も経たないうちに錯乱状態に陥り、自らの頭部を壁にぶつけた末にそのまま絶命した。
防衛改革の一環で軍事利用のために開発されたという噂だが、機密事項に該当するため回答することはできない、と政府は説明している。
どうあれ、『アメーバ』の存在自体は、製造元の企業が当時から公表していた。特定企業の医薬品を法律内で指定することは避けるべきだとの考えから、同法第二条第二項ではわかりにくく規定したのだろう。同項の規定にあてはめるならば、『アメーバ』は、掲げられた各号のうちの第二号に該当するものだ。
精神の自由に対する制限だと言いながら、その実質は、精神的な苦痛を与えることを目的としている。
その実質を覆いかくすためにも積極的刑罰措置という柔らかい呼称を与えたり、執行ではなく実施だと呼ぶあたりにも、拷問投票法の性格の悪さが際立っている。
当然のことながら、司法はバカではない。精神的機能に障害を与えることは現行法上、傷害罪であり、これは考えるまでもなく残虐な刑罰だ。以上のような言い分で司法が納得するとは考えにくい。
しかしながら、そもそも立法経緯からして高度に政策的な法律なので、統治行為として司法判断を遠慮すべきではないかと期待されている。いまのところ、積極的刑罰措置が実施された例がないことも加担して、司法はだんまりを続けている。
