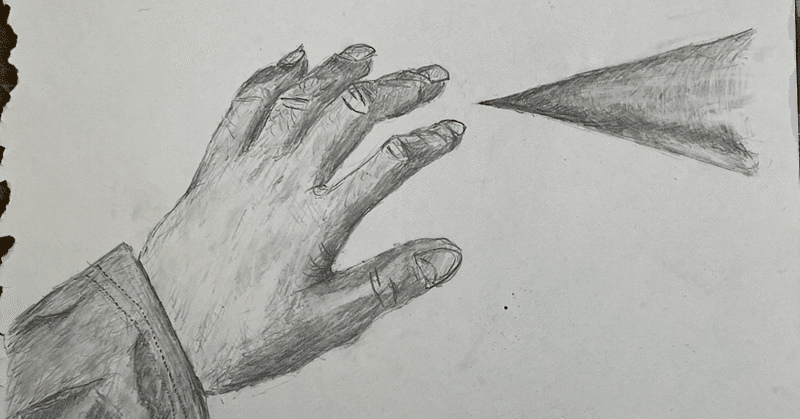
◯拷問投票184【第三章 〜正義と正義〜】
世間に利用され、決めつけられる痛みは、周りからは想像しにくい。ひとつの感覚として尊重すべきだとは思った。
だが、正直なところ、長瀬の胸には響いていなかった。
たしかに世間は残虐かもしれない。いつも正しいことを言っているが、口にする正しいことが口を動かす動機になっていない場合もある。なにか他の短絡的な動機があって誰かを責め立てたいときでも、自己中心的な言葉をそのまま口にすることはできない。あえて正しい言葉を選ぶことで、これは誹謗中傷ではない、これは悪ではない、と納得しながら気持ちを発散させる。
被害者遺族の気持ちというのも、使いやすい道具になることがある。
当事者からしたら、「被害者遺族の気持ちを考えると許せない」という世間の正しい言葉を聞いて、個人的なストレス発散のために自分たちの存在を利用された、と思えるのも不自然ではなかった。
それは長瀬もわかる。
しかし、実際のところは、どうなのだ。
世間など、ホントはどうでもいい。世間が我々を利用しているのではなく、我々が世間を利用しているのだ。大事なのは、我々がなにを求めているのか、である。その実際のところにこそ意識を集中させるべきなのだ。自分の気持ちを否定したって、苦しみが消えるわけではない。
「犯人を罰することを、望んでいないということですか?」
つい直接的な追及になってしまった。
「だから、そういうことではありません」
父親は、少し取り乱し、首を振った。
「わたしの心にも犯人への処罰感情はありますが、そういう人間になることについて、そういう人間だと見られることについて、そういう人間だと押し付けられることについて、わたしたちはもう耐えられません」
「それでは、一生、傷は癒えませんよ」
高橋実が、ちょっとだけ厳しい声を飛ばした。
「最後まで戦いましょう。わたしたちは戦うことでしか前に進めない。世間なんかに潰されている場合ではないのです」
同じ事件の被害者遺族である高橋実の言葉は重いはずだったが、それでも、坂田真奈美の父親は頑なだ。
「戦うことだけが傷を癒す方法なのかについては疑問がありますから、そう言われても難しいです」
「唯一の方法ではないとしても、ひとつの有効な方法ではありませんか」
「有効だったとしても、ひとりの人間に対して科学技術で苦痛を与えるという方法を選んでしまう人間だと見られたくはありません」
「奥さまは?」
坂田真奈美の母に、長瀬は、発言を促した。
「わたしも同じであります。戦うことで傷を埋めること、それをする人間になることは、夫と一緒で、耐えられませんでした」
こうやって仲間が離れていく。長瀬の胸では、いつからか幼い孤独感が強まっていた。すでに頑丈だったはずの活動の正当性が、内部から揺れている。忘れたはずだった疑いと恐怖が封印を解き放たれたかのように、ちらりと顔を出す。恨めしそうなその顔を、長瀬は、全力で押し返した。
――このふたりは、もう、ダメだ。
谷川が言っていたように、どんなに説得しても無理そうである。いかに強く背中を押したとしても、意思を変えることはないだろう。
「では、その点は、お互いに妥協しないことにしましょうか。むしろ重要なのは、文書のほうです」
長瀬は、彼らの意思を変えることは諦めて、せめて被害者文書だけは現在の形で残すように交渉を始めた。
不幸にも、そこでも、お互いに妥協することはできなかった。
話し合いは決裂し、被害者文書の継続的な掲載については、長瀬たちの権限で強行するしかなくなった。
