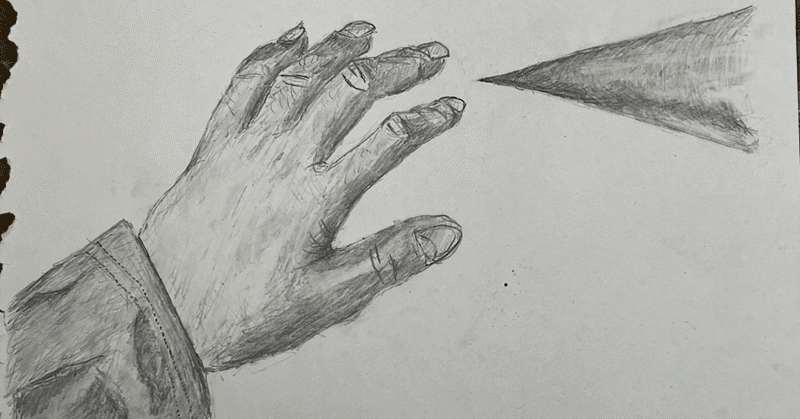
◯拷問投票191【第三章 〜正義と正義〜】
なんで、家族を殺されてきた我々が、まるで自分たちが犯罪者になるかのような気持ちの悪さを感じなければいけないのか。
坂田真奈美の両親だって、被害者だ。心の一部をえぐり取られた挙句、苦しい自制に甘んじることを余儀なくされた。
長瀬にはそれができない。高橋実と契約を結んだあのときから、引き返す道はなくなっていた。
もう、戻れない。戻りたくない。
悪いのは、制度そのもののような気もしてきた。
拷問投票制度さえなければ、拷問など目指さなかった。長瀬は、良心を維持しながら、まっとうに生きてきたつもりだ。見知らぬ強盗に妻を殺されるまで、人の苦しみを願ったことなど、なかった。手の届きそうなところに拷問のスイッチが用意されているからこそ、懸命に手を伸ばしている。
我々の正義は、拷問を正当化している。
拷問を否定する人たちのほうが野蛮だ、と感じてしまうのは、我々の正義が排他的なほどに膨らんでしまったせいだろう。
ああ。
……正義は重い。
長瀬の心に生じた小さな揺らぎは、波紋のように静かに広がっていた。理論武装で守ってきた本音がそのまま姿を現してきたような不快感がある。
長瀬は、自分の心から目を逸らすように、ぐっと力強く目を開いた。
路上に、立法形に切り取られた空間。かすかな振動もないから、どこかのアパートの一室のようだ。
自動運転の宣伝カー、その後部座席。
窓を見れば、舞台照明よりも熱い光にさらされ、頬を流れていく汗をうっとうしそうに歩いている若い女がいた。パープルのパンチパーマをした中年の男もいる。いろんな人がいろんな方向へ、いろんな歩き方で進んでいく。
どの人も、相変わらず、こちらに目を向けようとしない。宣伝カーそのものを見て見ぬふりしている。
拷問投票。
テレビやネット上では主要な話題のひとつだが、身近なところではタブー視されているのかもしれない。この重たい正義という荷物の一部を彼らの背にも負わせることの難しさを感じていた。
「この暑さだと、やはり、いつもより人出は少ないですか?」
長瀬は、隣で休憩していたウグイス嬢に声をかけた。ブライダル司会者を生業にしているという三十代の女性だ。
「そうですね。少ないです。屋内には、いるでしょうけど」
「訴えてきた感触としては、どうでしょうか。なにか手応えのようなものは、ありますでしょうか」
「それは正直、ブラックボックスみたいなところですね」
苦々しそうな顔をしてきた。そりゃそうだ、と長瀬は質問をしておきながらも思った。拷問に賛成か反対かについて本音を表に出している人は、そんなにいないだろう。投票の当日を迎えるまで、わからない。
かといって、なにも手掛かりがないわけでもない。
