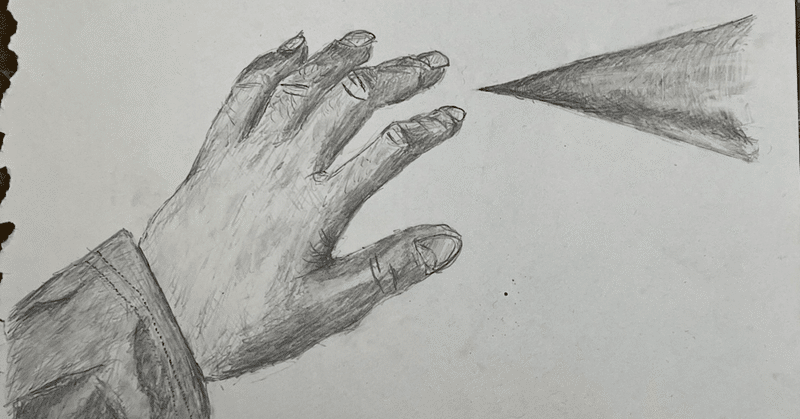
◯拷問投票195【第三章 〜正義と正義〜】
時刻は正午過ぎだった。
長瀬は、ひとり、人通りの少ない歩道脇で宣伝カーから降りた。汗をぬぐうためのタオルを片手に、一歩ずつコンクリートを踏みしめていく。
降り注いでいるのは、どこか金属的な鋭い日差しだ。ちょうど太陽が鎮座している方角との関係で、大きな街路樹も歩道の上に影をつくらない。放出されたものを全身で受け止めることになっていた。
なんと言えばいいのか。ぼろぼろの弦楽器が不協和音を奏でたような不快感がある。いまさっきまで冷房の効いていた宣伝カーでくつろいでいただけに、なおさら居心地の悪さが際立つ。ほとんど雨に対して傘をさすような発想で、日傘をさしたくなった。露出している首や顔や腕が熱いというより痛い。
少し歩いただけでも、汗があふれだした。
鼻の頭や唇の上に汗が浮かび上がってくるのを、イライラしながら、ぐいぐいとタオルで拭く。
曲がり角のむこうからは、ざらざらとした拡声器の声が不鮮明に聞こえている。
なんらかの事件というわけではない、とすぐに安心できるような、規則的な人々の叫び声も聞こえていた。
巨大な建造物の隅っこに形成されている曲がり角に近づくにつれ、耳にかかる負担が大きくなる。
長瀬は、足を止めなかった。躊躇することなく、曲がり角を左に曲がった。
視界に飛び込んできたのは、燃えるように魂を震わせている群衆だった。まだ彼らのいるところからは遠いが、騒ぎのリアリティーは増した。
東京高裁前の路上には、黄色と赤色の群衆がいた。拡声器を介して川島の力強い声が響いている。言葉の意味も、さっきよりは聞き取れた。
『我々は悪を滅ぼすことに酔いすぎている。いままでの人類の……中で繰り返されてきた戦いはほぼすべて、当事者たち……は正義の行使だった』
なにか壮大な主張をしている。ただの一時代の熱狂に過ぎない拷問投票制度を、人類の過ちと結びつけるわけか。
それって、本心なのか、と疑問に感じた。
群衆の声をよく聞くと、そうだ、そうだ、と賛成する声だけではない。バカバカしい、子供騙しだ、などとヤジも飛んでいる。イデオロギーを異にする集団が同じ場所に集まっているのだから、当然であった。
長瀬は、徐々に彼らのところへと足を進めつつ、ところどころ聞き取れない演説に耳を傾けた。まだ川島の姿そのものは見えない。
『我々は、常に、我々の正義を疑わなければいけないという……を負っている。いままでと同じように過ちを繰り返してはなら……。冷静に考えてみよう。本当に、個人は自由な存在だと言えるのか?』
突如、哲学的な話題が始まった。熱を込めて声量が増す。
