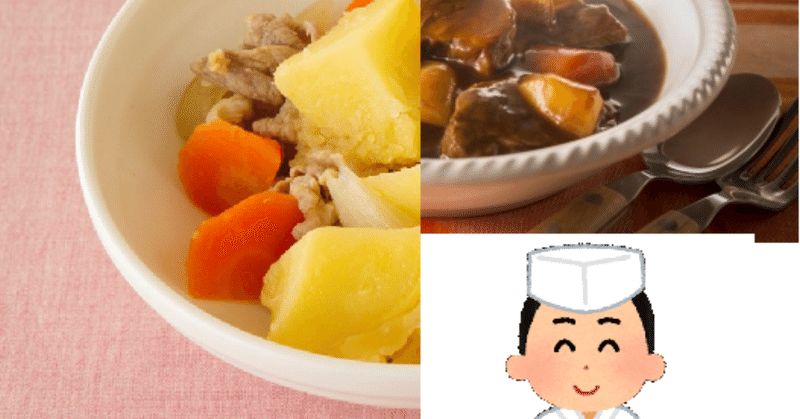
作る、食う、生きる――雑で楽な自炊への道。その③ 「料理」を覚えるとは何か?……俺たちは雰囲気で料理をやっている!
さて前回(作る、食う、生きる――雑で楽な自炊への道。その② 「料理」を覚える、三工程)の最後で「次は【調味】を覚える!」と言いましたが、その前にもう少し根本的な話をしましょう。
それは「料理を覚える」とは何か? ということです。
最終段階をどこに設定するかは個人がどこまで道を極めたいか……によって変わりますが、この『作る、食う、生きる』では最終到達点として(いいですか最終到達点ですから、これを聞いて「そんなん無理だぁ」と思う必要はありませんよ。そこには私でもまだ完全に達していないのですから)
「食べた料理を、作れる」
としたいと思います。
……とは言ったもののプロのシェフが提供する素晴らしい一皿を再現できるようになる!という話ではありません。
「あのとき食べたアレ、うまかったなぁ……こんな風?かな?」とまったく同じではなくても40点から80点ぐらいの再現度で作りあげ、「うん……うんうん、こんな感じこんな感じ」と【自分だけでいいから】(ここ重要)納得できるものを作れるようになる。というレベルの話です。グラビアアイドルがやる野原しんのすけのモノマネ、ぐらいのレベルで60点としています。
前回≪「レシピ」は覚えられても「料理」を身につけることにはならない≫と書きましたが、食べただけの料理には「レシピ」がありません。それでも「料理」を身に着けていれば完璧ではなくても、模倣ができるようにはなるのです。
そのために心構えとして覚えていて欲しいのは
・料理とは系統発展型のスキルツリーである。
・料理とは複合可能なスキルである。
という点です。
RPGのスキルツリーシステムを想像して貰うとわかりやすいと思います。
火の玉(敵一人に火属性の小ダメージ)の呪文が熟練度3レベルになれば
→火炎(敵複数に火属性の小ダメージ)の習得
→大火球(敵一人に火属性の中ダメージ)の習得
と発展していく。あるいは
ハヤブサ斬り(敵一人に優先順位を無視して最速攻撃、ダメージ倍率0.8倍)が熟練度3レベルになれば
→疾風斬り(敵全体に物理攻撃、ダメージ倍率0.8倍)の習得
→マッハ斬り(敵一体にダメージ倍率0.8倍で2回攻撃)の習得
というように拡張されていく。さらには
ハヤブサ斬り熟練度3レベル+火の玉熟練度3レベル=火炎斬り(敵一体に火属性と物理属性の攻撃)習得
料理の技術とはこれに近いものがあります。例えば「豚の小間切れ肉をフライパンで食べれるように焼く」ことを覚えたとしましょう。そうなれば「豚ロース薄切り」「豚バラ肉薄切り」を食べれるように焼けるようになります(もちろん、それぞれの肉に特性があるので最初は失敗するかもしれません。けれどもそこで「小間切れ肉との違い」を理解できれば次は大丈夫なハズです!)。
そうやって「豚肉に火が通った状態」がわかれば、そこからスキルツリーはさらに広がっていきます。
厚みが違う「厚切り豚ロースを焼く」
肉質が違う「牛小間切れ肉を焼く」
方法が違う「豚の小間切れを茹でる」
もちろん熟練度3レベルの「豚の小間切れ肉をフライパンで食べれるように焼く」と比べて、最初は上手くいかないと思います。それでも習得はできますし、何回か繰り返せば「豚の小間切れ肉をフライパンで食べれるように焼く」のと変わらない上手さになるでしょう。
さてここからスキル合成で「牛小間切れ肉を焼く」+「豚の小間切れを茹でる」=「牛の小間切れを茹でる」=おっ、牛丼が見えてきましたね? 「厚切り豚ロースを焼く」+「牛小間切れ肉を焼く」=「厚切り牛ロースを焼く」=ビフテキだ!おかあさん、きょうはビフテキだね!わぁーこんなお肉、何年ぶりだろう。おとうさんがいなくなる前だから……おかあさん?どうして泣きながら縄で輪っかを作ってるの?
といった具合に料理スキル発展していきます。少年の未来も発展するのかな?そうだといいですね!
なんにせよ、こういった形で「拡張できるスキル」と「スキル合成」を身に着けていれば「食べた料理を、作れる」は40点の完成度を目指すならそれほど困難ではありません。
例えば生まれて初めて「豚バラのしょうが焼き」を食べたとして(可能性低い例えだなぁ)、それを作ろうと思うなら
「豚バラ肉は旨いなぁ、太るなぁ」+「玉ねぎをスライスして一緒に調理してる、甘い、おいしい」+「味付けは醤油と砂糖?がメイン……まぁ恐らく酒と塩も使っているだろう、照りは無いしみりんではないかな?」+「このスパイスはショウガか、なるほどこれで臭いを消してるんだな」+「てことは漬け置きしてるかもなぁ」=合体!「豚と玉ねぎのジンジャー煮込み」!ダメー!といった感じで、コイツが「フライパンで焼く」というスキルが抜けていたばっかりに失敗するわけですが、まぁそれでも「なんか違うけど、それっぽいしうまいうまい」ぐらいのものはできるでしょう。
これが私の思う「料理を覚える」ということです。そう言われれば≪「レシピ」は覚えられても「料理」を身につけることにはならない≫というのがわかってもらえるでしょうか。
料理が出来る人に「得意料理って何?」と尋ねて、微妙な顔を返された経験があるでしょうか? あるいは「結構料理とかしますよ」と言ったところに「へー、得意料理ってあるの?」と聞かれて答えに窮した経験が。その理由がここにあります。
家庭で行う範囲で「料理できるよー」というのは、いま上げたように「基礎的な料理スキルを複数身に着けて、それを組み合わせることができる」を意味します。一方で「得意料理」とはつまり「レシピ」のことです、そう!我々には本来「レシピ」など無いのだ!ぜんぜんわからない、俺たちは雰囲気で料理をやっている!
でも家庭は名物料理のあるリストランテでも、完璧なコースが求められるグランメゾンでもないのです!
疲れて帰ってきたら白飯にイカの塩辛を乗せてお湯かけて食う!ちょっと柚子の皮を削って散らせば料亭風!キュウリのキューちゃんがあれば野菜も食ったことになる!100点!が許される場所であり、いつも望む食材/望む環境/そして何より望む技術があるわけではなぁい!
だから「雰囲気でやる」という柔軟性こそが、家庭料理の神髄であると私は言いたい。
……そう、だからね、関係ない話するけど、私も何度か「得意料理は何?」って聞かれて困ったうえ、「あぁいま口から出まかせに料理が得意と言ったと思われてるぅ!違うっ違うんです!だってだって「一番得意なのはニンニクの芽を弱火で香りを立てながら、適度なタイミングで強めの中火にしてベストな焦げ目をつけることです!」って言われても、あなたが困ると思って!うぅぅ……できるんですぅ、本当なんですぅ……」と落ち込んだ末に発見したんです。あれね「作ってるとテンション上がる料理」を答えればいいんですよ。作ってて楽しい料理、自分の自信あるスキルが使える料理、それを答えるのが正解だったんです。
まぁ「えー、豚とニンニクの芽の中華炒めかなー」ではモテからは遠いけどな!ファック!
最後に
私がこの「料理を覚える」とはこういうことだと気づいたのは、あの有名な逸話
「明治時代。東郷平八郎が材料だけを渡し、和食の料理人にビーフシチューを作れと命じて出来上がったのが、肉じゃがのはじまり」
からです。
話の真偽はよくわかりませんが、何となくその料理人が何を考えてどうしてそうなったのかはよくわかる気がしませんか?
その板前のスキルツリーにはフォン(洋食の出汁)もドミグラスソースもバターも赤ワインもありません。彼の頭の中では「牛肉は料理したことは無いが同じ肉、恐らくかしわ(鶏肉)と同じでいいはずだ。ジャガイモにんじん玉葱がゴロゴロと煮込まれていると東郷殿は言っていた……すると具を大きめに切った筑前煮と似たようなものだろうか。西洋の”しちゅう”なるものは匙で食い、汁気が多いと聞く。ならば酒としょう油を多めにして……ふむ牛鍋の西洋野菜煮のようなものか、なぁに西洋とはいえ人が食うもの、大して変わりはあるまいて」といった思考が行われていたのでしょう。
そう肉じゃがもまた「雰囲気」によって作られたのです。
さて今回は導入にするだけのつもりが、思いのほか長くなってしまいました。
次回こそは【調味】を覚える編、やっていきます!
→やれませんでした。【作る、食う、生きる――雑で楽な自炊への道。その④たまごを、信じるな。】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
