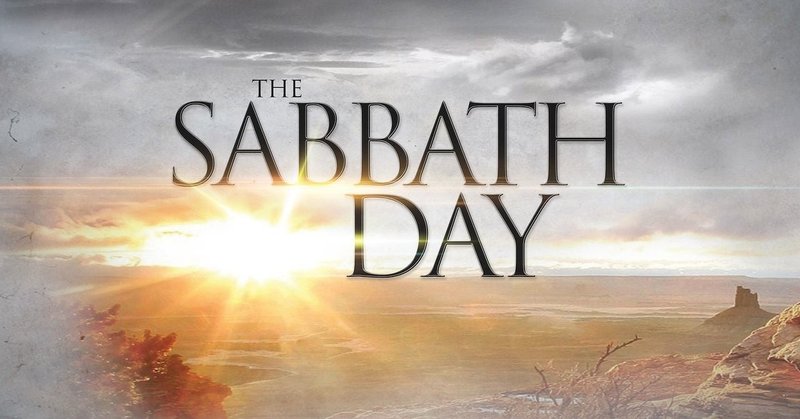
神の聖なる日-5 安息日と救い(安息日を守らないと救われませんか?)
囲いを好む羊
羊は、羊飼いがめぐらした木の囲いの中にいる事を好みます。なぜなら、そこが自分にとって一番安全な場所だからです。羊は自分を閉じ込めた囲いに対して不平を言うより、むしろ自由を味わい喜んでいるようです。
私たちクリスチャンも同じように、自分の心と生活を安全に守ってくれる垣根である律法や戒めを、絶対に煩わしいとは思いません。「神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ることである。そして、その戒めはむずかしいものではない」(ヨハネの第ーの手紙5:3)というみ言葉の通りです。
ところが、神を愛するといっている多くのクリスチャンが、罪を放棄するように導く律法の要求を、煩わしい束縛だと思っています。神様の戒めを守るなら、自分の人生は楽しみや喜びを味わうことのできない、乾いた砂漠のようになってしまうのではないかと心配するのです。そのように考えるクリスチャンは、本当に悲しむべき存在だと言えます。魂の真の牧者であられるキリストが、ご自分の羊を保護するためにめぐらして下さった囲い、すなわち、十戒に対して不平不満をもらす人は、いまだに、自分自身がオオカミの本性に支配されていることを知るべきなのです。オオカミが羊のような生活を要求されるなら、オオカミはどれほど自分の状態に対して不平不満を持つことでしょう。ですから、預言者イザヤは、オオカミのような人たちに対して、次の叱責を記録しています。「いま行って、これを彼らの前で札にしるし、書物に載せ、後の世に伝えて、とこしえにあかしとせよ。彼らはそむける民、偽りを言う子ら、主の教を聞こうとしない子らだ」(イザヤ書30:8,9)
律法の下にではなく恵みの下にあるとは?
私たちはしばしば、次のような発言を耳にします。「私たちは“律法の下”にあるのではなく、“恵みの下”にあるのでこれ以上十戒を守る必要はありません」と。これは、正しい見解でしょうか?律法の下にあるのではないという意味は、私たちが、もうこれ以上律法を守らなくでもよいという意味でしょうか。使徒パウロが、律法の下にあるのではなく恵みの下にあると言った時、クリスチャンは、神様の律法を公然と、意識的に犯してもよいと言ったのではありません。使徒パウロが語った内容の全体を、もう一度よく見ると「なぜなら、あなたがたは律法の下にあるのではなく、恵みの下にあるので、罪に支配されることはないからである。それでは、どうなのか。律法の下にではなく、恵みの下にあるからといって、わたしたちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない」(ローマ人への手紙6:14,15)と言っています。
子供でも分かる内容だと思いますが、律法は廃止されたという先入観のために、この言葉の意味を誤解してしまっているのです。この言葉が意味するものは何でしょうか?パウロは、「律法の下にあるのではなく恵みの下にある」と言ったあとですぐに、「それでは、どうなのか?」という言葉を付け加えています。これは、「それをどのように理解するべきか?」と言う問いかけであり、「恵みの下にあるからといって、私たちは律法を破って罪を犯してもよいのだろうか。断じてそうではない」とパウロは答えを出しているのです。このようにしてパウロは、クリスチャンが恵みの下にあるからといって、それが律法を犯しても良いという許可証ではない事を強調しています。
律法に対するパウロの態度はどのようなものだったでしょうか。「このようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しく、かつ善なるものである」(ローマ書7:12)。パウロによると、律法にはどんな問題もありませんでした。それは聖で、善でした。律法は、神の国の根本的な道徳の標準を表したものです。それは、天の政府の永遠の原則です。それは、善と悪を規定し、聖と俗を区別します。
ローマ人への手紙7章7節には「わたしたちは、なんと言おうか。律法は罪なのか。断じてそうではない。しかし、律法によらなければ、わたしは罪を知らなかったであろう」とあり、また同じローマ人への手紙3章20節では「律法によっては、罪の自覚が生じるのみである」とあります。
律法の役割は、神様が良しとされる正しい生き方を教えるものです。しかし人間は罪を持っているために、この神様の律法に、心から従うことはできなくなってしまいました。そのために神様は、キリストをつかわして、人が律法に従うことができる、新しい心と新しい力を受けることができる道を開かれたのです。その素晴らしい恵みを受け取る手が信仰なのです。
「すると、信仰のゆえに、わたしたちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえって、それによって律法を確立するのである」(ローマ書3:31)。パウロはここで明白に、信仰によって律法を確立していくことを述べました。神様の恵みは、律法を無効にして廃するものではなく、律法の要求を満たして確立するものです。そして、このことを信頼するのが信仰なのです(ヘブル11:1参照)。
それでは、「律法の下にあるのではなく」とはどのような意味でしょうか?ローマ人への手紙3章19節では、次のように説明しています。「さて、わたしたちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法のもとにある者たちに対して語られている。それは、すべての口がふさがれ、全世界が神のさばきに服するためである」。ここでパウロは“律法の下にある”ことを“裁きの下に”いることと同一視しています。つまり、律法の下にいる者たちとは、律法を犯したことによって、神様から審判を受ける者たちを言うのです。“律法の下に”いるというのは、自分の力と努力、自分の行いと功績を通して自分を救おうとする事を意味します。もちろんパウロは、そのような事は不可能であると宣言しています。(ローマ3:23~28)。パウロによれば、この世界には、二つの制度があり、一つは“律法の制度”であり、もう一つは“恵みの制度”です。律法の制度は、人間が救われるための義の標準を示しますが、それに従う力は与えません。恵みの制度では、主イエス・キリストを通して過去の罪に対する赦しと、現在のための力が同時に与えられます。
真のキリスト者は律法の下にあるのではなく、恵みの力の下にあります。彼らは、神様のおきてを犯すような生涯を過ごすのではなく、天の父なる神様が下さる恵みを通して、律法に従い罪に勝利する生涯を送ります。それゆえに、パウロは断固とした口調で次のように言っています。「なぜなら、あなたがたは律法の下にあるのではなく、恵みの下にあるので、罪に支配されることはないからである」(ローマ人への手紙6:14)。恵みの下にあるクリスチャンは、決して故意に主のおきてを破ることはありません。(ここでの故意にという意味は、天の父なる神様のみ心と真理が何であるかを、知的に良心的にはっきりと理解していたにもかかわらず、意図的に故意に不服従な態度をとることを表し、ついうっかり間違ったり、失敗したりすることではありません)。
以上の事を理解されたなら、神様の恵みの下にあるから安息日に対する戒めに従う必要はなくなったという議論は、間違いであることがお分かり頂けると思います。それは、「殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人について、偽証してはならない」という他の十戒の戒めを無くす事は出来ないのと同様です。恵みによって救われた人は、喜んで聖書の教えに従いたいと思うように心が変えられ、十戒のすべての戒めを愛するようになります。そのような人が、他の九つの戒めを愛して従いながら、安息日の戒めだけは、他の日に変えてもいいのだという態度をとることはできないはずです。
恵みにもとづく信仰の従順
これから私たちは、罪から救われる秘訣を研究していきたいと思います。パウロは律法を守り、罪の力から救われる秘訣を次のように説教しています。「愛は隣り人に害を加えることはない。だから、愛は律法を完成するものである」(ローマ13:10)。ところがある人は、この聖書の箇所を指摘して、“お互いに愛さえあればよいのだ!戒めはこれ以上必要ない”といいます。しかし、パウロによれば、愛は律法を廃止するものではなく、むしろ、それを通して律法を完成するものだと言っています。「愛は律法を完成する」という意味は、愛と罪は当時に存在する事は出来ないということです。もし愛が、私たちの生涯のあらゆる動機と思いと行動を支配するならば、私たちは律法と完全に調和した生き方をするようになるということです。
ヤコブがラケルを愛するゆえに、彼女を妻として迎え入れる条件として、7年という長い期間を彼女の両親のために働くことを約束したように、私たちがイエス様を真に愛するならば、私たちのあらゆる言葉と行いが、イエス様を第一としていくことでしょう。私たちの愛情も関心も、その方を中心としていくことでしょう。イエス様が好まれるものは何かということに最高の関心を傾けるようになり、その方が喜ばれない事は絶対にしないという思いが自然に生じるのではないでしょうか?さらに、私たちの救いのために命をも捧げてくださったイエス様の愛と犠牲を思い起こすなら、その方が言われることはどんなことであっても、喜んで果たしたいと願うようになるはずです。
十戒に服従する行為は、心の中にある純潔な神様への応答なのです。愛は、私たちに戒めを守らせるための強力な力です。神様への愛が、み業を行うための動機となります。それゆえ、パウロは救いについて、「あなたがたの救われたのは、実に、恵みにより、信仰によるのである。それは、あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である」(エぺソ2:8)と結論づけたのでした。
愛と律法の関係についての正しい理解
「律法の全体は、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ』というこの一句に尽きるからである」(ガラテヤ5:14)。神様の十戒を一言でまとめるなら、それは、“愛せよ”ということになります。なぜでしょうか?神様はご自身の律法である十戒を、自ら二つの石の板へ書き記してくださいました。最初の石の板には、神様と人間との愛が四つの戒めとして書き記され、二枚目の石の板には人間同士の愛が、六つの戒めとして書かれていました。神様を心から愛する者は、神のほかに、他のなにものをも神とせず(第一条)、刻んだ像を造らず(第二条)、主の名をみだりに唱えないで(第三条)、安息日を覚えてこれを聖として守る事でしょう(第四条)。同じように、隣人を真に愛する者は、人間関係についての残りの六つの戒めを、自然に守るようになる事でしょう。そして、心の中に真の愛を所有している人は、神様のおきてを守る事には、どのような苦痛も感じません。なぜならば、それは、あまりにも当然で、自然なことだからです。
ある神学校で、神学の教授が学生たちに講義をしている時、ひとりの学生が次のような質問をしました。
学生:「先生、先生は、殺してはならないという戒めをご存じだと思います」
教授:「それは、良く知っているよ」
学生:「それでは、先生は、奥様を殺さないようにするために、一日どれほど決心しますか?」
教授:「わたしは全然そのような決心をしませんよ」
学生:「それでは、奥様の物を盗んではならないという戒めを守るために、とれほど努力されますか?」
教授:「全然、努力は不要だよ」
学生:「私はこれまで、真実なクリスチャンになるために、毎日非常な努力をしている、という人にたくさん会ってきました。ところが、先生は、奥様に対する戒めを守るために努力もしなければ、全然苦しくもないと言われましたが、それはなぜですか」
教授:「私は家内を心から本当に愛しているからだよ!」
この簡単な例話は、「すべてのいましめは、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ』。これより大事ないましめはほかにない」という聖句の意味をよく説明していると思います。あらゆるクリスチャンにとって、とても大切な原則は、次のようなものです。“あなたが、自分自身より天の父なる神様を愛するなら、決して神様のみ旨に逆らう罪を犯さないことでしょう。もろもろの罪の根源は、自分を愛する事にあります。私たちが、主の恵みを通して自我を否定し、それを十字架に釘づけ、イエス・キリストを心に受け入れるなら、常に勝利は私たちのものになります。私たちが、私たち自身よりキリストを愛するなら、どのような状況にあっても、神様の戒めに従うことができるようにされます。愛は、あらゆる親切と寛大な心の根拠であり、犠牲の原動力です。”
「神はそのひとり子を賜ったほどに、この世を愛して下さった」(ヨハネ3:16)。ご自分のみ子さえも下さった事実を覚えておくべきです。神様の愛が罪人の心に刻まれるとき、罪人はついに、滅亡から永遠の生命へと移されます。いったい誰が、愛する者に対して、裏切るようなことができるでしょうか。
新しい戒めの誤解
皆様の中には、“イエス様が、新しい戒めとして、互いに愛し合いなさいという戒めを下さったので、文字としての律法や十戒はこれ以上守る必要がなくなりました”という話を聞かれたことがあるかもしれません。確かにイエス様は、弟子たちに「互いに愛し合いなさい」という新しい戒めを与えられました(ヨハネ13:34)。では、イエス様が言われた新しい戒めとは、何が新しいのでしょうか。これは今までなかったものが、新しく付け加えられたのでそう呼ばれたのでしょうか。この問題に対する正しい理解が、現在のキリスト教会に広がっている誤解を解く鍵になると思われます。
実は、イエス様が誕生される数千年以前から、旧約聖書の中に、すでに“自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ”という律法の根本的な精神が教えられていました。ところが、ユダヤ人たちは、本来の律法の精神を見失い、その意味をゆがめ、形式的でめんどうな規則にしてしまいました。外側の形だけを厳格に守ろうとする、律法主義が広まっていた時代に、イエス様は来られたのでした。イエス様は、ご自分が与えられた律法の本当の意味と守り方を、人々に教えながら、人々が戒めに対して持っている誤解を解いていかれました。そして、律法を守ることのできる唯一の道を彼らに教えようとされました。イエス様は、愛こそが、ご自身の律法に従うことのできる力であることを伝えられました。そこでイエス様は、公生涯の最初に、山上の説教において、愛と慈悲と柔和の教訓を語られたのです。
そのとき、キリストの説教を聞いた多くのパリサイ人や律法学者たちは、非常に驚きました。それは、キリストの教えが、彼らが今まで人々に教えていたものとは大きく違っていたからです。イエス様は、長い間ホコリの中に埋もれて見えなくなっていた、律法の根本原則の泥を払いのけ、光り輝く全く新しいものとして、律法の精神を人々に紹介されたのでした。そして、戒めを真実に守るための秘訣として、神様の愛を人々に伝えていかれたのです。人々が、「愛に根差し、愛を基として生活する」(エペソ3:17)ようにイエス様は教えられ、ご自身の律法を「互に愛し合いなさい」という、人々がこれまで聞いたこともない新しいものとして紹介されました。
「愛する者たちよ。わたしがあなたがたに書き送るのは、新しいいましめではなく、あなたがたが初めから受けていた古い戒めである。その古い戒めとは、あなたがたがすでに聞いた御言である。しかも、新しい戒めを、あなたがたに書きおくるのである」(ヨハネ第一の手紙2:7,8)。イエス様と直接交わった使徒ヨハネもまた、イエス様が、古い戒めを新しいものとされたことを語っています。
ところが、イエス様が、律法を完成する秘訣である愛を強調する言葉を語られると、ユダヤ人たちは、イエス様が律法の文字にはずれた言葉を述べていると非難しました。イエス様は、ユダヤ人たちのそれらの非難を次のような言葉で強く否定されました。
「わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思ってはならない。廃するためではなく、成就するためにきたのである。よく言っておく、天地が滅び行くまでは、律法の一点、一画もすたる事はなくことごとく全うされるのである」(マタイ5:17,18)
イエス様が愛を強調されたのは、律法を廃するためではなく、律法の根本精神と、律法に服従する力が愛からくることを表すためでした。
最後に、律法と愛の調和について、イエス様が教えられた聖句をご紹介しましょう。
「『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。これがいちばん大切な第一のいましめである。第二もこれと同様である、『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』これらの二つのいましめに、律法全体と預言者とが、かかっている」(マタイによる福音書22:37~40)
「心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ。これがいちばん大切な、第一のいましめである」。これは神様に対する愛として、十戒の最初の石の板に書き刻まれた第一条から第四条のいましめの要約です。
「同じく、第二もこれと同様である、『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』」。この言葉は、二枚目の石の板へ刻まれた、人々に対する愛の要約なのです。
イエス様は、この聖書箇所の最後に「これらの二つのいましめに、律法全体と預言者とが、かかっている」と語られる事によって、愛を実践する新しい戒めは、今までとは全く違う新しい戒めではなく、旧約時代のすべての律法と預言者たちを要約したものである事を明らかにされました。
イエス様は、誰がほんとうにイエス様を愛しているかを区別する判断基準として、次のような、明白な言葉を残されました。「もしあなたがたがわたしを愛するならば、わたしのいましめを守るべきである」(ヨハネ14:15)。
妻を愛するからと言って、妻のために自分がどれほど努力して犠牲を払ったかをひけらかすような夫がいるでしょうか。もし、あるクリスチャンが、「神様、私はどんなときにも安息日を覚えてそれを守りました。主が来られるとき私の努力を覚えてくださり、私を救ってください」と言うなら、それを聞かれた天の父なる神様はどう思われるでしょうか?安息日を覚えてこれを聖として守る事は、努力でもなく犠牲でもありません。それは押さえきれない愛の表現そのものです。「もしあなたがたがわたしを愛するなら、わたしのいましめを守るべきである」と言われたキリストの言葉の意味を知って、実践する人こそ、ほんとうに、救われたクリスチャンです。
古い契約の意味
ある日、教会で説教を終えた後、皆さんとあいさつを交わすため入り口の方に向かって歩き出していたら、急に3人の青年が前に私の前にやってきました。そのうちの一人が、私に大きな声で尋ねました。「先生、今日の説教では十戒に対する従順を強調しておられましたが、まるで私たちが、古い戒めの下におかれているかのように話しておられました。私たちは今、新しい戒めの時代に生きているのではないでしょうか?」
青年は、十戒は古い戒めで、それは十字架上で廃されたものであるから、恵みの下に生きる現代のクリスチャンは、もはや十戒に拘束されないものだと信じていました。
その青年の発言は、今日、十戒に対して多くのクリスチャンが持っている確信を反映したものだと思います。しかし、そのような確信は、聖書で立証できるものでしょうか?私たちはこの問題を、聖書という基準によって正しくとらえるべきだと思います。十戒の教えが教会の中できちんと説かれなくなった事が、現在のキリスト教会の世俗化の大きな原因ではないかと思われます。
もし、国家の法律が廃止されたり、不必要だという意見が国民の中に強くなり、法律を無視したり、都合のいい所だけ守るというようになったら、その国はどうなるでしょう。あらゆる犯罪や不道徳が広がるに違いありません。同じように、クリスチャンが、戒めを無視したり、軽んじたりするなら、教会は自分勝手な話が飛び交い、秩序も、敬虔さも失われ、世俗そのものになっていくことでしょう。
契約の定義
まず契約ということについて考えてみましょう。契約には、様々なかたちがありますが、基本的にそれは、お互いの約束と誓いに基礎をおいた、双方の合意を意味します。各時代を通して神様は、人との契約に基づいて、ご自身の民を導かれました。神様は時には、個人と契約を結ばれ、またある時は国家と契約を結ばれました。時代、場所、環境によって少しずつ異なった形で契約が結ばれましたが、神様の契約の条件は常に不変であって、「従えば祝福、従わなければのろい」というものでした。
今日の多くのクリスチャンは、契約に対する先入観を持っているために、次のような聖書の言葉を用いて、古い契約と新しい契約には違いがあるのだと主張します。
「ところがキリストは、はるかにすぐれた務めを得られたのである。それは、さらにまさった約束に基いて立てられた、さらにまさった契約の仲保者となられたことによる。もし初め〔古い〕の契約に欠けたところがなかったなら、あとのもの〔新しい契約〕が立てられる余地はなかったであろう。ところが、神は彼らを責めて言われた、『主は言われる、見よ、わたしがイスラエルの家およびユダの家と、新しい契約を結ぶ日が来る。それは、わたしが彼らの先祖たちの手をとって、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らがわたしの契約にとどまることをしないので、わたしも彼らをかえりみなかったからであると、主が言われる。わたしが、それらの日の後、イスラエルの家と立てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、わたしの律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となるであろう。彼らは、それぞれ、その同胞に、また、それぞれ、その兄弟に、主を知れ、と言って教えることはなくなる。なぜなら、大なる者から小なる者に至るまで、彼らはことごとく、わたしを知るようになるからである。わたしは、彼らの不義をあわれみ、もはや、彼らの罪を思い出すことはしない」。神は、『新しい』と言われたことによって、初め〔古い〕の契約を古いとされたのである。年を経て古びたものは、やがて消えていく」(ヘブル人への手紙8:6~13)
この言葉は、あたかも古い契約に問題があったために、“さらにまさった契約”である新しい契約が結ばれ、古い契約は古びて消えたのだと説明しているように見えます。それでは、神様の戒めを心と思いに書き記す新しい契約とはどのようなもので、古びて消えて行った古い契約とは何だったのでしょうか?そのことがはっきりするなら、この聖句に対する正しい理解が与えられることでしょう。
廃止された契約は十戒ではない
聖書には廃止された契約に関する記事が出ています。そこで、ある人々は廃止された契約とは十戒であると思っています。しかし、廃止された契約に十戒が含まれていないことは、次の三つの聖書的証言をあげることができます。
第1の証拠:パウロは“さらにまさった約束、さらにまさった契約”という表現を通して、古い契約に何らかの問題がある事を言っています。ではもし、十戒が古い契約そのものであるとするならば、十戒の中でそのような問題点、何か貧弱な約束を探し出せるでしょうか?『ヘブル人への手紙』の著者であるパウロは、『エぺソ人への手紙』の中で、十戒の道徳律がとても良いものであると語っています。「子たる者よ。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことである。『あなたの父と母とを敬え』。これが第一の戒めであって、次の約束がそれについている、『そうすれば、あなたは幸福になり、地上でながく生きながらえるであろう』」(エぺソ人への手紙6:1~3)。
パウロは、ヘブル人への手紙の中では、十戒が古い契約で欠けたところがあると言い、エペソ人への手紙では、幸福になる正しい教えであると、矛盾したことを言っているのでしょうか?そうではなく、ヘブル人への手紙8章の、欠けたところのある契約とは、十戒ではなく、旧約時代に繰り返された、キリストのひな型である犠牲制度の律法であったと見るべきなのです。
第2の証拠:古い契約が十戒ではなかったことを示す、最も強い証拠は「古い契約に欠けたところがあった」と言われている言葉のなかにありますい。「もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、あとのものが立てられる余地はなかったであろう」(ヘブル人への手紙8:7)と言われています。仮に、十戒が古い契約そのものであったならば、私たちは神様が手ずから石の板へ書き記された十戒の中から、何かの欠陥を発見しなければなりません。
詩篇を書いたダビデと、使徒パウロは、この問題に対してどのように語っているか聞いてみましょう。
「主のおきては完全であって魂を行きかえらせ」(詩編19:7)
「このようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しく、かつ善なるものである」(ローマ人への手紙7:12)
明らかに十戒を意図しているこれらの聖書箇所で、おきてや律法が、何か貧弱で欠陥があるものとして描写されているでしょうか?いいえ、かえって、完全であり、善なるものであると宣言しています。完全であるとは、どんな欠陥も探し出せないことを意味しています。
第三の証拠:「神は、『新しい』と言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものは、やがて消えていく」(ヘブル人への手紙8:13)。ここで使徒パウロは、古い契約は廃止され消えていったと、強い表現を使って述べています。古い契約が十戒をさしているのだとすれば、神様の道徳律である十戒が古びて消えていったことになります。しかし、パウロの律法に対する立場は、「すると、信仰のゆえに、わたしたちは律法を無効にするのであるか。断じてそうでははい。かえって、それによって律法を確立するのである」(ローマ人への手紙3:31)。このように語り、律法が信仰によって確立されていくべき、重要なものであることを教えています。こうして私たちは、古びて消えていった古い契約が、十戒を指しているのではないことを確認することができます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
