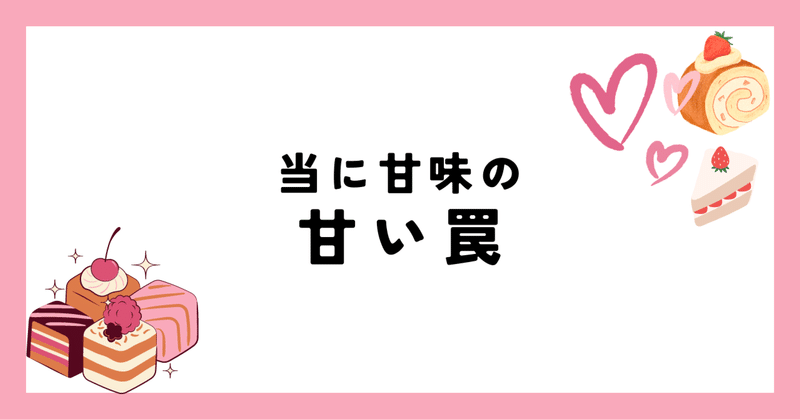
4. 「当に甘味の甘い罠」
ワンポイントアドバイス4
唐突ですがヒトの味覚は5種類。
苦味、酸味、塩味、甘味、そして うま味 です。
誇らしい事に、最後の旨味は日本人が発見しました。
この “うま味” については別の機会で話すとして、では残り4種類の味覚とはなんなのか?
味覚にはどのような意味があるのでしょう、、、。
端的に、苦味、酸味、塩味、は警戒する味、食べる事に注意をはらう必要がある味。
太古の昔、ヒトの祖先が樹上生活をしていた頃、せっせと食べ物を探していた時から長い時間を経て備えられた、本来
“ヒトが安全に生きる為の一つの大切な感覚”
非常に重要な感知機能なのです。
塩を口にたくさん含めば吐き出し、作りおいていた料理を食べた時にあれ?酸っぱい、、、と感じたら吐き出します。
甘いはずの大福が苦ければ吐き出します。
ですよね?(-_-;)
●“幸せホルモンドーパミンの分泌”
ですが甘いものは別。
大袈裟に言えば 甘味は食べるべき味、、、ヒトは本能的にそんな感覚を持っている。
ですから甘い物を求めようとします。
これが 当に“甘味の甘い罠” の原因なのです。(´;ω;`)
甘味中毒、甘味依存、、、なんて嫌な例えもある様ですが、それは脳の仕組みのせい。
甘味を摂ることで “幸せホルモンの一つ、ドーパミン、α-エンドルミン”
の分泌が促されるからです。
つまり甘味を食べると ”なんか幸せ” そんな感情が沸き起こる、、、
ですが、この状態は長続きしません。
すると脳がまた繰り返し甘味を求めてくる。
するとまた甘味が食べたくなる。
すぐ手の届くところ、例えばテーブルの上にクッキーや焼き菓子を常備していればさっと手を出して口にしてしまう、、、。
これが “甘味中毒、甘味依存” の正体です。(-_-;)
このサイクルが頻繁になればなるほど抜けられなくなる、、、要注意です。
●甘味の習慣を作らないことが大事。
常日頃から “甘味を我慢する”
そんな感覚をお持ちの場合は既に脳が頻繁に甘味を求めている状況なのかも。(^_-)
なんだか散漫で集中できない、やる気が出ない、、、甘いもの食べたいなあ、、、
で パクッと一口。
こんな状況がやがて恒常的になってしまう、、、これは先行き不安です。
もちろん仕事に集中して疲れた!
こんな時に甘味を欲しがるのは当たり前の事、脳がフル回転すればそれだけブドウ糖が消費される、、、なんら問題ありません。
● ビーマルワン(BMAL1) “甘味を食べるなら15時”
ところで3時のおやつ、、、
これは江戸時代から庶民の間で広まった習慣との事。
1日2食が一般的なこの時代、ちょうど一休みに合った間食タイムだったのでしょうね^^
この令和の時代においても同じ様な事が言われています。
“甘い物は15時に食べよう” 、、、メディアでも取り上げられる甘味のゴールデンタイム。
これにはちょっと納得してしまいそうな理由があります。
ビーマルワン(BMAL1)、ご存知の方も多いと思います。
脂肪細胞に脂肪を溜め込む働きをするたんぱく質の名前ですが、このビーマルワンの分泌が一番少ない時間帯が15時前後という事から、この時間に食べれば ”太りにくい?”と、、、。
果たしてどうか?
粗食で栄養価も低かった食環境の江戸時代と飽食環境にある今を比較してみるとどうでしょう。よくよく考えてみる必要がありそうです。
何より 甘味の習慣をつけない事が一番です。^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
