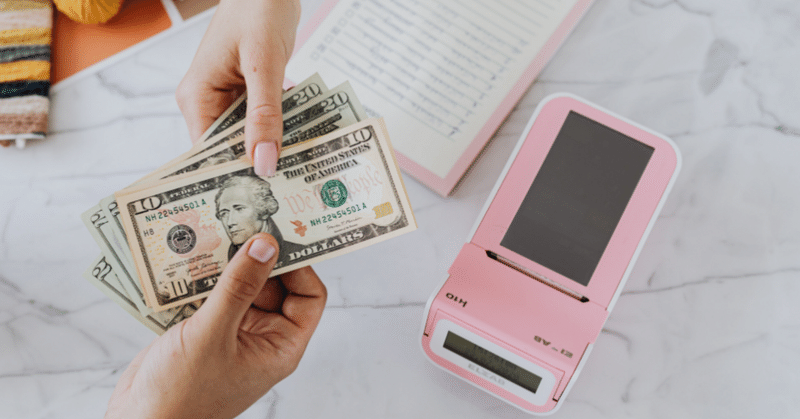
物々交換の現代
自分が大学に入って、初めてクレジットカードを保有し、また、PayPayなどの、スマホで完結するキャッシュレス決済サービスを利用し始めたころ、一つ、頭の中にふつふつと湧いてきた考えがあった。
高校生の頃は、現金を使っての買い物が多かった。ほとんど唯一の収入源である親族からの贈与(お小遣いとか、お年玉とか)は、もちろん現金手渡しだったし、親がお金を出してくれるタイプの必要経費や遊興費も、仮払形式か立替形式かはさておき、現金でのやり取りがほとんどだった。
WAONは使っていたような記憶がある。家族旅行で沖縄に行った時に買った、首里城がプリントされたご当地WAON(?)だ。WAONは電子マネーだが、クレジットカードを保有していないので、現金をチャージして利用する。5000円札をコンビニの店員さんに渡して、2000円チャージするといったエモい使い方だ。今はといえば、5000円札をそもそも持っておらず、おつりが出てくるのを面倒くさがって1万円札をそのまま全額ICOCAに入れてしまう。あの頃とはちょうど真逆の、まったくもってかわいらしくない使い方である。
そういう世界の話だから、分類上は電子マネーであっても、リアルマネーとしての現金との接点が多く、プラスチック製で、手元から離れていかないだけの現金というべきものである。
これが、大学に入り、アルバイトを始めるにあたって新しく自分名義の普通預金口座を開設し(銀行の窓口で、対面で口座開設した!)、あわせて自分名義のクレジットカードも作った。それでもまだ現金を使う場面は多かったが、その後PayPayが普及し、学部を出てロースクールに入るころにはほとんど現金を使わなくなった(学部4年がコロナの時期であったから、そのときの決済周りのことはあまり記憶にない)。
そんな中で、1つ思うところがあった。ロースクールに通いながら細々と続けて得た、なけなしのアルバイト収入は、自分名義の普通預金口座に振り込まれる。一方で、ロースクールの授業の合間に食べる質素なコンビニ飯や、授業の予習で忙しくて読めないにもかかわらずkindleアプリ内にうずたかく(観念的に)積みあがる電子書籍の購入などは、いずれもリアルマネーはおろか、プラスチック製のカードすら介さずになされるようになった。
もちろん、決済手段としての現金が下火になったというそれだけの話なのではあるが、現金は、自己の労働の成果を示す役割(昔の、あるいは昔を描いたコンテンツで見ることのある、現金手渡し時代の「給料袋の厚み」を想起するとわかりやすい)と、財やサービスの価値を示す役割を持っており、決済手段としての現金は、まさにこの2つの役割を結び付けるものだといえる。その現金を決済手段として用いなくなると、自分の労働の成果は普通預金口座に計数的に増やされるのみで、他方の、購入した財やサービスの対価も、普通預金口座から計数的に減らされるのみである。WEB通帳に青字と赤字で書き分けられて、それで、終わりである。
このように考えると、我々は、労働で直接的に財やサービスを購入しているのと変わらないといえるのではないか。1click購入に顕著なネットでの非対面決済や、モバイルオーダーサービスの普及などもあいまって、媒介としての現金に対する意識が希薄化すると、より一層、このような感覚にリアリティが出てくる。
この話を友人にして、ウケが良かった覚えはないが、先日、とある本を読んでいて、まさしく上で述べたようなことと同じような記述に出会い、嬉しくなった。
キャッシュレス決済は、実は物々交換とよく似ています。どういうことか、①私が自分の勤務先である大学から給与を受け取る、②私がレストランに出かけ食事をする、③レストランのオーナーの子どもがたまたま私の大学の学生で、大学に授業料を払う、という三つの支払いの例で見てみましょう。三つの支払いとも同額(たとえば一〇万円)とします。一昔前までは、私は大学から給与を現金でもらい、レストランで食事代を現金で払い、オーナーは授業料を現金で払う、というように、これらすべての支払いを現金で行っていました。しかしいまはキャッシュレスで決済できます。
私はレストランでクレジットカードを使って代金を支払い、レストランのオーナーは子どもの授業料をクレジットカードで支払うとします。私─勤務先の大学─レストラン─クレジットカード会社、このすべてが同じ銀行に口座をもっているとすると、決済日には、大学の口座→私の口座→クレジットカード会社の口座→レストランの口座→クレジットカード会社の口座→大学の口座、という順番でぐるっとおカネがまわることになります。「おカネがまわる」と言っても、銀行のコンピュータ上でそれぞれの口座の残高の数字が書き換えられるだけです。大学と私とレストランは、それぞれ一〇万円もらって一〇万円支払うので、最終的に残高は変わりません。
ここでのポイントは、私は貨幣なしで大学からの受け取りとレストランへの支払いを済ませていることです。だから、私が貨幣に魅力を感じることもないし、貨幣を需要することもありません。オーナーも大学も同じです。
もう少し正確に言うと、私は貨幣をもっていないわけではありません。私は銀行に口座をもっていて、それを使って支払いをしています。だから、銀行預金は貨幣と似た機能をもっています。実際、政府や日銀が、貨幣が世の中にいくらあるかを数える統計を作成する際には、銀行預金も貨幣の一部としてカウントします。しかし、右の例では、私の口座に勤務先から振り込まれた瞬間にその残高はレストランへの支払いとして送金されるので、私の口座に残高があるのはほんの一瞬です。その瞬間、預金という貨幣を私が手にするのは確かですが、それはその瞬間だけで、その他の時点では預金をもっていません。だから、平均的な預金残高は微々たるものです。しかも、私の口座の残高が変わる瞬間を私自身が知ることはないので、貨幣の魅力を実感することもありません。
なんでこの具体例にしたのかちょっとよくわからないところはあるけれども、「労働で直接モノやサービスを購入している」という私のアイデアが、「物々交換」という端的な言葉で表現されているではないか。
この一致によって、「現代は物々交換に回帰している!」みたいな論理の飛躍した目的不明の思想をふりまこうとするつもりがあるわけではもちろんないから、だから何だという話なのではあるが、自分の日常生活のバックグラウンドで何となく考えていたアイデアが、全く知らない文脈において、別な仕方で説明されているのに思いもかけずでくわすと、なかなかうれしい気持ちになる。
これは、自分の専門分野である法律において、「こういう説明でこういう帰結になるのではないか」と仮説を立てて、まさしくその通りの説明がリサーチの結果として出てきても、「やっぱりそうだよね。裏付けてくれてありがとう。」というドライな感情しかわかないことと好対照である。
自分の日常生活のバックグラウンドでものを考えること、関心の幅を広く持って、専門外のコンテクストに触れること、この2つは絶えず続けていかなければならないなと、ポジティブな形で思わされたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
