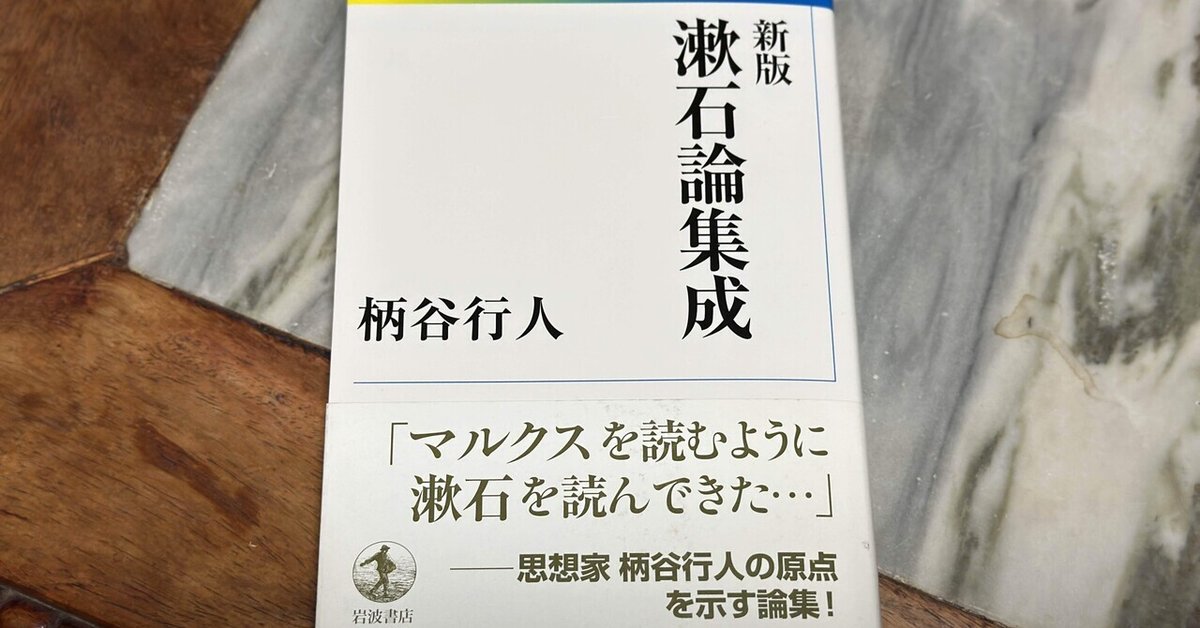
漱石の小説がもつ倫理的な位相と存在論的な位相の二重構造——柄谷行人『意識と自然』より
要するに、漱石の小説は倫理的な位相と存在論的な位相の二重構造をもっている。それはいいかえれば、他者(対象)としての私と対象化しえない「私」の二重構造である。他者としての私、すなわち反省的レベルでの私を完全に捨象してしまったとすれば、そして純粋に内側から「私」を了解しようとすればどうなるか。それを示しているのが「夢十夜」だ。この「夢」は漱石の存在感覚だけを純粋に暗示するのだが、われわれは漱石のどの作品にもこういう「夢」の部分を、すなわち漱石の存在感覚そのものの露出を見出すことができるのである。『坑夫』の出口のない地底の迷路もそうだし、『それから』の冒頭と最後にあらわれる「赤」の幻覚にしても然りである。
柄谷行人の出発点、漱石論の第一の論文『意識と自然』(1969年)よりの引用。柄谷は「今ふり返ってみても、夏目漱石論は私にとって、最初で且つ最も核心的な仕事であったと思う。特に1969年に群像新人賞を受賞した「意識と自然——漱石試論」には、10代から20代にかけて考えていたことが凝縮されている」と語っている。柄谷は、漱石の長編小説を読むと、なにか小説の主題が二重に分裂しており、はなはだしい場合には、それらが別個に無関係に展開されている、といった感をおぼえるという。『門』の宗助の参禅は彼の罪悪感とは無縁であり、『行人』は「Hからの手紙」の部分と明らかに断絶しており、また『こゝろ』の先生の自殺も罪の意識と結びつけるには不充分な唐突さがある。
漱石の小説に関して、「自己本位(エゴイズム)」や自意識の相克をみることは一種の誤解であると柄谷はいう。むしろ漱石は、人間と人間の関係を意識と意識の関係としてみるよりも、まず互いが同じ空間を占めようとして占めることができないというふうな、なまなましい肉感として、すなわち「存在論的な側面」において感受していたのではないかという。
漱石が問題にしていた存在論的な側面としての「私」とはなにか。それを柄谷は、対象としての私ではなく、対象化しえぬ「私」の同一性・連続性の問題であるという。『坑夫』に出てくる「此の正体の知れないもの」という表現に柄谷はその典型をみる。そしてもちろんそれは、漱石自身が感じていた非現実感・剥離感であった。漱石に生じている自己自身と外界からの剥離感は、反省的意識によって捉えられるものではない。それは、反省的に対象化できないような「私」の次元において生じたものだからである。漱石は、意志によってはどうすることもできないこの種の感覚や変容をさまざまな形でのべている。『行人』にでてくる「君の恐ろしいといふのは……つまり頭の恐ろしさに過ぎないんだらう。僕のは違ふ。僕のは心臓の恐ろしさだ」という表現がその例である。柄谷は、われわれが自意識や他者との倫理的葛藤を主題としたとみなしている漱石の長編小説を、「裏側」から、すなわち存在論的な側から読みなおしてみる必要があるという。
『門』の宗助は、かつて女を友人から奪ったという罪悪感に苦しんでいるが、それはある一般的な(漱石に固有の)「不安」に転化していき、それを解決するために宗助は参禅する。この小説が途中から妻を無視してしまっているのは、その「不安」が罪悪感からきた明瞭なものではなく「正体の知れないもの」だったからであると柄谷はいう。『門』の宗助は、その題名が示すように宗教を求める。「自分は門を開けて貰ひに来た。けれども門番は扉の向側にゐて、敲いても遂に顔さへ出して呉れなかつた」。この「門番」はカフカの短篇の門番のように、他者ではなく自己自身に関係する自己である。この「門番」は、門を開けてもらおうとすることそのものによって、門を閉ざすというふうに存在している。これはキルケゴールが「絶望的に自己自身であろうとすること——反抗」と呼んでいるものと同じであると、柄谷はみる。そして、キルケゴールの「不安」とは、いわば『行人』で語られるような「心臓の恐ろしさ」、つまり自意識の問題からくる不安ではなく、身体そのものからくる(存在論的な位相における)名状しがたい「不安」なのである。
つまり、漱石の長編小説はどれも倫理的な位相と同時に、存在論的な位相をもつという二重構造になっていると柄谷はいう。『こゝろ』の先生は自殺をとげる。この自殺の理由はさまざまに論じられているが、友人Kを裏切ったという罪悪感からのみきたものでないことは明らかである。「私は私の出来る限り此不可思議な私といふものを、貴方に解らせるやうに、今迄の叙述で己れを尽した積です」と先生は書いている。この「不可思議な私」とはなにか。それは、他者としての私(外側からみた私)と他者としての対象化しえない「私」(内側からみた私)を同時に意味していると、柄谷はいう。したがって、『こゝろ』は人間のエゴイズムとエゴイズムの確執などというテーマとは無縁である。漱石が凝視していたのは、依然として「正体のしれないもの」なのである、と柄谷は強調するのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
