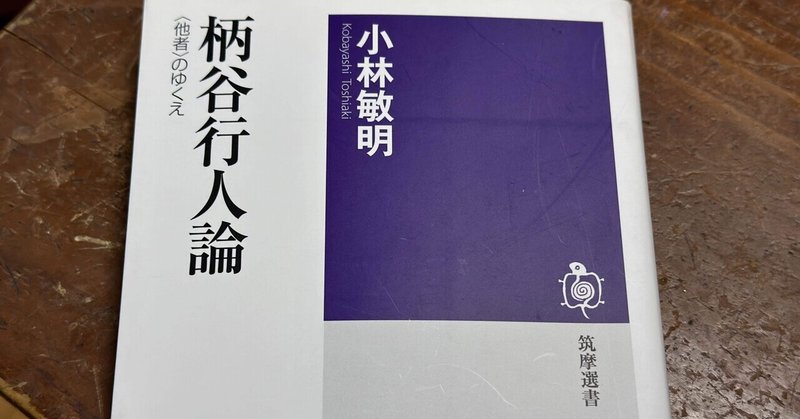
漱石とレヴィナスの「存在することの不安」——小林敏明『柄谷行人論』より
おそらく、漱石は人間の心理が見えすぎて困る自意識の持主だったが、そのゆえに見えない何ものかに畏怖する人間だったのである。
柄谷行人(からたに こうじん、1941 -)という人がいる。戦後思想界の巨人の一人で、哲学者、文学者、文芸批評家である。彼の関心は、漱石研究など「日本文学」から始まったが、そこから外国文学へ、そしてさらには哲学、数学、経済学、歴史学という領域へと広がっていった。その思想の幅の広がりは比類なきもので、その代表作を見ても『〈意識〉と〈自然〉 漱石試論』『マルクスその可能性の中心』『坂口安吾と中上健次』『世界史の構造』『哲学の起源』『ニュー・アソシエーショニスト宣言』など多彩なものがある。
柄谷の思想は何を軸としてどのように展開していったのか。漱石研究や文芸批評から始まった柄谷の思想の旅路は、哲学・精神分析・言語論・マルクス主義などを経て、どこを目指すものだったのか。それを解説しつつも、独自の視点で鋭く分析したのが小林敏明氏の『柄谷行人論』(筑摩書房, 2015)である。小林敏明氏は哲学・精神病理学を専門とする哲学者(ライプツィヒ大学東アジア研究所教授)で、西田幾多郎、廣松渉などに関する著書がある。『柄谷行人論』の序章で小林氏は、戦後1970年あたりまでは、丸山眞男や吉本隆明、廣松渉など時代と格闘しながら独自の思想をもって論断をリードしてきた知の巨人たちがいたが、それ以降は柄谷行人くらいしか残っていないと嘆く。
柄谷の出発点となった漱石研究は、決して文学批評というフィールドにおさまるものではなく、むしろ「固有の思想をもったひとりの悩める実存」としての漱石を対象にしつつ、柄谷自身の離人症的な感覚、つまり現実に対する現実感のなさ、「存在することの居心地の悪さ」をも分析することにつながっていた、と小林氏は述べる。例えば、『行人』の中で「心臓の恐ろしさ」と表現されていたものが、それにあたる。
「君の恐ろしいというのは、恐ろしいという言葉を使っても差支ないという意味だろう。実際恐ろしいんじゃないだろう。つまり頭の恐ろしさに過ぎないんだろう。僕のは違う。僕のは心臓の恐ろしさだ。脈を打つ活きた恐ろしさだ」
小林氏は、柄谷が漱石研究で論じていた「存在することの不安」あるいは「裸形の人間としての不安」は、レヴィナスの思想に通じるところが大きく、柄谷もレヴィナスに自覚的に関心を寄せていたと述べる。レヴィナスが論じていた存在することの根源的な不安とは以下のようなものであった。
存在の積極性そのもののうちに何かしら根本的な禍悪があるのではないだろうか。存在を前にしての不安——存在の醸す恐怖〔おぞましさ〕——は、死を前にしての不安と同じく根源的なのではないだろうか。存在することの恐怖は、存在にとっての恐怖と同じく根源的なのではないだろうか。いや、それよりいっそう根源的なのではないだろうか。
ここでは「存在」すなわち「あること」が、そのことだけで不安や恐怖をもたらすことが表明されていると、小林氏は述べる。では、こうした「裸形の人間としての不安」をめぐる漱石=柄谷とレヴィナスとの類似は何によっているのかが問題となる。そこでは「見えすぎて困る自意識」(本稿冒頭の引用)が鍵となる。漱石を読んだ柄谷が感じていたこととは、「心臓の恐ろしさ」を知る過敏な精神が体験している不安だったのではないか。それは、「見えすぎる」だけではない「見えすぎて困る」という苦痛なのであり、レヴィナスと同様に、切りつめられた意識がぎりぎりのところで感知した「存在すること」それ自体の苦痛だったのではないか、と。
小林氏は、この種の不安はすべての人が感じているはずだと述べる。「それはわれわれの意識の根底にいつでも横たわるもの」だからである。しかし、日常生活で私たちはそれに気づいていないかのようのである。それは私たちが「日常性への頽落」(ハイデッガー)のなかにあるからであり、ときには感じ取っているこうした瞬間は、神経の鈍麻とともに忘れられているのだと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
