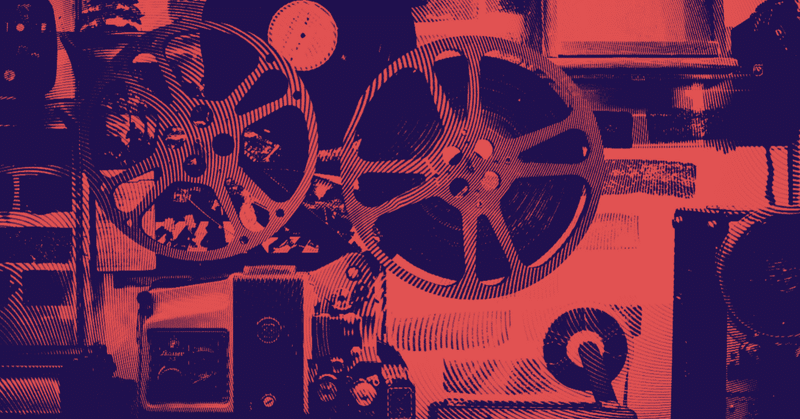
道
果たして、あとどのくらい、映画を見れるのだろう。
そう思ったのは、ネットを検索していて、「死ぬまでに観たい映画百選」というのを、各団体が発表していて、それを見ていると、ああ、この映画は観た、これは観てないがランクに入ってるんだとか、色々と感慨深いものがあった。
しかも、死ぬまでに観たいと付けられると、老い先短い身の上では、まさに切実感が増してくる。
最近は観る機会も極端に減ってきたが、若い頃はよく映画を観た。
「年に何本ぐらい観るの?」
と訊かれると、大体いつも
「そうねえ、百本ぐらいかなあ」
と答える。
確かにその頃は、やみくもに俗に名画座と呼ばれる映画館をはしごして、映画を観ていた。それが90本であろうが、110本であろうが、数えたこともないのに、100と答えるのが、なんとなく、かっこよかった。
と、必ず、では今まで見た中でベストスリーはと訊かれる。
私は別に映画評論家でもないので、適当に答えればいいのだが、うーんうーんと唸りながら、まるで、その答えで訊いた人の人生が変わるかのように悩んで、勿体つけてベストスリーを発表する。
それはいつも固定されたものでなく、その時の思い付きや、雰囲気でも変わるし、その時々で一位と三位は変わるのだが、二位だけは、いつも変わらない。
それが、フェデリコ・フェリーニ監督の「道」である。
誰もが知っている名作ではあるが、今回様々な百選を見ても同じネオ・リアリズムのデ・シーカ監督の「自転車泥棒」は載せられていても、この映画は外れていることが多い。
映画という媒体をどうとらえるかで、少し、百選としての評価も変わるのだろうけど、それを抜きにしても、観る側の心持次第で、その影響が大きく変わる映画なのかもしれない。
少なくとも、私にとって「道」は私の生き方を変えた映画である。
名作ゆえに、多くの人がこの映画のあらすじはご存じだろう。
主人公は少し知恵遅れの女、ジェルソミーナ。
彼女の家は貧しく、ある日、彼女は旅芸人のザンパノという男にお金で買われる。
彼女は家を出て、ザンパノと長い旅に出ることになる。
ザンパノは裸の身体に巻きつけた鎖を気合でひきちぎるという、これもまたお粗末な芸を売りにする男である。
ジェルソミーナは、太鼓を持ち、ラッパを吹き、旅芸人としてザンパノの助手として同行するが、このザンパノという男、野卑で乱暴者で、ジェルソミーナを叩き、怒り、ひどい目にあわせ、しかも彼女を性の対象ともする。
まるで夫婦のようにして、おんぼろバイクで各地を回る二人だが、ザンパノは各地で喧嘩をし、大酒をくらい、女を抱く。そんな時、ジェルソミーナは車を降ろされ路上に放置される。
そんな酷い仕打ちを受けながらも、ジェルソミーナは何とかザンパノのパートナーとして役に立ちたいと健気にそう思っている。
この辺のところを、作家、遠藤周作はぐうたらシリーズの中で、この二人の関係を世の男と女の象徴的のものとして、取り上げていたが、私の興味はそこではない。
ある日、二人はその旅の途上でサーカス団の一行と出会う。
その中に綱渡りを得意芸とする男がいた。この男はザンパノとは昔からの顔なじみだが二人はそりが合わなかった。男の芸はザンパノとは対照的でエンターテインメントとして十分観れる立派なもので、人間的にも温和で、二人もサーカス団の一員として参加するうちに、ジェルソミーナは綱渡りをする男と仲良くなる。
だが、ザンパノはそれが気に入らない。二人は喧嘩になり、大騒ぎとなって、留置場に入れられてしまう。
先に留置所から出てきた綱渡りの男はジェルソミーナに、あんな酷いザンパノと別れて、自分たちと一緒に行こうと誘うが、彼女は「自分は今まで何とかザンパノの力になろうと頑張ってきた。なのにうまくいかない。私は何の役にも立たない人間なんだ」と答える。
その時、綱渡りをする男は足元の小石を拾い上げて言った。
「こんな小さな石ころだって、たぶん何かの役に立っているんだ・・・」
だからお前もきっと何かの役に立っている・・・、と。
結局、ジェルソミーナはザンパノとの旅を選び、その後は一層ザンパノに尽くしていく。
しかし、肝心のザンパノは相変わらずで、世話になったところの物を盗むは、挙句には、偶然再会した綱渡りをする男を殴り殺してしまう。
さすがのジェルソミーナも、それ以来、精神的にも肉体的にも衰弱して行き、そんな彼女をザンパノは置き去りにしていく。
数年後、ジェルソミーナを捨て、一人で相変わらずの旅芸人として各地を回っていたザンパノは、どこからか聞こえてきたメロディーにはっとなる。それはジェルソミーナがトランペットでよく吹いていた曲だった。
そして、ザンパノはジェルソミーナがそこで死んだことを知らされる。
ジェルソミーナの死を知ったザンパノは、暗い海岸線をさまよい、砂浜に這いつくばって、号泣する。有名なラストシーンである。
映画館を出て、私は近くにあった小さな児童公園に立ち寄った。夕暮れが近付いていた。公園には誰もいなかった。
映画を観たからといって、実生活が劇的に変わるものではない。
私はその頃全てに絶望していた。
故郷を捨て、意気揚々と都会に出てはみたものの、気付かされたのは、自分の能力の無さだけだった。全てがうまくいかなかった。話し合える友達も恋人もいなかった。私は独りだった。
ジェルソミーナと同じで、自分の存在意義を考える、毎日だった。
映画の中で、綱渡りをする男は、小さな石ころだって何かの役に立っている、とそう言った。だが、どうしてそうわかるのか、と訊き返すジェルソミーナに、「それは俺にもわからない、でも、そうでなければ全てが無益だ。空の星だって・・・」とそう曖昧な哲学的な言葉を・・・。
結局、ジェルソミーナはザンパノに必要とされていた訳だが、でも自分の存在意義が認められたのは死んでからなのか、じゃあ私は・・・。
どれくらいの時間が経っただろうか、ふと、気が付くと公園のベンチに腰を降ろしたまま、私は、夕日を全身に浴びていた。
と、その時、あることに気付いたのである。
当たり前の話だが、公園の遊具も、水飲み場の水道も、小さな広場も、草むらも、すべてが夕日を浴びて、その影を長く背後に伸ばしていた。
私ははっとなった。
建物だけでなく、たとえば広場に転がっている石も、草むらに伸びた草の一本一本まで、それぞれに固有の影を持っていることに・・・。その時改めて気付いた。
「そういうことか・・・そういうことだったのか・・・」
私はようやくベンチから立ち上がり、帰路についた。
その日、私の中で、小さな覚悟のようなものが生まれたことを感じていた。
道
人生の途上で それはいつも目の前に続いている
でも私の前にはもうそれほど拡がっていないのかもしれない。
後ろを振り返れば 歩いてきた道 そこに確かな足あとは残されただろうか
この道を行く この道しかない
その時愛するパートナーや家族がいれば 嬉しい
自分がもし誰かに必要とされるならば そう感じれるものなら その道程も楽しいものになる
でも たとえそうでなかったにしても 私は 私自身の固有の影を引きずって 独り この道を歩いていく
そこに 自分の存在意義は見いだせないかもしれないが きっと それは何かしらの意味があるに 違いない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
