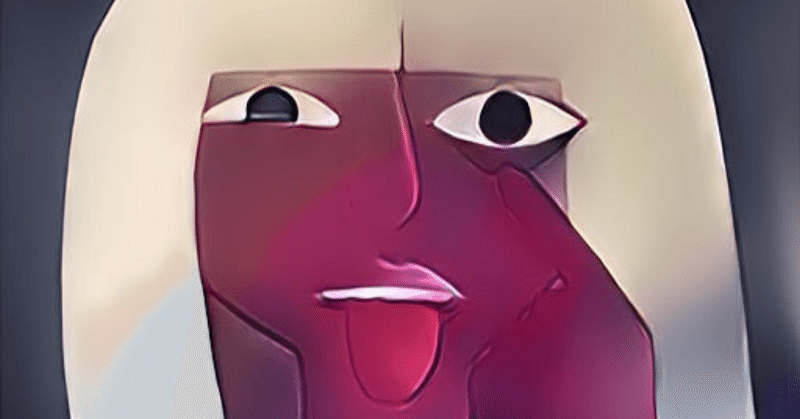
ただの綺麗事。ふざけんな。
前回からの続き。
この記事のキーワードとしては
【大人の介入により達成できる目標の設定】である。
おさらいとして、この自閉症男児(推定5歳、発達年齢約2歳半とする)には、家族で食卓を囲む際に以下の能力が備わってない。
それは、
・自分の皿とその他の皿の役割の認識。
・個々で食べるもの、家族みんなで食べるものの違いの判別。
・食事をする際の最低限のルールの理解等。
・そして、集団行動をする上での状況理解。
だが、この男児は上記の能力は備わっていないが、母親からの個別指示を理解したり、個別で意思を伝える事はできるようであった。
ですのでこの場合、少々大胆であるが、料理を囲んで家族顔を見合わせて食事をするスタイルから、横一列に並んで食事をするスタイルへの変更をまずは提案したい。(環境配慮)
並び順は、壁から男児→母親→妹→父親がベスト。
男児の前には男児の皿のみ。
おかずを取りたい場合は、母親にその意思を伝えて取ってもらう。
意思を伝えられた母親はすかさず男児を褒める。
自分で取りたいという場合にはやらせて、それができたら褒める。
このスタイルを続け、それが慣れてきたら母親はわざと男児に小さなストレスを与える。
取ってと頼まれたものを先に母親がとったり待たせたり。
やり方は様々だが、大事なのは先程も言った通り、【大人の介入により達成できる目標】をストレスとして与える事が重要である。
この男児の場合、まずは待つ事や我慢する事である。
待つ事のメリットや我慢の先にあるものを何もしらないのだ。
きっとデメリットとも感じてないだろう。
今すぐ欲求を満たしたいという事しか頭にない動物状態だ。
なので、待つ・我慢の時間も最初は秒単位でもいい。
秒であれ、待てたら褒める。
我慢できれば褒める。
これを繰り返し、時間を少しずつ伸ばしていくのだ。
こうやって少しずつ能力が上がってきた頃に、男児の能力に合わせ次の目標を設定する。
目の前に大皿を用意したり父親を座らせたりは、待つや我慢とは違った目標になるので違ったアプローチにはなるが、介入によって達成できる目標を設定し続けて、最終的には家族が顔を見合わせて食卓を囲むという状態にもっていくのだ。
その頃の男児は、注意や叱責を受けずとも、肯定感を維持したまま必要な能力が上がっている状態なので、食事に対して抵抗もない。
妹も、兄に邪魔される事なく食事を楽しめる上に、両隣には笑顔の両親が座っているのだ。
これで、皆んな笑顔の食卓のできあがり。
はい、これでめでたしめでたしって。
はぁ〜、結局こんなもん。
ただの綺麗事、絵空事。
ふざけんな。ばーか。
なんてね❤︎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
