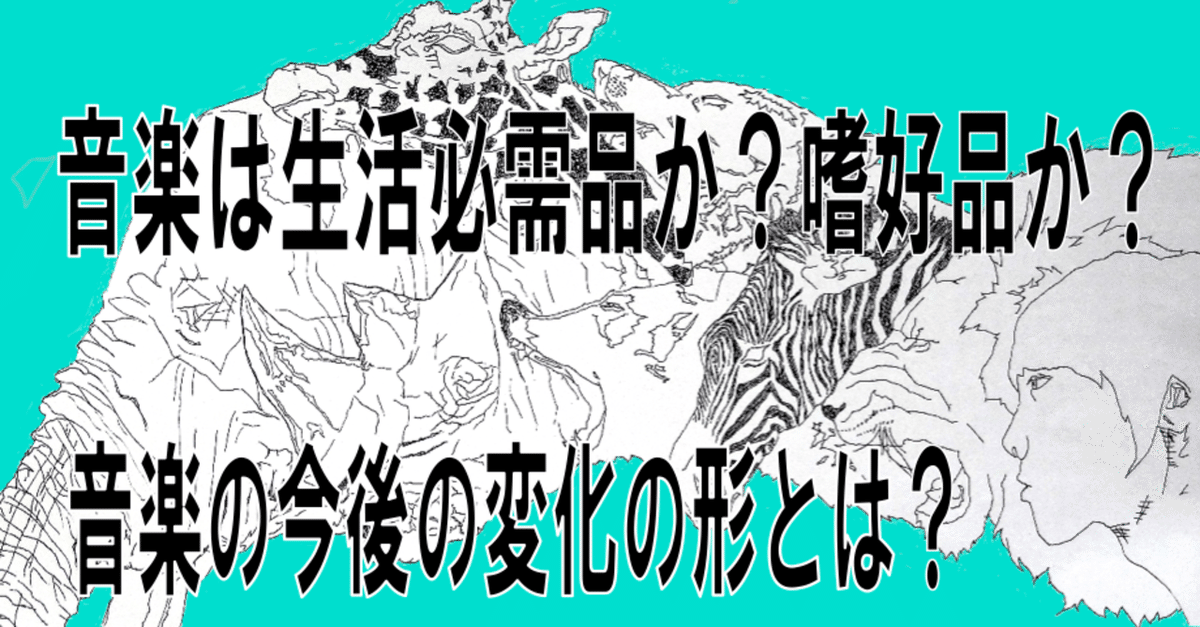
音楽は生活必需品か?嗜好品か?そして音楽の今後の変化
前回の記事で、『生活必需品と思想は洗練され、嗜好品は多様化していく』という考察をしてみました。
(今回の記事は長いので、目次から「まとめ」のタイトルに飛んでもらっても大丈夫です。)
そうした中で、『音楽は今後一体どんな変化を遂げていくのか?』
今回はその点について考察してみたいと思います。。。が、
その前に、
【音楽とは生活必需品か?嗜好品か?】
音楽とは生活必需品か?嗜好品か?という議論があるかと思います。
よく「将来ミュージシャンになる!」という主人公に対してその両親が「もっとちゃんとした仕事に就きなさい!」というやりとりが昔のドラマなどであったりしました。
確かに音楽を作ることで腹は満たされませんし、雨風しのぐ物理的な助けにはならないとは思います。
なので、
生きるベースの部分で衣食住が確保されることがまず優先される、として、
音楽が、社会で生きる中での電話のような生活必需品になるのか?娯楽などの嗜好品になるのか?
【音楽とは生活必需品か?嗜好品か?の個人的結論】
結論から言いますと、
『生活必需品にも嗜好品にもなり得る』と思います。
って、なんかズルい答え方ですが。
過去の記事で考察してみたのですが、人間が動物ではなく"人として"、"人らしく"生きる上で『個人としての生きる価値・存在意義を見つけたい』という欲求が人には存在します。
産業の発展によっての"労働"という『社会を生きるための"手段"』と両輪を成す『心をつくる"芸術"』は"人だからこそ"必要不可欠なものにも思えます。
そのため音楽などの芸術は生活必需品にもなり得ますし、
逆に嗜好品として生活の中の心の緩衝材やその他のツールにもなり得ます。
音楽は『生活必需品にも嗜好品にもなり得る』と結論づけておこうと個人的には思います。
【音楽の今後の変化】
前回の続きに戻りますが、
生活必需品や思想は洗練されシンプルになる、嗜好品は多様化する。
そうした中で、音楽がどういった形に今後変化していくのか。
音楽がその人にとってどういった役割を担っているかによって求められることが違うように思います。
【音楽の捉え方は様々】
①音楽をファッションと捉える人は「違い」を好む
→他者と差別化するための目新しさを求める。
②音楽をアートと捉える人は「否定」を好む
→現在の音楽の表現を否定した別のアプローチを取り入れたもの。
③音楽を産業と捉える人は「ニーズ」を好む
→音楽自体が作者の思想ではなく世間という大きな括りの中に漂う不安感や喜びの種類に沿った聴き手優先の作り方で、流行や時流を追ったもの。
④音楽を応援のツールと捉える人は「発信者自体」を好む
→このアイドルが好きだからこの曲買えばその人を応援できるので、あくまでその発信者自体の行動を追う。
⑤音楽をメッセージと捉える人は「ストーリー」を好む
→その音楽で語られるシチュエーションや心情描写から共感、または学びを取り出す。
⑥音楽を嗜好品と捉える人は「余白」を好む
→考える余地を残す作風。
⑦音楽に文化的価値を求める人は「思想」を好む
→作者のアイデンティティや生み出されたバックボーンを知ろうとする。
こうしたそれぞれの要素を人によって様々な組み合わせで持っていると思います。
例えば、僕はキリンジが大好きですが、キリンジを聴き始めた時には①の「違い」で、他者との差別化のために聴いてた節があります。
ちょっとニッチな部分を感じられるキリンジを聴くことを"特別な自分"として他者と差別化するための自分のステータスにしようとしていたんです。
そこからキリンジの音楽性にどハマりして⑤や⑥の意図で聴いてたりします。
音楽を日常のBGMとして捉えている人もいれば、音楽から人生の教訓を得ようとする人もいる。はたまた使用楽器やそのテクニックの妙に躍動したい、というものさしで音楽同士を比較することを嗜好する人もいる。
どれが正しくてどれが間違っているなんてこともない。
どれも音楽の聴き方として正解であり、だからこそ音楽が広く、長く親しまれてきた所以だとも思います。
【音楽の多様性の根底にあるもの】
こうして見ていけば、音楽は"多様化"という変化を遂げているように思えますが、
そもそもの『"音楽"という形』にフォーカスすればまた見え方は変わってくるように思います。
先程も挙げましたように、音楽には様々な楽しみ方や用途がありますが、それだけ多岐にわたって姿形を変える音楽の魅力、
他の生活必需品や嗜好品と一線を画す魅力として、"メロディー"という特徴があると思います。
【"メロディー"という特筆性】
メロディーとは言わば"感情を擬態化"させたもの。
「嬉しい」「悲しい」など言葉とはあくまで"感情の総称"で、本来は「嬉しい」の中にも様々な感情が含まれており、それらを束にしてその色合いを見た総称として「嬉しい」という名前をつけているに過ぎず、
一つの言葉では言い表せない感情を人は数多く持ち合わせています。
そうした感情の機微を事細かに再現してくれるのが、この"メロディー"だと思います。
常に流動的で様々な感情と共存する人間だからこそ、人間にとっての『人らしさ』を感じる上での表現として、発信するにしても受け取るにしても『音楽が欠かせない存在』になっていると思います。
用途が生活必需品としてでも嗜好品としてでも、
そこで『音楽を選んだ』ということの根源には少なからず"感情に訴える魅力"を感じ取った、とも言えそうです。
【人の持つ「いい!」という感覚】
その"感情に訴える魅力"が強い曲をよく「いい曲」なんて言ったりします。
「いい曲」という言い方はすごく抽象的ですが、
往年の名曲や、最近では米津玄師さん、星野源さん、YOASOBIさんなど、多くの聴衆からその楽曲に対して高い評価を獲得している方がいます。
これだけ多岐に渡った嗜好を持つ我々人間たちが、上記に挙げたような特定の楽曲に対して評価をする、ということは、
人々の感覚の中には"ある共通の琴線"があり、評価をされる曲というのは、そういった『人が持つ"普遍的"な感覚を捉えている』ということにもなりそうです。
そのことを踏まえて、
(すみません、だいぶ長くなりましたがまとめに入ります)
【音楽の今後の変化のまとめ】
ざっくりまとめると、
音楽の今後は、
『変わらない』。
だいぶざっくり説明を省いちゃいました。。
言葉を補うと、
『"メロディーに対する価値観"は変わらない』
です。
時代を超えて過去の作品が未だ色褪せることなく感動を与えてくれるのが良い例だと思いますが、
人の価値観や取り巻く環境は変わっても『本質的な人の感情の源泉は変わらない』。
怒り、悲しみ、喜び、憂い、など、それらの原因となる対象は、「自分を傷つけられた時」、「大切なものを失った時」、「成果が実った時」、「孤独に苛まれた時」など、
今も昔もたいして変わりはなく、
そうした人間の本質的な感覚・感情に訴えかけるメロディーは、探究すればするほど人間が本来持っている共通の"普遍的"なものに辿り着くことになるように思います。
何も考えず、手放しで「いい曲」と思える感覚こそ人が共通して持っている普遍的な琴線に触れた瞬間。
音楽のアプローチ(楽器や構成など)は時代に合わせて変化しても、本質であるメロディーはいつの時代も変わらぬ「いい!」がある。
【音楽を受け取る人の感情の振り幅は年齢を重ねる度に大きくなる】
また興味深いのは、人が年齢を重ねていき、様々な経験や感情を経由することで、『感受性が豊かになっていく』ということ。
涙もろくなった。
些細なことにも喜べるようになった。
人の痛みが分かるようになった。
そんな風にして、人の感情というのは成熟すればするほど、時間の経過と共にその振り幅を大きくしていきます。
人の成熟が音楽から受け取れる要素を増やし、音楽の魅力をさらに大きなものにする。
時代が進み、倫理観が育ち、様々な感覚に理解が示されるようになっていくにつれて、
(前回の記事で述べた)人の思想の発展の先にある"普遍性"と"音楽の普遍性"というのはどんどん合致していくのではないか。
突拍子もない発想を付け足していくことより、深層心理を深く深く掘り下げていくことが音楽の果たす役割を広げていくことになるのではないか。
つい10年前には携帯電話すらなかった、というこのテクノロジーの進化のスピードと、目まぐるしく変化し、拡がり続ける嗜好性と相反し、
音楽は『人間の本来の姿を映す鏡』のように時代と逆行しながらも、実は本質に近づいていくことになっている。
テクノロジーが進化すればするほどそれは顕著に、人が歌い、生み出す音楽に価値が生まれる。
音楽は人が存在する限り変わらず求められ、人の思想が発展し成熟すればするほど、どんどん剥き出しになっていく人の本質に、
"変わらない"というアプローチで寄り添っていける、そんな存在ではないかと思います。
【逆に音楽の届け方や意味合いは多様性を持って変化を続ける』
その逆に、音楽を取り巻く"パッケージ"はどんどん変化を遂げていくと思います。
もうすでに音楽を『CDショップで買う』という購買方法も『テレビから情報を仕入れる』というものも、『CDにパッケージする』ということも全て現代では形を変えています。
それはまさにテクノロジーの進化と共にあり、より効率的に、より個人の嗜好に合わせて、これからもその姿を変化させていくと思います。
いつかの自分が描いていた「CDデビューする」なんていう夢は現代では時代にそぐわない発想となりつつあります。
【総まとめ】
なので、音楽は、本質である"感情の源泉"を捉え、"メロディー"という形で表現する『変わらない魅力』を"時代にあったパッケージで届ける"ということ、
というふわっとしたまとめになりました(^^;;
"時代に合ったパッケージ"については違う機会にもっと深掘りしたいと思いますが、『音楽を受け取る窓口』が多様化していると思うので、『音楽を作ってYouTubeにアップしておしまい』にするのではなく、『届け方』までしっかり神経を張り巡らせていけたらと思います。
そして本質であるメロディーについては、人間の持つ本能的で本質的な感覚に現代社会からアプローチして辿り着けるよう、
僕は"この社会で生きる"ことをやめず、むしろ必死にもがいて足掻いて、たくさんの感情と経験を得て、
人の本質に添えるような普遍的な感覚、つまり"メロディー"を、僕の感情から忠実に再現できるよう目一杯取り組んでいきたいと思います。
『いい音楽』への挑戦はまだまだ続きますー!!
ではまた!
ソーダ・ヒロ official website 「音楽と絵と生活と」
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://soda-hiro-ff.amebaownd.com
ソーダ・ヒロ YouTube オリジナル音源公開中!!
チャンネル登録1000人目指しています!
よろしければチャンネル登録もお願いします!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
