
幽霊からの花言葉【短編小説】
その道には、いつも花が置いてあった。
カサブランカ
ユリ科ユリ属の栽培品種
大輪の花を咲かせることから「ユリの女王」と呼ばれる
花言葉は純粋、陽気
脳内で自らの記憶と照合しながら、慎重にカーブを曲がる。
昔から、花を見るのが好きだった。
小学生の時は、昼休みになるといつも図書室で花の図鑑を読んでいた。男のくせに花が好きなんて、などとからかわれることも多々あったが、同級生からのそんな視線を気にするよりも好奇心の方が強かった。
そのような学生時代を過ごしたが故に、今でも有名どころの花の特徴は大体そらんじることができるのだった。
今日はカサブランカか。バックミラーに映る黄色い花弁を一瞥しながら、前日までの記憶を手繰り寄せる。
昨日はマリーゴールド、一昨日はアネモネ、その前は月桂樹。
毎日別の花に変えられているのを、いつも仕事帰りの車から見ていた。
恐らく以前ここで誰かが事故死したのだろう、という予想はついた。職場と自宅を結ぶこの峠道は、事故が多いことで有名だった。
山肌を削り取って作ったようなその道路は、道幅も狭く、カーブも多い。そのくせ崖側には錆びたガードレールがあるのみで、まさに”いわゆる事故の多い峠道”と言われイメージするそのままの道だった。
特にちょうどこの花が置いてある付近の急カーブは対向車の存在に気づきにくく、通るときはいつも少しヒヤヒヤした。
きっとかつて命を落としたその人は運転しながら居眠りでもして、向こうからやってきたトラックと激突し、車体ごと吹き飛ばされガードレールを乗り越え崖下に真っ逆さまに……。
無意識にそんな想像が膨らみ、背筋がゾクッとする。
バックミラーからは既にカサブランカの姿は見えなくなっていた。

相変わらず、仕事はうまくいっていなかった。
大体にして、部長が悪いのだ。プロジェクトの規模に対して予算とスケジュールが足りなすぎる。
そのせいで赤字が続いていて、なのに責任はリーダーである私に押し付けられて……。
それに、最近配属された新人にも腹が立つことばかりだった。
ろくに仕事もできないくせに、毎日定時上がりで、それを指摘しようものならやれハラスメントだ労働基準法違反だ……。
ストレスでため息が出る。
上司と部下の間で板挟みにされ、結局私ばかりが夜遅くまで残業する羽目になる毎日だった。
職場での唯一の癒しといえば、夕食に妻の作った弁当を食べる時間だった。
昼食はコンビニで適当に済ませ、来る残業に向け夜に愛妻弁当を食べ気合を入れるのが日課になっていた。気が重い業務時間中、この瞬間だけは責任から解放されたような気分に浸れるのだった。
しかし、実は最近妻とは良好とは言えない関係が続いていた。
何かトラブルがあったわけでもないが、私の仕事が忙しくなるにつれ、自然に会話が少なくなっていった。そもそも私の帰宅する時間には妻は既に寝床に着いていることがほとんどだった。
前はこのようなすれ違いでよく夫婦喧嘩に発展したものだが、最近はあまりそういうこともなくなった。
そんな中、唯一妻との繋がりを感じられるのがこの弁当だった。
妻は料理が得意で、実際私は胃袋を掴まれて結婚に至った。
以前から辛い食べ物が好きな私の舌に合わせたメニューで構成されていたが、ここ最近はさらにうんと辛いおかずが増えたように思う。それに、お弁当に加え、毎日バナナを一本付けてくれていた。
私の激務を十分に理解してくれた妻が、私が夜遅くまで業務に取り組めるエネルギーを補充できるよう考えてくれているのだ。
言葉はなくとも、妻からの愛情を体で感じられるこの弁当が、私は大好きだった。
23時ごろ。
その日も部下のミスを私が一人職場に残って尻拭いしていた。
フロアには私以外の人間はとうにいなくなり、私のデスク付近以外は照明も消えていた。薄暗い部屋の中、ショボショボとした目をこすりながらモニターに向き合う。
少しは手伝ってくれたっていいじゃないか。どうして私ばかりがこんな毎日……なんて、文句を言っても始まらないのはわかっているが。
水筒のコーヒーをグビッと喉に流し込む。
うんと濃く抽出されたコーヒーが、重たい瞼に喝を入れる。これも、妻が用意してくれたものだった。夜中まで作業している私を気遣い、日に日に濃さが増していってる気がする。
はぁ。
ため息と混ざったその味は、普段より一層苦く感じた気がした。

会社を出る頃には既に日付が変わっていた。
疲労で頭がボーっとしたまま車を走らせる。
その日例の場所に置いてあったのは、数本のバラの花だった。
バラか……。
バラの花言葉は少し特殊で、本数によって意味が変わる。
1本だと「一目惚れ」
3本だと「愛しています」
99本だと「永遠の愛」
そして、108本だと「結婚してください」
バラは、私にとって特に思い入れのある花の一つだった。妻へのプロポーズの際に贈ったのが、まさに108本のバラの花束だったのだ。
脳裏に蘇ったプロポーズの映像を皮切りに、妻との思い出が次々と再生されていく。
記憶の中の妻は、どれも笑っていた。
最近は妻の笑顔なんて、ほとんど見てないな。
どうしてこんなことになってしまったのだろう。
気づけば私は涙を流していた。
あぁ、そんな、なぜ涙が……。
自分でも驚くほどに、感情のコントロールが効かなかった。情緒が暴れて抑えがきかず、堰を切ったように涙が溢れてきた。
こんな感覚は久しぶりだった。これは……。
妻への想いと、自分への後悔が溢れて止まらなかった。
そうだ、プロジェクトが落ち着いたら、久しぶりに旅行にでも連れていってやろう。一週間くらいまとまった休みを取って二人で温泉に行こう。ゆったりと湯に浸かりながら、なんでもない話をしよう。そうすれば、きっとまた……
朦朧とした意識の中、ついついそんな物思いに耽って周りへの注意が散漫になってしまい。
私はカーブの先から走ってくる対向車に気づかず、そのまま激突した。

大破した車に、ひしゃげたガードレール。
そして車のドアから身を乗り出す形で頭から血を流して倒れている、私。
目の前にそんな景色が広がっていた。
私は一体……
なんて、考えるまでもなく答えはひとつだった。
どうやら私は死んでしまったらしい。
事故に遭う直前の記憶もしっかり残っている。いつもは気を付けている道なのに、ついつい油断してしまったようだ。
生色を失った自分の顔を眺める。時々虫が止まっては数秒ほどでまた飛んで行った。
当然ながら自分で自分の姿を俯瞰的に見るのは初めてだった。
私の今のこの状態は、いわゆる”幽霊”ということだろうか。
両手を目の前に出し、指を閉じたり開いたりしてみる。私の手は確かにそこにあるし、感覚もあった。
実感が湧かず、なんだか夢見心地な気分だった。
やがて警察やら救急車やらが来て、車や私の死体を片付けて行った。テキパキとしたその様子はまるでタイムラプスで撮った映像のように、私の目の前を流れていった。
その間こちらに気がつく人は誰もいなかった。やはり私は生きている彼らには見えていないらしい。
騒ぎが収まり皆が撤収した頃には、もう朝日が昇り始めていた。
何事もなかったかのように静まり返った道路には、私とバラの花だけが残された。
あの時、道路に供えてあったバラ。
近づいて確認してみると、バラは4本だった。
4本、ということは花言葉は……
「死ぬまで気持ちは変わらない」
か。
生涯を添い遂げるという深い愛の言葉だが、事故で死んだ人に贈る言葉としてはどうなのだろう。少し皮肉を感じるな。
そう思いひとり苦笑していると、後ろから「おーい!」という声が聞こえてきた。
振り返ると、向こうで1人の男性がこっちに向かって手を振っているのが見えた。中肉中背で、年齢は恐らく私と同じくらいか。
こちら側には私以外の人影はない。
まさか私が見えているのか?
「君もここで死んだんだろうー?」
彼が左手を振りながら右手を口の横に添えて言葉を投げかけてくる。
なるほど。状況が概ね理解できた。
彼もまた幽霊ということか。
私が彼の元に駆け寄ろうとすると、彼は慌てた様子で叫んだ。
「あ、ストップストップ!近づきすぎると危ないぞ!」
私は咄嗟に立ち止まり、彼と2メートルほどの距離を空けて対峙する形になった。
危ないとはどういうことだろう。
「いや、危ないっていうのは違うか、うーん……。
君、自分が死んだっていうのはもう分かってる?」
「それは、はい」
「ならよかった。簡単に言うと、僕らはもう現実の世界にはいないんだよ。死んじゃったからね。まあ、『死の世界』とでも言うのかな、にいる」
「え、でも……」
私は混乱し、周りを見渡す。この世に既にいないとは……?
「うん、分かるよ。どう見ても現実と一緒だからね。実際、見ているこの景色自体は本物だし。どう言えばいいかな……。説明が難しいんだけど、僕たちがいる死の世界が、現実世界の形に切り取られているというか、重なっているというか……」
「死の世界が、現実に重なっている……?」
さらに混乱が加速する。
「うん、『重なってる』がイメージしやすいかもしれない。死の世界が現実世界にぴったり重なって存在していて、僕らはその上に立っているんだよ。グニャグニャの死の世界を、現実世界に押し付けて形どってる状態。現実世界にぴったりと死の世界の膜を張ってその上に立ってる状態。イメージついた?」
なんとも言えず黙っていると、彼はさらに説明を続けた。
「だから、僕らが今見ているこの景色は真に現実のもので間違いない。岩肌とか地面とかも触れるし、ザラザラとした感触もするだろ?ただ、これは正確には現実世界を触っているわけじゃなく、現実世界にぴったり重なった死の世界の内壁を触っているっていう状態になるね」
うーん。
私は左手にそびえる絶壁を見上げた。
「でも、その辺に落ちてる石ころとかは触れないよ。触れるのは地面とか壁とか、『地形』に当たるものだけ。じゃあ壁を触ってて削れた石はどうなるの?とかその辺の細かいことは僕もよく分かんない。物理法則が現実のものとは違うから、完全な説明はできない、らしい」
そう言って彼はふぅ、と息をついた。
私はなんだか分かったような分からないような……そんな状態である。
「あ、そうそう、それでさっき危ないって言ったのはね、君が死んだのってあのひしゃげたガードレールのあたりだろう?ってことは、ちょうどこの辺だと思う。ちょっと手を前に伸ばしてみてよ」
言われるがまま右手を前に突き出す。すると……
手首から先が、消えた?!
驚いて手を戻すと、手首から先は復活していた。
右手を左手でさすって存在を確認しながら、説明を求めて彼の顔を見る。
「ごめんごめん。つまりね、ここが君の死の世界の領域のうち、現実に重なってる部分とそうでない部分の境界ってこと。大体死んだ場所から半径5,6メートルくらいかな。死んだ場所を中心に広がってる、球状のエリア。そこが現実世界で自由に動き回れる範囲になってる。このラインを超えちゃうと、もう現実には戻ってくることはできなくなるからね。まぁ分かりやすく言うと、『成仏』することになるのかな。だから別に、”危ない”っていうのも違う気がして……。この世に未練がないなら、さっさと成仏しちゃっと方がいい気もするしね」
そう言って彼はハハハ、と笑った。
「ってこれ、全部僕も昔幽霊の先輩から教えてもらったこと。僕は別にこの世に未練もないけどさ、成仏するのもなんか怖いし、なんとなくゴロゴロしながら過ごしてるってわけ。あ、名乗るの忘れてたけど、僕は八木。まあ、またなんかあったら声かけてよ」
そう言うと彼は向こうに歩き出し、5メートルほど先で地面に寝っ転がった。
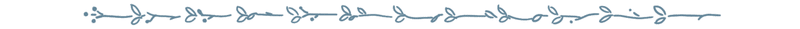
そうは言われても、まるで実感が湧かなかった。
今見ているこの景色は現実世界のものだけど、私が立っているこの場所は死の世界で……。
近くの岩肌に触れてみた。
冷たくザラザラとした感触が指に伝わってくる。
どうしたって現実のそれを触っているようにしか思えないが、これは”岩肌の形にピッタリ切り取られた死の世界の壁”を触っている感触で……。
でも、つまりはサランラップを岩肌に貼り付けてその上から触っている状態だと考えれば、感触自体は現実のものから伝わっている本物の感触なのでは?
などと考えてみる。
落ちている石ころを持とうとしてみた。触れない。空きカンも、手をすり抜けてしまう。
同様に、ガードレールも手をすり抜けてしまった。
これは危ない。知らずに寄り掛かろうとなどしてたら、そのまま体をすり抜け谷底に……。
そんな想像にひとり身震いする。
ガードレールは地形の判定ではないらしい。基準は一体どうなっているのだろう。
さらに私の思考を混乱させたのは花だった。
花は、触ることができた。
供えられていた例のバラの花。それは触ることも、手で持って移動させることもできた。
なぜ動かせるのだろう。花は地形の判定なのだろうか。
私が今手に持って移動させている花は、生きている人間から見たら空中に浮遊しているように見えるのだろう。さながらポルターガイストのように。
まぁ八木という男も言っていた通り、この世界には現実の物理法則は通用しないのだ。なぜ、など考えても無駄なことだろう。
さて、これからどうしようか。
手に持ったバラを元の場所に戻し、その場にしゃがみこんで考える。
未練は……ある。
もちろん妻のことだった。
結局すれ違ったまま、疎遠な状態で死別してしまった。
なぜ普段からもっとコミュニケーションを取れなかったのだろう。なぜもっと感謝の言葉や愛の言葉を伝えられなかったのだろう。
事故の直前にも考えていた諸々がまた押し寄せてきて、陰鬱な気持ちになる。
後悔なんかしたって死んでしまったものは仕方がない……と言っても、やはり悔やんでも悔やみきれない。
こんな状態で成仏などできっこない。と思った。
どうにかして妻に私の気持ちを伝えることはできないだろうか。
しかし私はこの世界では無力だ。
そもそもこの数メートルの範囲しか移動できないのだから、自ら会いに行くことすら叶わない。
途方に暮れ、ため息が出る。
無理なのか……何か方法は……。
ふと、眼前のバラの花がそよ風に花びらを揺らした。
その瞬間、ピンとある考えが頭に浮かんだ。
そうか、花……。

バラの花びらをちぎっては、地面に並べていった。
こちらから妻に会いに行くことはできないけれど、向こうがここに来る可能性は大いにある。
そう思った。
かつて死んだ誰かのために、何者が毎日ここに花を供えに来ていたように、妻も私を弔いにやってくるかもしれない。いや、きっと来る。
僕らは長年連れ添った夫婦なのだ。
私が好きだった花、それこそ例えば2人の思い出の花であるバラの花を持って……。
私の死を知った妻は今どんな気持ちなのだろう。
悲しんでくれているだろうか。私のように、後悔に押しつぶされそうになってはいないだろうか。
とにかく、来る。必ず来る。
そう信じるしかなかった。
来るその時に向けて、私は道路にバラの花びらを文字の形になるよう置いて、妻へのメッセージを書いた。
ちょうど、私が事故に合ったひしゃげたガードレールの目の前の位置。
物体には一切干渉することのできないこの世界で、唯一このバラの花だけ例外とされているのは、もしかすると神が私に与えた最後のチャンスなのかもしれない。
そんな気さえした。
作業はそう簡単ではなかった。
花びらを地面に置いても、風が吹けばすぐに飛ばされてしまった。車が近くを走っただけで、いとも簡単に文字は形を失ってしまう。
私はこの世界では石ころひとつ触ることができない。重りを花びらの上に置いて固定する、というようなことができないから、地面に花びらを押し付けるしか手段がなかった。
地面の少しのとっかかりにはまって固定されるよう、力一杯押し付けた。
幸い雨が降るような様子はなかったが、風は突発的に吹いたりもした。その度に、固定が甘かった花びらは風に飛ばされてしまった。その部分を修復しようとするうちに、また風が吹いて他の花びらが飛ばされた。
一文字完成させるだけでも、途方もない作業に感じられた。
風が吹くたび、体を覆い被せて花を守った。子犬を雨風から守るように、うつ伏せで地面を抱きかかえた。今の私の体には風を防ぐ効果はないけれど、地面と私の体に挟まれた花びらは、風になびきながらもそこに留まらせることができた。
それに、そうしないとなんだか私のこの気持ちでさえ、風に飛ばされてしまいそうな気がして……。

完成する頃には既に朝日が昇りきっていた。事故のあった夜から二度目の朝だった。
バラの花びらを並べて作った言葉が目の前の地面にポツンと出来上がっていた。
ありがとう
あいしてる
そのたった十文字。
ガタガタで滲んで綺麗とは言えない文字だったが、妻にはきっと伝わると思った。
僕から君への花言葉。
花で綴った、思いの言葉。
不細工な出来に苦笑しつつ眼前の言葉を眺めていると向こうから
「おーい!」と、八木に呼びかけられた。
この前とまったく同じ構図だな、と思いながら、今度は距離に気をつけながら彼の元に駆け寄った。
「しゃがみこんで何してたんだい?」
彼がそう聞いてきたので、私はことの経緯を説明した。
「へぇ、君、あの花触れるんだ」
「そうだ、八木さんも何か書いてみたらどうですか?まだ花も残ってるんで。誰かに見てもらったら、成仏する決断がつくかもしれませんし」
「いや、僕は別に誰かに思いを伝えたいとか、そういうのじゃないから。それに、僕にはその花触れないしね」
「そうですか。でもこの花、なぜか触れるんですよ。ほら」
「うん、だから、君が触れるってことは僕は触れないじゃんか」
「えっと……」
困惑した私の様子の僕を見て、彼が「あぁ」と納得した様子で説明を続けた。
「ごめんごめん、言ってなかったっけ。僕ら幽霊はこの世界では地形以外のものは一切触ることができないんだけど、一個だけ例外があるんだよ」
「例外?」
「うん。唯一、"自分のために供えられたもの"だけは触って干渉することができるんだ」
自分のために供えられたもの?
どういうことだ。頭が混乱した。
彼の言っていることが正しいとすると、この花は、私のために供えられたものということになる。
私の死を悲しんだ誰かが?いや、そんなはずがない。このバラの花は、私が死ぬ前からここに置いてあったではないか。
そう、だって実際に私はあの夜、この花に気を取られていたせいで……
この矛盾に彼も気づいたようで、独り言のように呟いた。
「あれ、でもおかしいなぁ。だってここに飾られてる花って君が死ぬ前から毎日あの人が置きに来てたもんなぁ。そういえばあの女の人、君が死んでからは来てないなぁ」
あの女の人……?
やはり意味がわからない。
まだ生きている私のために、毎日花を供えに?
誰が?一体、何のために?
その時、向こうから一台の車がやってきた。警察のパトカーだ。
私が書いた花言葉の3メートルほど手前で止まり、中から数人が出てきた。
これはいわゆる、現場検証というやつだろうか。
「あ、あの人あの人、花を置いてたの。ほら、後部座席から降りてきた女の人」
八木が指差すその先、あの人は……
妻だ。
間違いない、私の妻だった。
もう訳が分からなくて、頭がおかしくなりそうだった。
警察に連れられてここに来るのはかろうじて理解できる。現場検証に事故当事者の身内として同行させられたのだろう。
しかし、妻が私の通勤路に花を置いていたと?
そう言っているのか?
確かに私が仕事中、妻が何をしているのかは把握していなかった。朝、私が家を出てから花を買いに行き、日中のうちにここに来て置いて帰るというのは、時間的には可能だが……。
数日ぶりに見る妻は、思ったよりは疲弊した様子は見られなかった。悲しみに暮れ食事も喉を通らないんじゃなかと心配していた分、ホッと胸を撫で下ろした。
いやむしろ、肌艶が明るくなったような気さえ……。
私はパトカーの元まで近づこうと歩みを進めた。
ひしゃげたガードレール辺りまで近づいたところで、警察官と妻との会話が聞こえてきた。
「いやぁ、災難でしたね奥さん。旦那さん、まさか飲酒運転とはね」
は?
思わず足を止めた。
飲酒運転?何を言ってるんだこの警官は。
私は飲酒運転など……。
「すごい酔っ払ってたみたいですよ旦那さん。直前にお酒とコーヒーがぶ飲みしてたみたいで。コーヒーとお酒って相性悪いんですよ~。カフェインのせいで酔いが回ってることに気づきにくくなるんですって。残業も多かったみたいなんで、ストレス溜まってたんすかねぇ」
バカな。あの夜私が飲んだのはコーヒーだけだ。断じて酒など……
あの、コーヒーに?
ゴクッと飲み込んだ唾に、あの時喉元を通り過ぎた強い苦味が重なって思い出された。
「しかもね、当時すごい辛いもの食べてたみたいで。辛いものはね、血液の巡りよくするでしょ。だから全身に酔いが回りやすくなるいんですよ。
それに、バナナ!バナナもね、一説によると利尿作用があるから血中アルコール濃度が上がりやすくなるみたいで。解剖の結果見ても、旦那さん事故当時はもうフラフラだったんじゃないかって話ですよ」
辛いもの、それにバナナ……。
妻が私に毎日弁当として持たせてくれていたものだ。
でもそれは私の好みを合わせ、そして残業を乗り切るためのエネルギーをつけるために、私のことを想ってのことで……。
「旦那さん、お酒はよく飲まれてたんですか?」
「いえ、家では滅多に飲みませんでした。夫はお酒に弱かったし、ものすごい泣き上戸なんです。まさか、職場でこっそり飲んでいたなんて……」
そうだ。
あの夜の感覚が鮮明にフラッシュバックする。急に感情のコントロールが効かなくなり涙が止まらなくなった、あの感覚。
久しく飲酒をする機会がなく意識からすっぽり抜けていたが、あれはまさに泣き上戸である私が酒に酔った時特有の症状ではないか。
「お弁当は奥さんが?」
「いえ、夫が自分で作っていました。水筒もです。そんな、辛いものばかりのお弁当なんて、私、気付いたら止めてたのに……」
妻はそう言って手で顔を覆った。
どこか演技がかったセリフのように思えた。
どうして……。
どうしてそんな嘘を付く必要があるんだよ。
どうしてと言いつつ、脳内では解が一直線に結ばれようとしていた。
抗おうとしても、パズルのピースが所定の場所に自動的に吸い込まれていった。
妻が、私を…...?
運転中の私の注意を散漫にさせるために、峠道に毎日花を置いた。それも最も見通しの悪い急カーブに。私の、花を見るとその種類や花言葉や関連する思い出を連想し、意識が上の空になる性質を知っていたから。
そして自らリスクを負って犯罪を犯さずとも、私が蓋然的に事故を起こすのを待った。とは言っても実際には中々事故を起こすことなどない。
だから、酔わせてさらに意識を散漫にさせるために、酒の入ったコーヒーとアルコールの回りやすい食材で作った弁当を毎日私に持たせるようになった。
中々思うように事故を起こさない私へのもどかしさに、日に日にアルコールの量は増していき、それに比例するようにコーヒーの濃さも増していった。アルコールの苦味を覆い隠すために。
そしてあの夜、皮肉にも2人の思い出の花であるバラを置いた日、私はまんまと花に気を取られてカーブの向こうの対向車に気づかず……
仕留められた、というのか。
「旦那さんが事故にあったのはあのガードレールのあたりですか。少し近づいてみましょう」
警官の言葉に従い、妻はこちらに向かって歩みを進めてくる。視線が一瞬、地面に書いた花言葉を捉え、ぴく、と表情が歪んだ気がしたのだが……
構わず、靴で踏みつけ、通り過ぎた。
私は、あぁ、と思わず駆け寄ってしゃがみこむ。
それと同時に、目の前のバラの花びらがピースとなり、脳裏に言葉を浮かび上がらせる。
道に置かれていた4本のバラの花。
「死ぬまで気持ちは変わらない」
私が、死ぬまで
私を、殺すまで
そんな……
どうして。
嘘だと言ってくれ。
家にお金も十分入れてやっていた。
もうすぐ旅行にでも連れてってやろうと思ってた。
君はただ家で家事をしているだけで、何も不自由などなかったはずだ。
僕のおかげで楽に生活できていたんじゃないか。
また仲良くやっていけるはずだった。
僕は君を愛してるんだ。
なぜ、殺そうなどと。
どうして。
「ちょうどこの辺で対向車に激突したようですね。いやはや、ご愁傷さまです」
その時、不意に突風が吹いた。
崖の上の木々がさざめき木の葉を散らし、妻の長い髪や服をなびかせた。
そして、地面に強く押し付け固定していたはずのバラの花びらを舞い上げた。
あ、待って。
「奥さん、旦那さんがお亡くなりになられて相当ショックかとは思いますが、あまり気を落とさないでください」
花びらが風に飛ばされ、ガードレールの向こうに流れていく。
私は思わずそれを追いかける。
きっと、何かの間違いだ、そうだ。
妻が私を殺そうなんて、そんなはずないではないか。
これは全部何かの偶然で、そう、話し合えば、きっと、わかるはずで。
「現実的な話ですが、生活の方は大丈夫ですか?旦那さんのお給料もなくなってしまうわけですから」
だから、この花びらはまだ。
言葉を伝える唯一の手段だから。
飛ばされてしまうわけにはいかないから……。
「危ない!」
八木の叫び声が響く。もちろん、私の耳の中でだけ。
一枚のバラの花びらをようやく手で掴んだ。と思ったら、私の体はすでにガードレールをすり抜け、空中に放り出されていた。
「あ、それに関しては心配無用です」
振り返って崖に戻ろうとしたが、もう手を伸ばしても到底届かないところまで来ていた。
助けて。
妻の方を見ると、妻もこちらを見ていた。
目が合った。歯を食いしばり、ものすごい形相でこちらを睨みつけていた。
あぁ……
実際には空中で不自然に止まった一枚の花びらを怪訝に思って見ていただけだったのだろう。
妻は警官に顔を戻し言った。
「夫は生命保険に入ってましたので」
青空をバックにバラの花びらがひらひらと舞っている。美しい景色だった。
右も左も花びらでいっぱいで、まるで花の中を泳いでいるような幻想的な気分だった。浮遊感が心地よく、ずっとこうしていたいと思った。
しかしやがて重力は無情にも花びらの海から私を掴んで引き抜く。
体は花びら達を現実に置き去りにし、死の世界の境界へと落ちて消えていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
